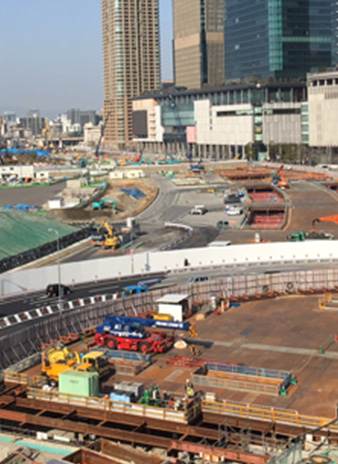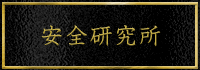(株)JR西日本カスタマーリレーションズは、1日約6,000件に及ぶ鉄道全般に関わるお問い合わせやインターネット予約などの電話・メールによるお問い合わせに、約600名の社員で対応している。神戸にある「JR西日本お客様センター」では、およそ40名のTSR※1(以下、オペレーター)がお客様からの電話に応対する。松浦は、お客様接点の最前線を受け持つコンタクトグループ電話係の担当課長として、チームを束ね応対品質の向上に指揮を執る。
※1 テレフォン・セールス・リプレゼンタティブ(Telephone Sales Representative)の略。コールセンターなどの現場で電話の受発信に従事する人たちのこと。オペレーター。

お客様センターの運営は、2009年8月までは(株)JR西日本交通サービスが担っており、同月より同じくグループ会社の(株)JR西日本カスタマーリレーションズが担うようになった。松浦のキャリアステップは、派遣社員として2007年12月からスタートする。新入社員研修では営業制度などを学び、その難易度の高さに驚くと同時に、公共性の高い企業で働く責任に身が引き締まったという。
最初に担当したのは、電話応対をするオペレーター業務。「お客様のお困りごとを解決するのが役割ですが、マニュアル通りにいかない案件への対応力が弱く、どう解決すればいいのか判断できず苦労しました」と、当時を振り返る。松浦は、先輩のASVやSV※2に質問し、サポートを受けた際の手法に学びながら、1つ1つ地道に経験を積み重ねた。その後、新人のOJT講師やメールによる「お客様の声」への回答作成にも携わるようになった松浦は、「もっといろんな業務を幅広くやってみたい」との思いから、2011年9月に入社。そこではオペレーター業務のサポートや「お客様の声」に対する回答を該当する部署に割り当てる業務など、着実に受け持つ領域を広げていった。「回答の割り当て業務は、解決するまでの方針を示して指示を出すのが基本。難しかったがやりがいもあり、視野を広げることもできました」。
※2 ASV(アシスタントスーパーバイザー)は、主にオペレーター業務のフォローを担当。また、SV(スーパーバイザー)はオペレーターとASVをフォローし、ご案内窓口の運営管理全体を担う。
 部下から寄せられる相談には的確かつ迅速に答える。
部下から寄せられる相談には的確かつ迅速に答える。
現在、松浦はオペレーター全体の業務管理をはじめ、SVからのエスカレーション※3対応、個々の実績評価や実務能力向上に向けた取り組みなど、マネジメント全般に携わる。お問い合わせを一次受付するオペレーターの応対が適切かつ正確で、お客様が納得して電話をお切りになるか、またサポートするASVの指示が端的かどうかなど、応対品質の向上にきめ細かな視線を配る。指導にあたって活かされるのは、自身がオペレーター業務を担当していた時の経験だ。「オペレーターが次のアクションに迷っていては、お客様にご迷惑がかかります。回答に時間がかかる場合には折り返しのお電話に切り替えるなど、オペレーターへの明確な指示を徹底しています」。
中でも、力を入れて取り組んでいるのは、業務改善に向け社員一人ひとりの自主性を高めることだ。「お客様応対とそのサポートの場面には改善のヒントがたくさんあります。そのヒントをつかんでいるのは、オペレーターやSVたち。彼らの気づきを実際の行動へとつなげることで、多くの改善事例が生まれています」。そのためには、「声を上げやすい職場の雰囲気づくり、そしてまずは任せてみることが大切」と松浦は言う。「任せられるとモチベーションが上がる。私自身、システム改修など大きなプロジェクトに参画し、中心になって業務をやり遂げた経験が今に活きています。自発的な行動を促し、それぞれの役割を認識させることで、個々の能力やチーム全体の課題対応力を高めています」。
※3 コールセンターにおいて、対応者自身の業務スキルでは対応しきれない案件を上位権限者に委ねることを指す。
地道な取り組みの成果は、異常時に大きな力となって発揮された。大阪北部地震、西日本豪雨、台風21号と、JR西日本管内が大規模な自然災害に見舞われた昨夏。途切れることなく輸送障害が起きる中、松浦は受電件数の増加に対応して一人でも多くのお客様へご案内するための体制づくりに奮闘した。「1日の総着信数が何万件にものぼる状況が1週間以上も続くと、だんだんオペレーターの疲労の色が濃くなります。JR西日本の支社や指令から届く情報を、ご案内に活かすために整理、更新する作業も大変でした」と振り返る。そんな中、SVは代行バスの情報や各路線の復旧状況などの資料を自主的に整理し、オペレーターが少しでも案内しやすいように工夫。また、オペレーターたちを早めに帰宅させるため、課長や係長が電話対応をした日もあった。「困難な時期を乗り越えられたのは、一人ひとりがセンターの役割を自覚し、お互いをサポートし合えたから」と、チームワークを誇らしく語る。
2018年10月からは、米子支社エリアの電話を集約し、センターでのお問い合わせ対応を開始している。こうした受諾エリアの拡大は、今後の大きな課題という。「支社の方たちのご協力のもと、エリア特性などの知識の習得に努め、地域性の高いご案内を実現していきたい」。松浦の視線の先には、センターの未来像が広がっている。

![]()
![]()
初めて入社した会社の社員研修で触れた言葉です。社会人としての基礎研修で、新入社員全員で唱和したのを覚えています。学生時代には、「自分は何をどうしたいのか」を強く意識していましたが、この言葉に触れて、自分にないものを知らされたように感じ、強烈にこの言葉が頭に残っています。仕事は互いの協力が不可欠であり、その上で必要になるのが、相手の考えを謙虚に聞き、学ぶ姿勢だと思います。今後とも「謙虚な心」を忘れずに精進していきます。