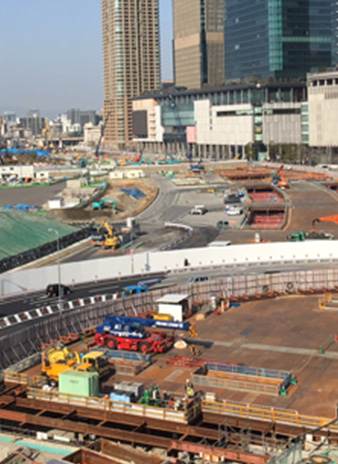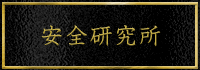「仕事をする上で大切にしていることは、連携です。自分が楽をしたい思いが少しでもあれば、連携はうまくいかないと思いますので、相手が仕事をしやすい状況を作り出すように心掛けています」。こう話すのは、福知山支社 電気課 吉田 祐彌。経験を確実に現在に活かして次につなげる若き匠を訪ねた。

1999年入社。現在、電気系統の新入社員は1カ月の新入社員研修を経た後にファーストステップ研修という独自の研修で業務知識を学ぶが、当時は新入社員研修後すぐに現場に配属され、仕事は実践を通じて覚えていった。「未熟な中で、自分の父親くらいの先輩方についていって列車見張員を担当するのが仕事でした。『列車接近!』と大声で伝えると皆さんが一斉に待避して、『よく聞こえたぞ』と言われてうれしかったことを鮮明に覚えています」。緊張の中、小さなことでもほめられたことがとても印象に残っているという。この経験は、後に吉田が部下を持った際、部下の緊張を和らげるための手法として活かされることになる。

吉田にとって転機となった業務があるという。2008年に福知山支社で踏切設備の改良を担当したことだ。踏切保安度向上対策として全社的に踏切設備の改良を実施しており、福知山支社でも短期間に支社管内全ての踏切を改良する必要があった。「福知山支社では踏切の改良は年に1つか2つを行っていましたが、全ての踏切が対象ということで一晩に複数の踏切を改良したこともありました。通常であれば始発列車までに機能確認を終えるところを、作業が追いつかず、踏切に保安係員を配置して始発列車が通過してから機能確認、ということもありました。作業の合間を縫って次の踏切改良に必要な書類の準備や手続きを進める忙しい日々でしたが、安全性向上のためにやり遂げなければならないと、無我夢中で取り組みました」。
踏切設備の改良で多忙な中、吉田は連携の大切さ、何事も細部まで突き詰めて考えることの大切さに気付いた。「正直きつい時期もありましたが、上司と仲間の間で会話を絶やさず、それぞれの状況を把握して助け合いながら仕事を進めたことで乗り切れたと思います。また、作業にはグループ会社、協力会社など多くの方が関わります。限られた時間の中で作業を完遂するためには、そうした方々としっかりと連携を取る必要がありました。そこで私は、関係者が円滑に行動できるよう、スケジュールや担当者を細かく定め、確実に共有することに努めました。いつ、どこで、誰と行うのか、場所はなるべく移動ロスが発生しないようにするなど、皆さんが迷わないように配慮しました。思いやりの気持ちがスムーズな作業につながるのではと思います」。その後吉田が拠りどころとする要素を身に付けたエピソードだ。
現在は、福知山支社で年間の工事計画の策定とそれに伴う予算管理を担当している。「信号設備は故障しない設備、保守しやすい設備にするため、先を見据えた計画を立てなければならず、それらを考慮した予算策定を行っています。また、将来的に何度も設備を移設しなくてもいいように、効率的かつ無理のない工程を組むように心掛けています。私自身が過去に経験したことを踏まえ、相手の立場に立って物事を考えるようにしています」と語る吉田。現場で保守・施工をした経験、さまざまな関係者と仕事をした経験、吉田はあますことなく次の仕事に活かしていく。「これまでに、信号に関するさまざまな業務を経験してきました。幅広い知識を蓄えて、何事にも手本となれるような社員になりたいです。若手には、『これはどうなっているのか』など疑問を持ちながら仕事をしてほしいと思います。私の職場の方針の一部でもある『気づきの感性向上』を心掛け、若手ならではの感性を大切にして仕事をしてほしいですね」と、後進にエールを送った。


配線盤の端子