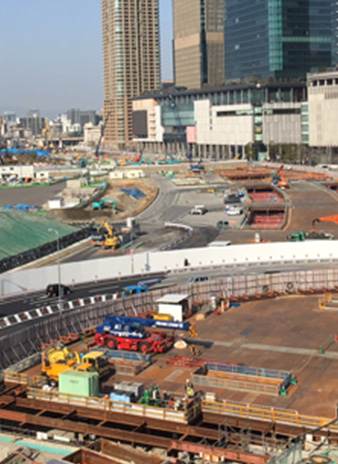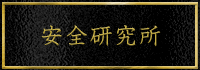当社は、女性の能力が十分に発揮できる環境を整備することにより、女性をはじめとする全ての社員が働きがいを持っていきいきと働ける企業となることを目指し、2016年の3月に「女性活躍に関する行動計画」を策定した。今回は、2度の育児休職を経て復職し、建築区の係長として活躍している清水に焦点を当て、仕事と家庭の両立のヒントを探る。

平成9年に入社した清水。修繕や改良工事の設計・計画を担当することとなったが、当初は分からないことや上手くできないことが多く、あまりの悔しさにトイレへ駆け込んで泣いたこともあったという。
またある時は、ベテラン社員に教えを
その後は、持ち前の負けん気で仕事に没頭し、知識と技術を身に付けていった清水。そして入社して4、5年後には能登川駅の橋上化工事の計画から設計・積算までを担当するなど、徐々にその手腕が認められ、重要な仕事を任されるようになる。
仕事に楽しみを覚え始めた頃、家庭面では大きな転機を迎えることに。そう、出産である。1年の育児休職を経て職場に復帰したが、初めはとても苦労したと清水は語る。「夫婦共働きで、お互いの両親は遠方におり、親しい知人やご近所さんもいなかったので、子どもが病気になった時などはとても大変でした。今思えば、きちんとファミサポ※に登録しておけば良かったと思います」。
仕事も家庭も、これまでのレベルを維持しようとすれば時間がいくらあっても足りないと考えた清水は、発想を変えて「仕事も家庭も、定めた時間の中でいかに効率的に物事を行うか」考えるようにしたという。「仕事面では、所定の労働時間内で業務を行う習慣ができましたが、どうしても周囲には迷惑を掛けてしまいます。それでも、『辞めるよりはうんとマシ』と思うようにして、ここまで続けてきました」。
※ ファミリーサポートセンターの略。地域において育児や介護を助け合う会員組織で、市区町村が設立・運営している。
清水は現在、大阪建築区の係長として、年間の工事発注や契約スケジュールなどの調整や部下の指導・育成を行う一方、家庭では12歳の長男と10歳の長女の2人の母として子育てに励んでいる。両立の秘訣について、清水は「できることをできる範囲で頑張ること」と語る。
そして、後輩社員に伝えたいこととして「つらい時には身近にいる上司や先輩に相談してほしい」と述べた。続けて、「特に女性社員の場合、妊娠・出産・育児と仕事との両立をどうすべきか悩むことがあると思います。過去にはそれらが原因で辞めた社員も多くいますが、今ではさまざまな制度が整備されており、社会的にも会社的にも女性の労働力が貴重であるという認識が浸透してきています。『周りに迷惑を掛けてしまう』という心配は、するなと言っても無理かもしれません。しかし、辞めてしまうよりは、しばらくは迷惑を掛けてでも仕事を続けた方が、長期的に考えれば周りも自分も幸せです。自分だけが頑張る必要はありません。周りを頼り相談しながら、できる範囲で頑張ってください」と熱いエールを贈った。

 現場での一幕。修繕の勘所を部下に伝授する。
現場での一幕。修繕の勘所を部下に伝授する。 限られた時間の中で、積極的にコミュニケーションを図る。
限られた時間の中で、積極的にコミュニケーションを図る。

大阪建築区
嶽山 隆浩区長
清水係長は、設計・計画業務の経験が豊富な上、グループ会社への出向経験もあり、業務知識が豊富です。その的確な判断力や関係箇所との事前調整力など、日々の仕事を行う上で若手社員からベテラン社員まで皆が助けられています。また毎日忙しい中、若手社員への的確なアドバイスや自己研鑽に取り組む姿に感心しています。
これまで培った知識・技能に加え、責任感や前向きな取り組み姿勢なども、若い世代に継承してくれることを期待しています。