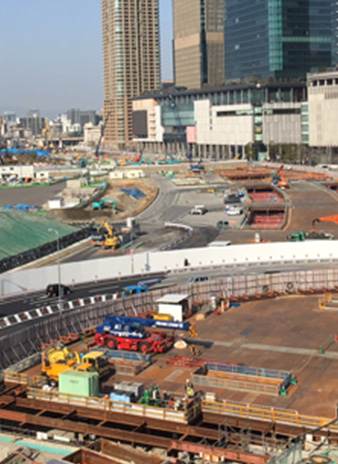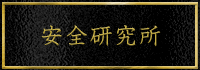当社は、近代日本の成長をけん引してきた産業遺産として歴史的価値の高い蒸気機関車(以下、SL)を国鉄から数多く継承しており、これらを後世に伝えることを社会的使命としている。今回の主役は、京都鉄道博物館に隣接する梅小路運転区でSL技術を受け継ぐフロントランナーとして活躍している今井將博だ。

平成10年に、鷹取工場(現 網干総合車両所)でそのキャリアをスタートさせた今井。入社当初はもっぱら電車の検修に従事していた。その頃の思い出を尋ねると、入社6年目に「配管班」へ配属された頃を挙げてくれた。「実は、配管作業がとても苦手でした。例えば配線作業は、図面を見れば電気の流れがはっきりと書かれているので理解できます。一方、配管作業は、図面を見ても空気の流れが書かれていないので今ひとつよく分かりません。そのせいで、当初はとても混乱しました」と振り返る。「しかし、苦手だからといって逃げるのは嫌でした。仕事を覚えるために、現場の班長に頼み込んで、始業1時間前から空気の流れや装置の仕組みを教えてもらっては、図面にポイントを書き込んでいきました」。

その負けん気と粘り強さで配管に精通し、配管技能士の国家資格を取得するまでになった今井。次の一歩として、自分で書き込んだ図面を利用して新人作業者のためのマニュアルも整備した。「それまでは教育用のマニュアルがありませんでした。後輩が私のように苦労しないように、分かりやすさに重点を置いて作り込みました」。
今井に転機が訪れたのは入社16年目の平成25年。上司からSLの技術継承の受け手を打診されたのだ。「その頃は、SLについての知識は全くなく、具体的なイメージが湧きませんでした。しかし、会社としてSL検修の技術継承に力を入れ始めていたのは知っていたので、まずはチャレンジしてみようと思いました」。そうして梅小路運転区に配属された今井だが、当初は戸惑いの連続だったという。「それまでに取り扱っていた電車とは違い、不具合が発生したからといってすぐに予備品があるわけではありません。先輩が必要に応じて自ら部品を作るのを見て衝撃を受けたのを、今でも覚えています」。

それでも、先輩の作業を必死に追い、少しずつノウハウを身に付けた今井は、次第に周囲から一目置かれる存在となる。「配属当初から技術を教わっている師匠のような先輩社員がいるのですが、いつしか周りの人から『(先輩社員の)後を引き継ぐのはお前しかいない』と言っていただけるようになりました。それが、とてもうれしくて」と言って顔を綻ばせた。
いまや検修係長を務めるようになった今井。若手社員への指導や転入者教育に加えて、車両管理や工事契約を行うなど、己の技術を磨くだけでなく、係長として周囲のサポートをする機会が増え、あらためてSL検修に携わる誇りを感じるようになった。「SLは『生きた鉄の塊』です。どのように検修するか、その方法は時々によって異なります。日々状況が変わる中で柔軟に対応する必要があり、苦労もひとしおですが、そのぶん検修を終えての達成感ややりがいを感じることができます。これからも、職場の皆とともに苦楽を分かち合いながら、先輩方のSLに対する誇りや技術を受け継ぎ、いつしか『匠』と呼ばれるようになりたいと思います」。今井は前を見据えて力強く述べた。
 検修中の風景。集団で作業に取りかかる。
検修中の風景。集団で作業に取りかかる。 打ち合わせの一幕。
打ち合わせの一幕。

梅小路運転区
藤谷 哲男区長
今井係長はこれまで、SL検修技術の習得のために先輩方から図面の見方や作業方法、機能などの指導を受けてきました。日々、作業服や顔を真っ黒に汚し、昔ながらの厳しい指導を受け、やっと匠の門を開けたと思います。
「真の匠」となるためにも、日本の産業近代化の原点であるSLの原理や装置個々の機能、役割と重要性を把握し、メーカーをも指導出来る加工技術を身に付けるとともに、人間的にもさらに磨きを掛け、先輩や若手社員に慕われる「頼り甲斐のある技術者であり指導者」となることを期待しています。