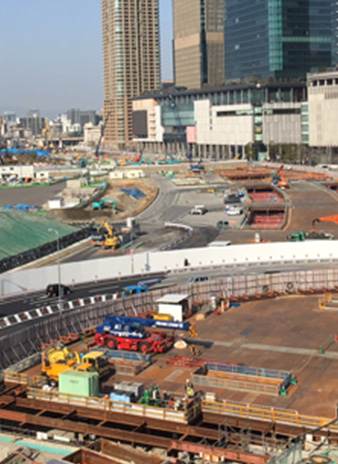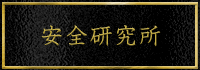広島新幹線保線区のとある会議室。ここで、月に1回の勉強会が開催されていた。今回のテーマは「リスクアセスメント」。中から大きな声が聞こえてくる。「皆さんは『墜落』と聞いても、業務に関わりがないと思うかも知れません。でも、例えば『樹木の伐採』を行う場合を想像してみてください。我々の業務でも十分に起こり得る事故なのです」。中をのぞいてみると、説明用のスライドの前で身振り手振りを交じえ熱心に講義を行う男がいた。今回の主役、広島新幹線保線区の係長、鳴戸史憲だ。

鳴戸は現在、係長として企画業務を担当している。「企画の業務は、一言で言えば『保線区の何でも屋』といったところです。年間計画をはじめ、予算管理、材料管理、訓練の計画作成・実施、社員教育など、あらゆる業務を行っています」。そんな鳴戸が冒頭のように勉強会の講師を務める際、皆の理解を深めることに力を入れていると言う。「相手が頭でイメージしながら聞けるように、できる限り写真や図入りの資料を準備し、実作業を想定した具体的で分かりやすい説明をすることを心掛けています」。
このようなこだわりは、入社直後に苦労した自身の経験がもとになっている。「入社当初は、周囲から『鳴戸が分かれば誰でも分かる』と言われるほど理解力が乏しく、仕事を覚えるのにとても苦労しました。どんくさいこともあり、先輩から『邪魔をするなら手を出すな』と怒られる日々でした。そこで私は、自分で何度も図を書いたり模型を作ったりして、頭で作業のイメージができるようにしました。すると、たとえ作業で失敗したとしても、『何が悪かったのか』が分かるようになり、ただ漠然と身体を動かすよりも何倍も早く技術を習得できるようになりました」。

その後、たくさんの経験を積み重ねて誰からも頼られる存在となった鳴戸だが、今でも忘れられない失敗がある。「平成21年のころ、不具合事象を上司に報告する際に、状況の詳細を把握する時間がなかったこともあり、憶測でものを言ってしまいました。その結果、別の箇所からの報告との間に
将来の展望について、鳴戸は語ってくれた。「私はJR発足後に初めて高卒で入社した社員の1人ですので、キャリアの先頭に立っていかなければならないという自負があります。後輩たちも、私が進む道を少なからず見ていると思います。そこで、彼らに『どんくさい私でもここまでできる』という姿を見せることで、『この人の後について行きたい』と目標にされるような人物になりたいと思います。そのためにも、保線屋として優れた技術力を身に付け、何でもできるような『スーパー係長』を目指していきたいと思います」。フロントランナーとして、鳴戸はさらなる高みを目指す。
 競技会に向けた訓練。真剣な眼差しで後輩を指導する。
競技会に向けた訓練。真剣な眼差しで後輩を指導する。 打ち合わせの一幕。後輩が作成した資料に誤りがないか、丁寧に確認する。
打ち合わせの一幕。後輩が作成した資料に誤りがないか、丁寧に確認する。

新幹線管理本部 広島新幹線保線区
松岡 啓二区長
JR採用1期生の彼は、年齢の離れた先輩から「またかよー」と言われるほど遠慮することなく聞きまくって知識・技能の向上に努めています。係長となった現在、職場のけん引者として何事にも妥協することなく前進してくれています。後輩社員からの信頼も厚く、身近な目指すべき先輩として活躍しています。特にこの3年間は、北陸新幹線の保守業務に向かう社員や、経験の浅い社員への指導に、その力を注ぎ込んでくれています。高速鉄道の安全を限りなく追求し続ける人材として、さらなる飛躍を期待しています。