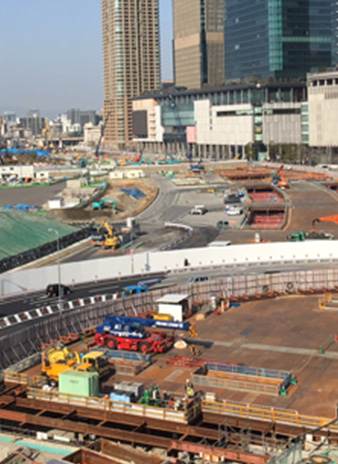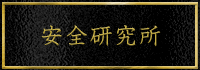- 昭和57年国鉄入社。以来、米子エリアの土木現場でその手腕を発揮する。平成13年にはその技術力を買われ、ジェイアール西日本コンサルタンツ(株)に出向した経験も持つ。平成27年から現職。厳しい中にも優しさのある指導に定評がある。
米子駅にほど近い米子土木技術センターのオフィス。中をのぞきこむと、開放的な雰囲気の職場の中で一際明るい声が響いてきた。その声の主こそ、今回の「匠」である二宮だ。
二宮は現在、区所でただ一人の助役として、「検査」「企画」「工事」の3つに分かれているグループを取りまとめている。検査グループが土木構造物を検査した結果をまとめた「検査報告書」や、工事グループが工事発注するための施工方法などを記した「工事立案書」の内容を確認して決裁するのも、彼の仕事だ。

しばらくすると、若手社員が工事立案書の決裁を求めてやって来た。普段は明るく、軽口も叩く二宮だが、この時は真剣な表情を見せる。一通り目を通したあと、おもむろに「この施工方法の意図は?」「ここの課題に対する解決策は考えているか?」と、次々と質問を浴びせていった。思わず若手社員が言葉に窮すると、少しばかりのヒントは与えつつ、「もう一度、自分で考えてくるように」と言って追い返したのだった。
二宮は言う。「現在の若手社員は、検査・工事ともに外注化が進み実務が減る中で、実務を請け負う会社の監督・指導を行わなければなりません。だからこそ、社員が現在の業務の中で実務能力向上を図れるように指導することを心掛けています。そのために、質問攻めにして『施工会社に言われるがままに資料を作っていないか』『自分の考えをしっかりと反映させているか』をチェックしているのです」。

二宮がこのような指導を行っているのは、過去の経験に拠るところが大きい。それは、今から約20年前。彼が30歳の頃、とある鉄桁の老朽取替工事を任されたのだ。「上司から、『桁の設計計算・製図・桁架設計画までの全てを自分でやってみろ』と言われました。初めての大役で、身の引き締まる思いとともに、『やってやろう』と意気込んだのを覚えています」。しかし、程なくして頭を抱えることとなる。「鉄桁からスラブ桁への取替工事だったのですが、めったにしない工事のため、やり方を知っている先輩がおらず、全てが手探りの中で仕事を進めなければなりませんでした。例えば『コンクリートの中の鉄筋の量はどれぐらい必要か』といった基本的なことも、一から調べていきました」。
そうやって、分からないことを資料などで調べて考え、理解して設計しては、また分からないことにぶつかる…をひたすら繰り返した。こうした二宮の努力のかいもあり、工事は無事に計画どおり完遂することができた。
「桁が架かり、初列車が通過した時はとても感動しました。そしてこの経験を経て、自分の仕事の仕方が変わりました。つまり、『分からないことがあれば納得するまで調べる』『前例にとらわれずに、より良い方法がないかを考える』ようになりました」。
若かりし頃を振り返ってみて、二宮はあらためて感じることがあると言う。「私が若手と言われていた頃、あえて難しい仕事を私に担当させる上司がいました。当時は分からないことを教えてもらいながら、がむしゃらに仕事をしていましたが、この時の経験がなければ、今の私はないと思います」。「だからこそ…」と二宮は続けて、「若手社員には『若いうちに苦労をたくさんしよう』『一生懸命勉強しよう』と言いたい。そして私は、当時私を鍛えてくれた上司のように、若手社員ががむしゃらに仕事に取り組めるような環境を整えてやりたいと思います」。そう言って笑顔を見せる二宮の瞳には、確かな決意が宿っていた。
 疑問を感じた時は横着せずにマニュアルなどを見て確認する。
疑問を感じた時は横着せずにマニュアルなどを見て確認する。 支社勤務時代の一幕。ファシリテーターとして皆の意見をまとめる。
支社勤務時代の一幕。ファシリテーターとして皆の意見をまとめる。

山田 雅
二宮助役は、豊富な経験・技術・知識を持っており、周りからの信頼も厚く、また、気さくな性格で人望を集めています。日々の忙しい業務の中、若手社員からの些細な質問などにも耳を傾け、一緒になって問題解決に取り組んでいただけるので、若手社員は意欲的に仕事をすることができます。私も鉄道土木技術者として、二宮助役に一歩でも近づけるよう技術・技能を身に付け、将来は後輩に指導できるよう頑張ります。