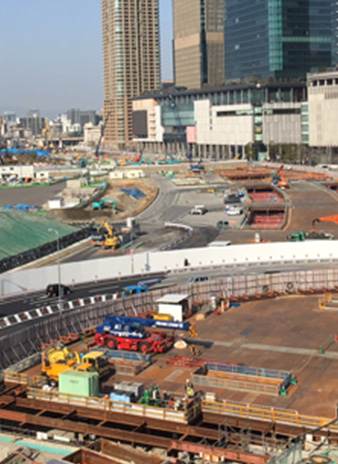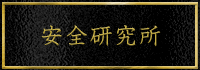- 昭和56年国鉄入社。主に敦賀駅で運転業務に従事したのち、金沢支社人事課での任免・採用アドバイザー業務を経て、平成11年から金沢支社輸送課で指令員としてのキャリアをスタート。以降、大口団臨や、多客輸送などの波動計画、指令長、総括指令長などの業務を歴任し、平成23年より指導監。訓練計画の策定やそれに基づく指令員育成に力を注いでいるほか、現在も月に数回は総括指令長として指令所の指揮を執っている。
「雨規制がかかったぞ、まず何するんや?正確さが必要なのは当たり前。いかに迅速に判断するかが大事やぞ」。時折笑顔を見せながらも、厳しく若手指令員の指導にあたる山本。この日は、梅雨の時期をにらんだ雨運転規制時の取り扱い訓練だ。訓練は、乗務員や駅運転係員などの関係者役を全て配して実戦さながらの形で行われる。「指令員は、列車を止める、運転を再開するなどの判断を求められます。その判断力を養うためには、過去の異常時を振り返ることはもちろん、それを踏まえてさまざまなシーンを想定した訓練を行うことが効果的です」。

入社以来、駅運転業務を中心に輸送畑を歩んだ山本が、指令員としてのキャリアをスタートさせたのは平成11年。「輸送畑とはいえ、当時は2分目ダイヤも読めませんでした。でも、数カ月後に控えるCTC※導入に向けた準備などで指令所全体が慌ただしく、先輩に一から教えてもらえるような状況ではありませんでした。しかも、当時は業務標準もなかったので、過去の異常時の指令電報や指令券、ダイヤなどを見返すことで実際の事例を学び、自分が判断するための『引き出し』を増やしていきました」。
さまざまな異常時を経験することで、さらに『引き出し』を増やし、総括指令長、指導監となった山本だが、平成23年冬には、今も忘れることのできない痛恨の経験をした。記録的な大雪で北陸本線の列車が運転を見合わせ、懸命の調整にもかかわらず、再開まで丸1日以上お客様を車内に閉じ込めてしまうことになったのだ。「指令の難しさをあらためて実感しました。異常時はケースバイケースで、一つとして同じ状況はありません。単に過去の事例を学ぶだけでなく、日ごろからそれらを組み合わせてさまざまな場面を想定し、シミュレーションしておく必要性を痛感しました」。
現在、山本は月に数回の総括指令長としての勤務を除くと、もっぱら若手指令員の指導にあたっている。「私が指令員になった頃と比べると、最近はマニュアル類もずいぶん整備されましたし、教育体制も整っています。ただ、マニュアルに頼り過ぎると、マニュアルどおりの判断しかできないとか、マニュアルに載っていないことは分からないといったことになりかねません。また、訓練をいくらやっても、教えられたことしか分からないようでは困ります。その都度異なる状況のなかで適切な判断を下せるようにするため、訓練の際には、必ず『次に何をすればよいか』『なぜそうするのか』などを自分で考えさせ、判断させる指導を心掛けています」。

北陸新幹線金沢開業に伴い、金沢以東の在来線は当社から経営分離され、指令所の体制も大きく変わった。しかし、体制は変わっても鉄道の安全を守る指令の使命は変わらない。若手への世代交代や体制の変更などを見据えながら、今日も山本は指導に力を入れる。
※列車集中制御装置。信号や分岐器の連動装置を指令所などにて遠隔制御するシステム。
 総括指令長として関係箇所に指示を送る。
総括指令長として関係箇所に指示を送る。 早期復旧には、工務指令との連携が欠かせない。
早期復旧には、工務指令との連携が欠かせない。 雨運転規制の早見表。
雨運転規制の早見表。

酒井 利昌
山本指導監は、後輩指導にとても熱心な方で、新任指令員だけでなく、中堅指令員にも注意を払って必要なアドバイスをしてくれます。また、部下の言うことにもまずは耳を傾けて聞こうとしてくれます。何よりすごいのは、ルールなども固定観念にとらわれず、変えるべきところは変えていく柔軟性も持ち合わせているところです。私も先輩社員に「お前になら任せられる」と言っていただけるような指令員になるために、山本指導監の技術や姿勢を継承していきたいと思います。