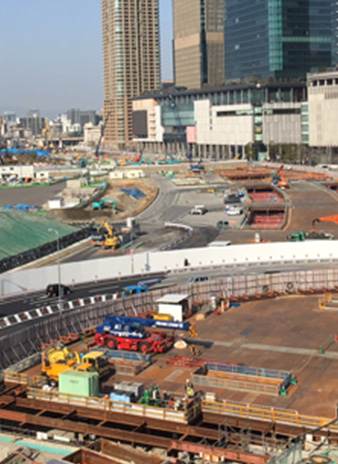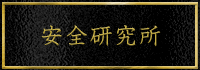- 昭和58年日本国有鉄道に入社、松任工場に配属される。職場は平成9年に統合され金沢総合車両所となったが、一貫してこの地で勤務し、窓や座席など室内設備の組み立てから電気機器の検査、改造工事まで担当する。現在、車両科に配属され、規程類の整理・見直しや新世代車両の検査体系の整備などを率先して推進している。
入社以来30年間、車両を肌で感じるこの仕事を愛し、お客様に安全・快適な車両をお届けすることにこだわり続けている高橋。「現場第一」を胸に、同僚社員が作業しやすい環境づくりに日々奮闘している。
平成14年、高橋は電気艤装班のリーダーを任された。ベテラン社員と若手社員のはざまに位置するリーダー高橋が感じる職場の最大の課題は、若手社員の技術力向上であった。同様に、世代間のコミュニケーションが不足していたことも頭を悩ませていた。高橋がたどりついた結論は、「若手社員が自発的に勉強しなければ技術力の向上はあり得ない」であり、若手社員を講師役としての勉強会をスタートさせた。「事前に勉強しなければ、講師として人に教えることはできません。また、難しい技術については、経験豊富な先輩がポイントを教え、コミュニケーションをとる機会も作れました」。
勉強会を通じて、若手社員の意欲が目に見えて向上し、ベテラン・若手一体となって解決しようという姿が多く見られたという。「環境を変えるためには、新しい風を吹かせたり、各自の目線を変えることが必要です。今振り返ると、『みんなで乗り越えた』と感じられます」。

平成17年に発生した福知山線列車事故を重い教訓として、車両部門ではさまざまな省令対応工事を実施することとなった。極めて短い期間の中で迅速・確実に施工しなければならず、当然ながら寸分のミスも許されない。技術管理を担当していた高橋は、「どうすれば現場の社員が作業しやすくなり、ミスが発生しないだろうか?」と考えた末、6カ月かけて工事や車種に合わせたチェック表を作り上げたのである。これには、工事スケジュールや手順に基づいた確認事項のみならず、工事での注意すべきポイントなどが分かりやすく記載されており、安全・確実に作業を遂行するための職場の手引きとなった。
これは一例であるが、こうした安全に対する弛まぬ考動が認められ、高橋は平成19年に第一回目の安全推進社長表彰を受賞している。
そんな高橋の「考動力」の原点は、若手のころ、先輩から図面を見せられ、簡単に説明するように言われたが、全くわからず、頭が真っ白になった時だという。その日から必死で自己研鑽に努めるようになった。図面や資料を持ち帰り勉強し、疑問点は自分の力で考え抜き、そして先輩に聞いたのである。結果、技術力だけでなく、探究心や課題解決力までも大いに養われることとなったのであろう。

高橋は言う。「まだまだ、私は匠ではありません。もっともっと勉強しなければいけない。『机上では語らない』人を目指したいと思っています。だから、作業場に足を運んで、車両と触れ、仲間と話すことに重きを置いています。若手社員もマニュアルに頼るだけでなく、マニュアルに書いていない部分をどう学ぶのかしっかり考えてほしいのです」。
高橋が見つめる先には常にお客様があり、現場を想い、安全で快適な車両を追求していく姿勢は、今日も変わらず続いている。
 規程類の整理や見直しを行う。
規程類の整理や見直しを行う。 作業に合致した準則を整備するため、1日に何度も足を運ぶ。
作業に合致した準則を整備するため、1日に何度も足を運ぶ。

宮口 直起
高橋係長は、ONとOFFがしっかりしていますが、親しみやすく、ミーティングのときも話しやすい雰囲気を作ってくれ、自分の意見をしっかり聞いてくれます。
特に尊敬するところは、最前線での業務を第一に考え、作業しやすい環境作りを追求してくれているところです。私も将来、高橋係長のように周りの方々に気を配れ、高い技術力を持った人になりたいと思います。