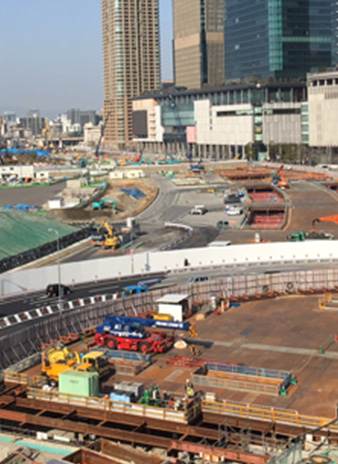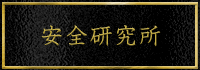- 昭和50年に国鉄入社。機械信号機・ワイヤー・分岐器などの保守、管理などに携わる。さらに能力を磨きたいとの思いから、平成10年から5年間、西日本電気システムへ出向する。ここでは、設計技術、工事の施工管理など一からモノを作る技術を学ぶ。
平成20年6月から浜田鉄道部の助役として、若手社員の教育にも全力を注いでいる。
山陰の地で35年以上、踏切や信号機をはじめとした電気設備に向き合い続けてきた匠がいる。浜田鉄道部の山口助役だ。今回は、自らが保守する機器に、錆を見つけると直ちに塗装し、機器の周りに雑草を見つけると、一本でも抜かずにはいられないという、電気設備をこよなく愛する山口を紹介したい。
「電気設備は生き物です。人と同じで性格が個々に違う。だから、家族のようにとことん向き合い続けることが大切です」。
昭和50年、山口は国鉄に入社した。当時、技術の習得は、教えてもらうよりも自分で学ばねばならなかった。先輩に必死で食らいつき、技術を見ては盗んだ。工事に携われば携わるほど、基礎となる知識の大切さを知り、設備の図面などから自身に不足する知識の習得に努めた。
経験を積むにつれ、さらに能力を磨きたいという思いが強まり、志願してグループ会社の西日本電気システム(NESCO)への出向を希望。平成10年から5年間の出向生活では、一からモノを作り上げるまでの設計技術や設備の原理を学んだ。JRで学んできた技術や知識は、完成品を修理・検査するためのものであり、モノの細部まで踏み込まねばならないNESCOでは全く通用せず、毎日寝る間も惜しみ必死で勉強したと言う。この並々ならぬ努力が、今日の山口を支えているのである。

技術・技能の習得に余念のない山口だったが、過去に信号設備の配線1本の確認ミスで列車を止めてしまったことがある。「ショックでたまりませんでした。でもこの失敗で仕事の重要性や確認作業がどれだけ大切か学びました。ナット1個、ビス1本、配線1本が確実にできていなかったら、事故につながる可能性があるのです」。以来、若手を指導する時は、必ずこの体験談を伝え、ミスをさせないよう心掛けていると言う。山口は語る。「過去の事故や失敗から学ぶことはたくさんあります。同じことを繰り返さないためにも、今までの事故を自分がしたと思い、共有するのです」。

現在、電気助役となった山口は、若手を育てることに人一倍の愛情を注いでいる。
昔に比べ、機器の故障が減ったこともあり、若手は現場に出る機会が少ない。だからこそ、異常時は一緒に対処し、技術力とともに自信を付けてもらうように心掛けている。「何かが起きると、若手はすぐマニュアルに頼ろうとするが、根本を分かっていないと難しい」。と山口は言う。
「何でこうなったのか?なぜこういう風にしないといけないのか?常に考えながら業務をしてほしい。それが、どんな場面にも対応できる実務能力につながっていく」。貪欲に身に付けた技術力や知識から、異常時対処の際の勘所を会得した山口が、若手に伝える極意がこれである。
「早く若手が一人前になってほしい…。若手が育つことは私の喜びでもあります」。若手を指導する山口の目や声は、わが子に接するように温かかった。
 切替工事のためにグループ会社も含めて事前打ち合わせ。
切替工事のためにグループ会社も含めて事前打ち合わせ。 現場に行く前に若手と荷物の確認。
現場に行く前に若手と荷物の確認。 柱上作業時における安全帯使用について指導中。
柱上作業時における安全帯使用について指導中。

山根 拓斗
山口助役は、真面目な方で、仕事の重要性を認識され、ルールや基本の大切さを日々厳しくご指導してくれます。仕事、特に現場では本当に厳しい方ですが一旦仕事を離れると人に対する気遣いなど心引かれる父親のような存在です。
現在私は、ベテラン社員の助けを借りながら切替工事の計画を進めています。将来的には、山口助役のように安全に関することに対して厳しくものが言え、かつ周囲の人間に気遣うことができる指導者になりたいと思います。