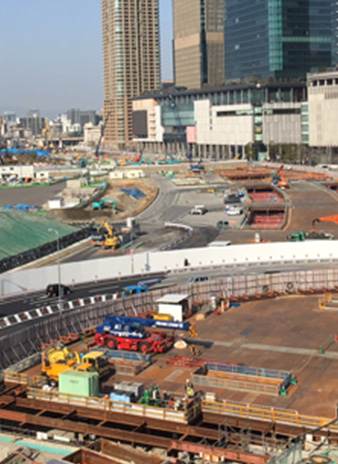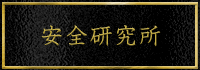自然災害に対する安全対策
地震対策

高架橋柱耐震補強

逸脱防止ガード

N700S
阪神・淡路大震災以降、構造物の耐震補強を進めており、これまでに山陽新幹線では高架橋柱(せん断破壊先行型)や落橋防止対策、トンネルの工事が完了しています。在来線についても省令に基づく高架橋柱(せん断破壊先行型)や落橋防止対策の工事が概ね完了しています。現在は、鉄筋コンクリート橋脚や駅舎等の耐震補強対策について順次進めているところです。
加えて、今後発生が予想される南海トラフ巨大地震に備え、高架橋柱(曲げ破壊先行型)のほか、盛土や鋼製橋脚、ホーム上家等の耐震補強も順次進めています。
また、山陽新幹線では万が一車両が脱線しても車輪が大きく逸脱することを防ぐ「逸脱防止ガード」の敷設や高架橋上の電柱の耐震補強を進めています。
最新車両(N700S)においては、地震発生時のブレーキ距離を従来車両より5%短縮し、停車した後に停電状態であっても、お客様の避難が容易な場所まで自力走行が可能となるバッテリ自走システムを搭載しています。
加えて、現在運行している車両(N700Aタイプ)に対しても最新車両と同等となるようブレーキシステムの改良を行います。
浸水対策
2019年10月の台風第19号による河川氾濫で、北陸新幹線の車両が浸水し甚大な被害を受けたことを踏まえ、ハード、ソフト両面から被害の軽減に向けた取り組みを行っています。
鉄道運行に著しく影響を及ぼす重要施設および車両のうち、計画規模降雨(※)で浸水が想定される施設を対象に、浸水防止に向けたハード対策を進めているほか、ソフト対策としてあらかじめ浸水が想定されるエリアから車両を避難させる計画を策定しています。
※河川整備において基本となる規模の降雨 年超過確率1/数十〜1/200 程度
強風対策

湖西線 防風柵
琵琶湖の西側を走る湖西線は、強風による運転見合わせや徐行運転が比較的多く発生する線区のため、防風柵を設置することで運転規制の低減を図っています。
また、他社から提供される高解像度の気象予測データを、当社のAIモデルを用いて解析することにより、風速・風向を予測するシステムを2025年2月より導入しています。これにより、特急「サンダーバード」の不要な迂回運転の削減やそれに伴う北陸新幹線の安定性向上、湖西線内の普通列車の運転取り止め区間の短縮に取り組んでいます。
津波対策
各府県の津波浸水想定に基づき、線区のハザードマップを作成するとともに、浸水エリアとなる箇所に「浸水区間起点・終点標」を設置しています。
南海トラフ巨大地震による津波被害が想定される紀勢線については、上記に加え、市町村の指定避難場所に誘導する「避難方向矢印標」と「線路外出口標」を設置しています。
また、和歌山エリアでは、沿線の方々の迅速な避難を可能にする壁蹴り式避難路の整備や、ご乗車中のお客様が取り扱うことができる避難用梯子の車内への整備等を行っています。

設置イメージ

壁蹴り式避難路

避難用梯子
降雨対策
斜面防災
近年、雨の降り方が局地化かつ激甚化しています。斜面や線路に多量の雨水が流れ込んだ場合は、斜面崩壊や土砂流入の可能性が高まることから、構造物の安全性を向上させるために、盛土や沿線の斜面の補強等を行う斜面防災工事を順次実施しています。また、沿線の斜面を定期的に確認するとともに、必要な箇所では徐行するなど、対策を実施しています。

盛土区間の補強

沿線の斜面の補強

沿線の斜面の確認
レーダー雨量の活用
降雨時の運転規制は、これまで平均12km間隔で設置されている鉄道雨量計での点的な観測によって実施していました。これに加えて、連続的かつ面的に観測できるレーダー雨量を新たに用いることで、これまで捉えることが難しかった雨量計間での局地的な大雨を早期に把握することができ、さらなる安全性の向上を図ることが可能となりました。2022年度に当社管内の在来線全線区を対象に導入が完了しています。

在来線における運転規制の支援強化
自然災害等に伴い、列車の運転を見合わせる場合や徐行が必要となった場合、これまでは指令員が複数のシステムを取扱う必要がありました。京阪神エリアの一部線区においては、2024年5月より新たにシステム間の連携を強化する端末を導入することで、列車の停止手配の自動化や指令員から乗務員に対する指示業務が支援されるなど、より迅速な対応が行えるようになりました。

※運行管理システム:指令でリアルタイムに列車の位置情報を把握し、ダイヤに応じて信号の制御を行うシステム
※気象災害対応システム:雨・風・地震等の気象災害に関する情報の管理を一元的に行うシステム
※通告伝送システム:指令から乗務員へ列車運行に関する指示や情報を伝達する通信システム
市民防災講座の開催
防災や減災に関係する幅広い専門家の方々から講演を行っていただき、沿線の皆様等の防災意識の向上と、避難時の行動や住民同士の協力の重要性を理解していただくことを目的に、京都大学大学院工学研究科 社会基盤工学専攻 災害リスクマネジメント工学(JR西日本)講座による市民防災講座を開催しています。2024年度は「自然災害に備える」をテーマに、7月、9月、12月の計3回実施しました。