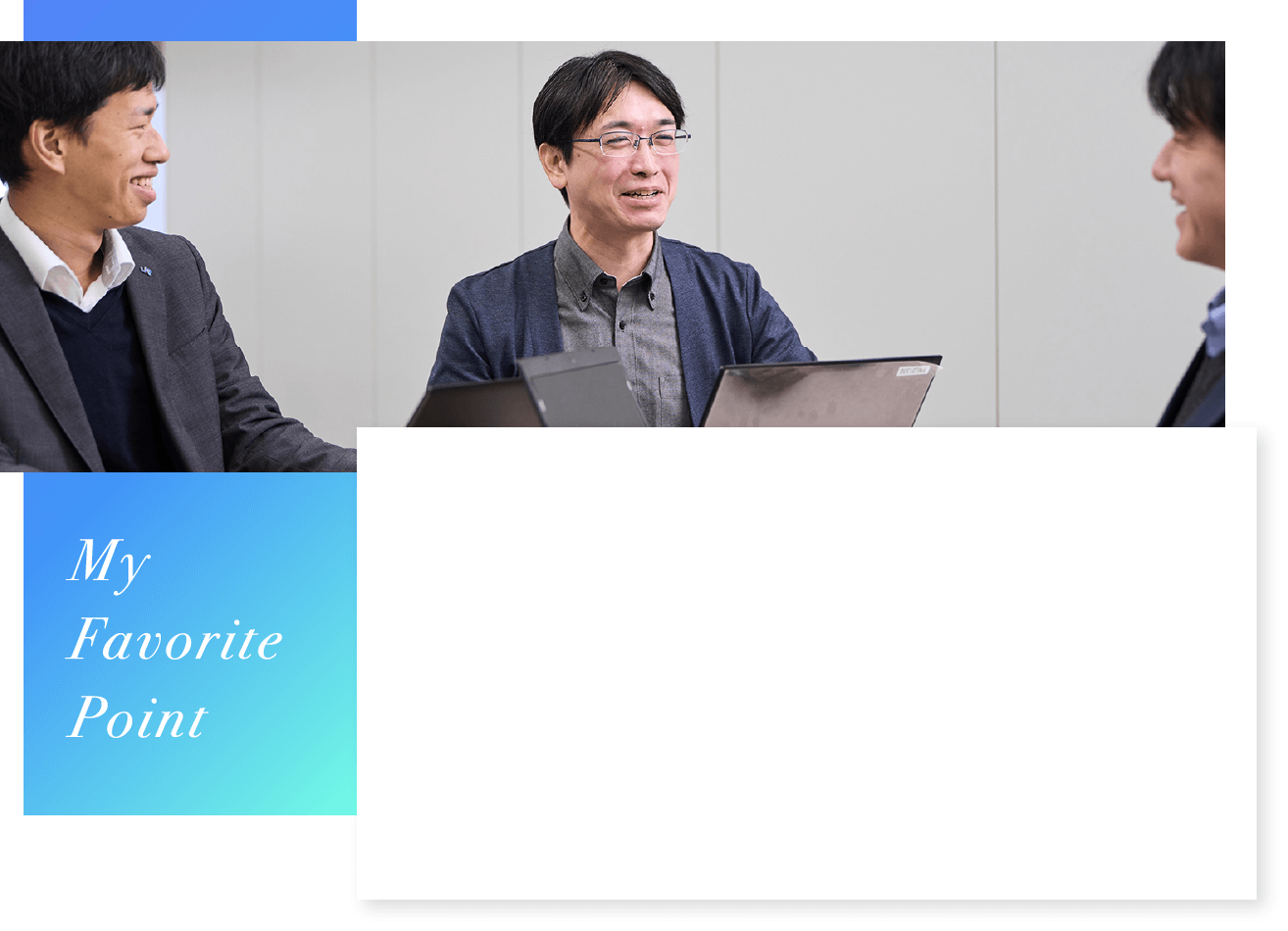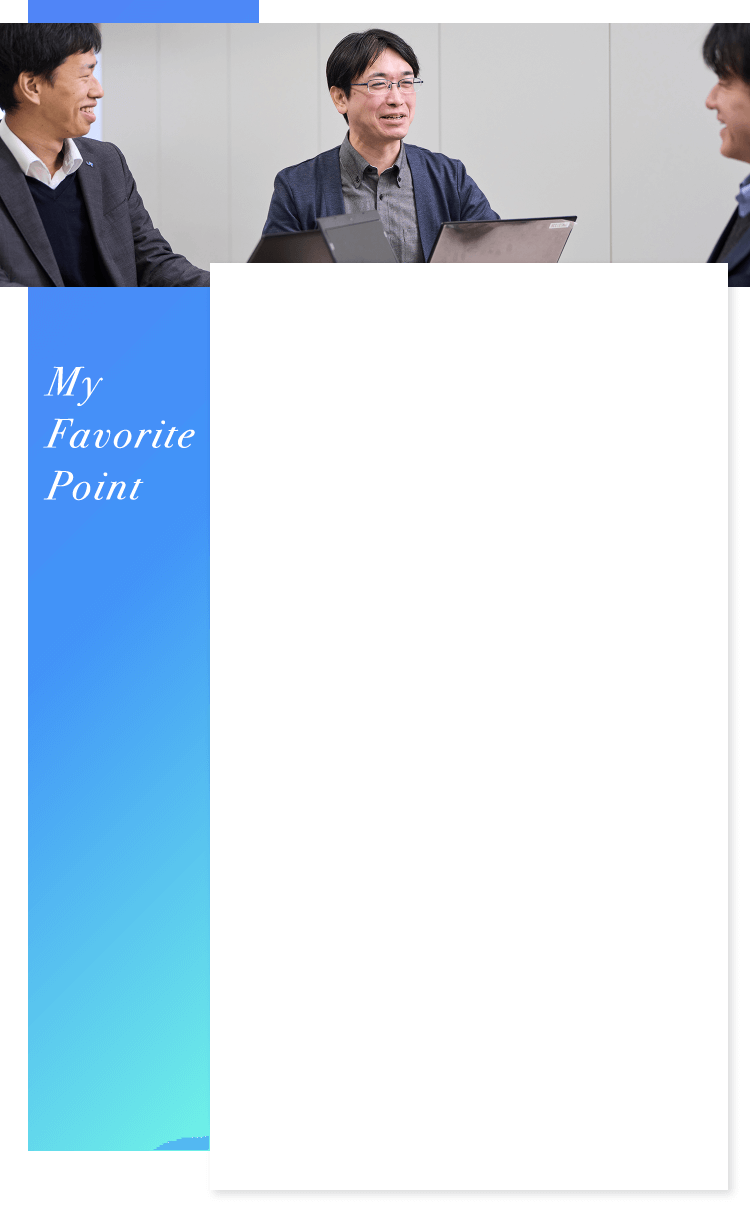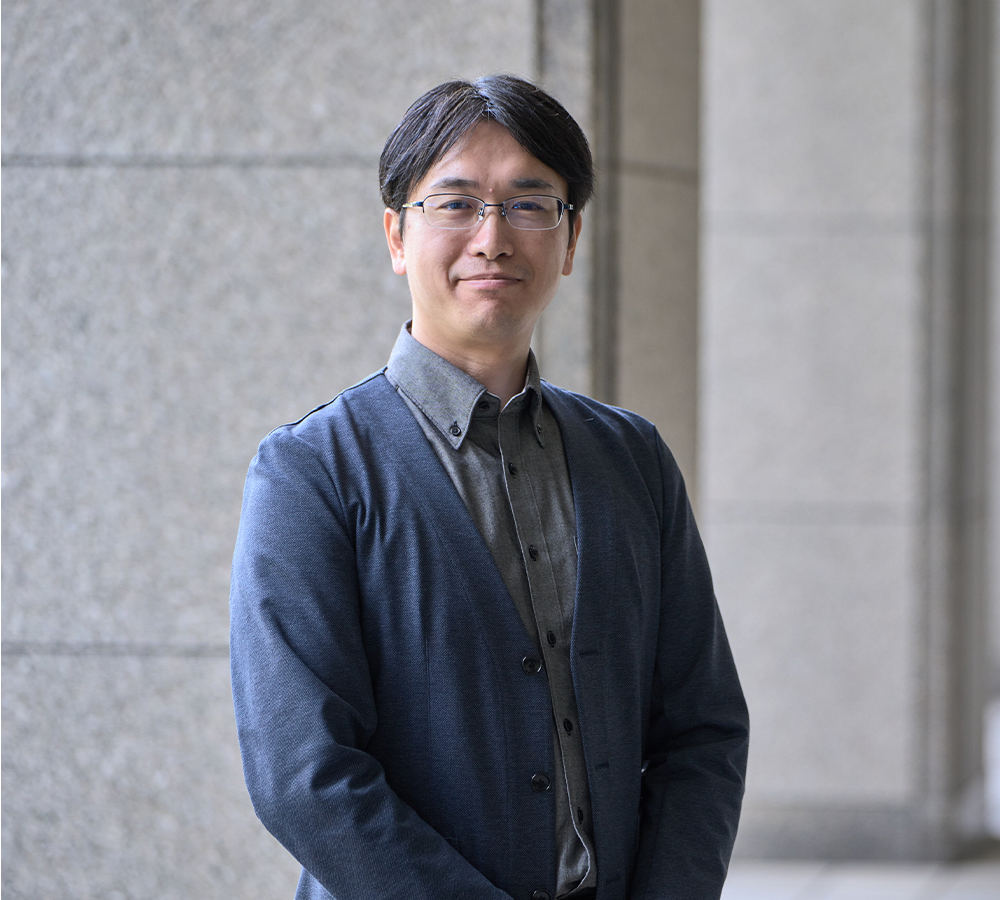
総合職採用
車両
鉄道本部 車両部 企画課 課長代理 D.Shirasaki 2009年 入社
Career Step
- 2009年神戸支社 網干総合車両所
- 2011年神戸支社 姫路列車区
- 2012年神戸支社 網干総合車両所
- 2012年鉄道本部 車両部 企画課
- 2013年鉄道本部 技術部 FGT推進PT
- 2018年鉄道本部 新幹線に係る新組織設置準備室
- 2018年鉄道本部 新幹線鉄道事業本部 新幹線安全推進部
- 2020年鉄道本部 車両部 企画課
- 2021年鉄道本部 車両部 企画課 課長代理
北陸新幹線敦賀延伸に向け、
世界初のFGT用パンタグラフの開発に挑む
技術部フリーゲージトレイン推進プロジェクト

2024年3月、北陸新幹線は金沢から敦賀まで延伸します。敦賀駅では新幹線から在来線への乗り換えも発生します。そこでお客様の利便性向上のために開発が始まったのが、線路の幅(軌間)が異なる新幹線と在来線を相互に乗り入れることができるフリーゲージトレイン(軌間可変電車:FGT)です。私は技術部の一員として、パンタグラフの開発を担当することになりました。
北陸FGT用のパンタグラフには、高速走行時に騒音を抑えることや耐寒耐雪という観点から、小型化が求められました。一方で直流による大電流集電を行う在来線区間では、架線の温度上昇を抑えるために、パンタグラフには大型化が求められます。このようなパンタグラフは、FGTの先進地であるヨーロッパでも前例がありません。相反する課題の両立、世界初の取り組み、そして国がけん引する大規模プロジェクトというプレッシャーもありましたが、技術者としては非常にやりがいのあるチャレンジでした。
パンタグラフの材質や大きさは騒音や架線へと影響を及ぼします。そのため、地上設備を担当する部門と協議を重ね、全体最適となる仕様を追求しました。実際の素材で実物大の試作品を作って実験を行うなど、技術者の探究心を刺激してくれる体験もたくさんできました。
開発の期間中に、北陸FGTのベースとなる九州新幹線西九州ルート用FGTで安全性が十分に確保できないことが判明したため、北陸FGTの開発も断念することになりました。非常に残念ではありましたが、開発過程で得た知見などは1冊の資料にまとめることができました。いつかFGTのような画期的な鉄道システムの開発プロジェクトが動き始めた時、私たちの経験が役立てばと願っています。

成長を支えたもの
節目節目で、支えになる言葉を上司からかけていただきました。FGTの開発時代は、会社や世の中からの期待と責任感で重圧は非常に大きかったです。そんななか、「とりあえずなんとかなる。最後までやってみなさい」という言葉のおかげで、ずいぶんと気持ちが楽になりました。新入社員時代には、「仕事では、常に自分の2~3段階上の役職の立場になって物事を考えなさい」と教えられました。その言葉は、会社全体の経営に密接に関わる仕事をする今の役割に大いに役立っています。

コロナ禍がもたらした厳しい経営状況を、
車両メンテナンスの最適化とダイヤ適正化で回復させる
鉄道本部 車両部 企画課

コロナ禍は鉄道のご利用者数を大きく減少させました。この苦しい状況の改善に向けて、車両部門に関するリソースを見直そうというのが、私が担当した役割です。車両の技術者でありつつ、財務や経営の視点を持ち、会社全体での最適解を見つけ出す仕事と言えます。
最初に着手したのは、車両部門のどこにコストがかかっているのかという現状分析です。車両の安全性が確保できることを大前提に、どのような対策ならば導入可能なのかを支社、現場やグループ会社と一緒に検討しました。車両部門では、新車両の投入と既存車両のメンテナンスが大きなコストの柱です。メンテナンスは省令などで内容が定められているため、簡単には変更できませんが、さまざまな検証を行いメンテナンスの最適化を行いました。また、既存車両と比べてメンテナンスの省力化が見込まれる新車両の投入を計画しました。
鉄道のご利用者数はコロナ禍以前の水準に戻ることはないと予想されています。そこで、ご利用状況に応じたダイヤの見直しも行いました。これらのプロセスでは運輸部門と連携し、どの路線をどれぐらいの便数にし、そこではどの車両を用いるのかといったシミュレーションを幾度も行い、最も合理的な答えを導き出していきました。
この仕事を通して、鉄道システムを維持していくためのお金の動きを詳しく理解することができました。投資効果や損益分岐といった、経営視点を身に付けることもできました。学生の時に取得した簿記の資格が今の仕事にとても役に立ちました。部門の垣根を越えて、「社会が抱える課題を解決する仕事がしたい」という今後の目標が定まったのも、この仕事がきっかけです。

実現したい未来
コロナ禍によって当社をめぐる社会環境が一変したなか、リソースの最適化を図ることの目的は、安全・安定的な鉄道サービスを持続的に提供することに他なりません。工夫を凝らして無駄なコストを抑制し、なおかつ安全や利便性をしっかりと守っていく私たちの仕事は、鉄道事業を未来へと継続していくことだと言えるのです。それは、「安全、安心で、人と地球にやさしい交通」「持続可能な社会」の実現に貢献するものだと考えています。