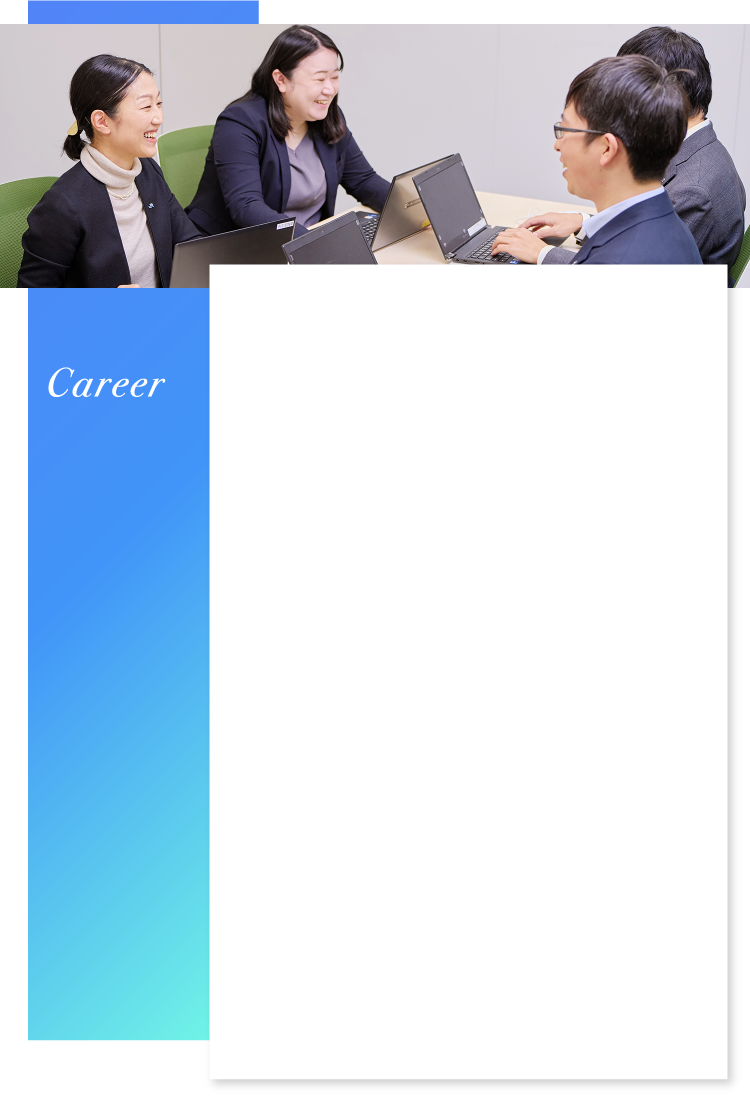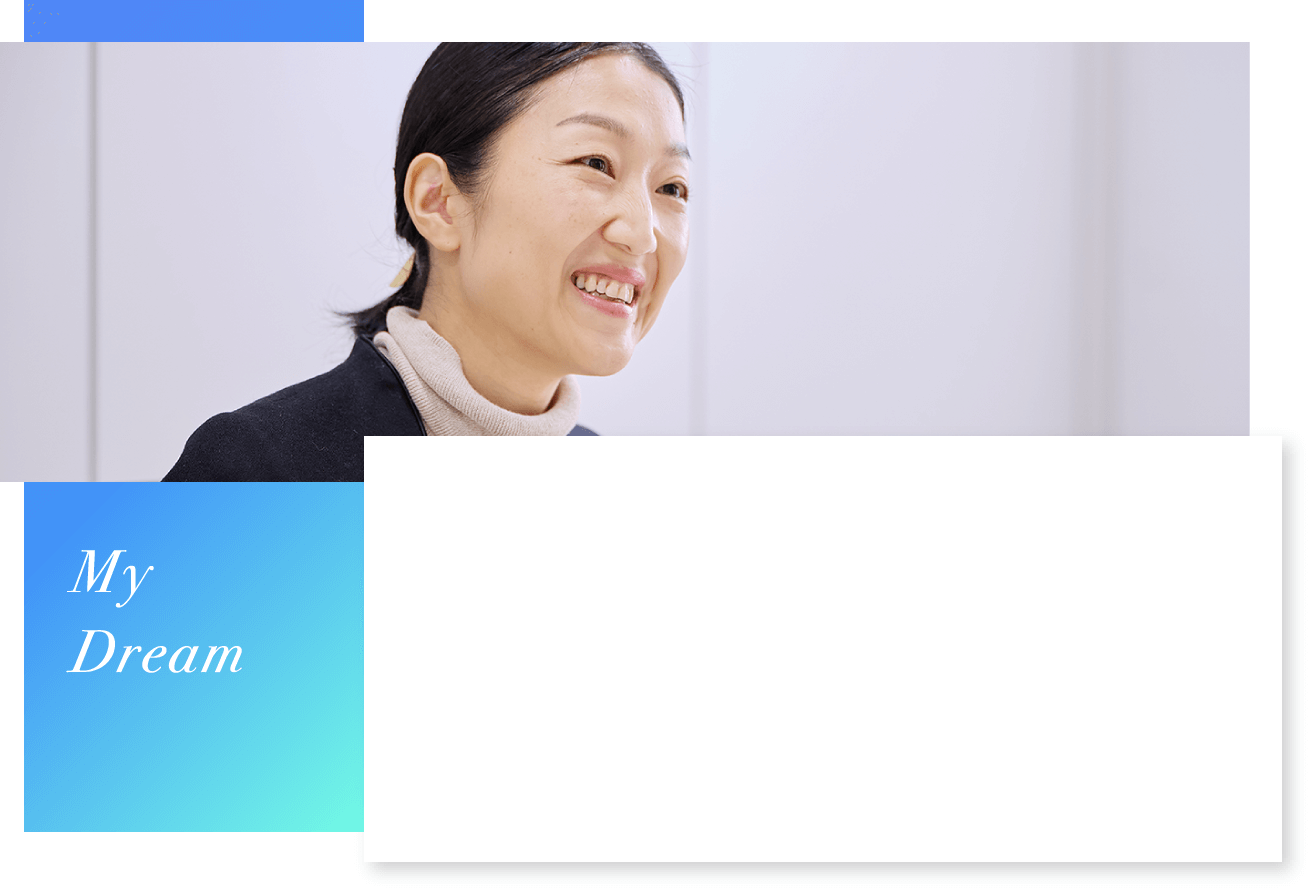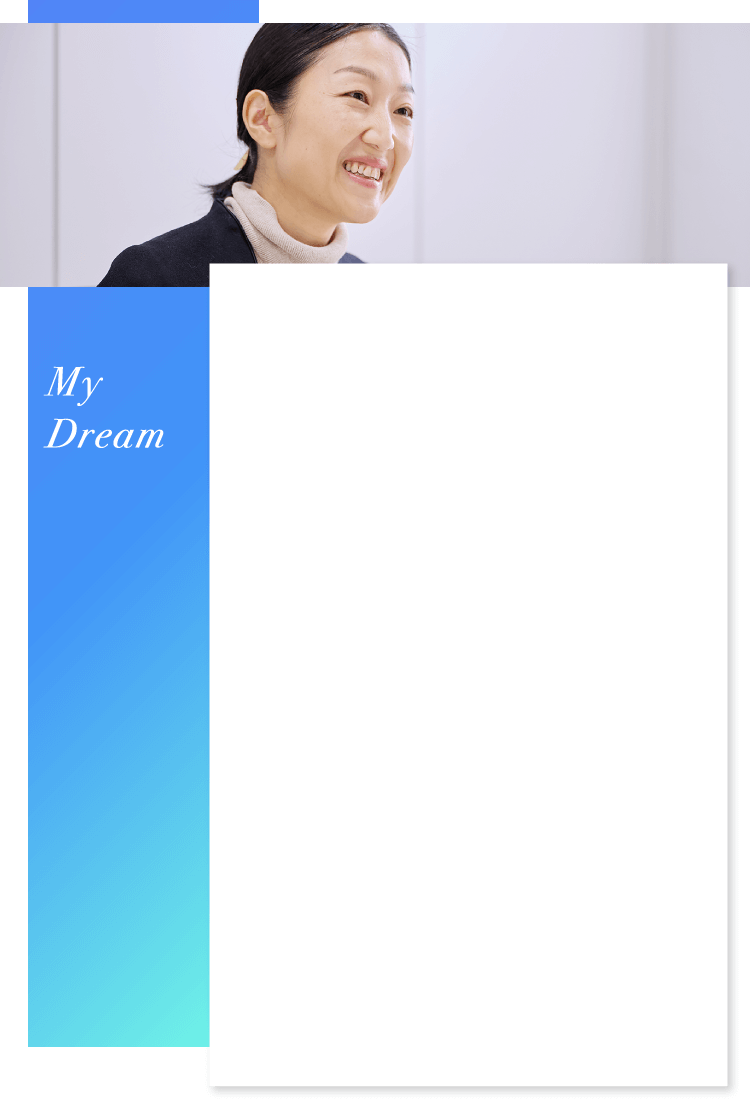高専卒採用
車両
イノベーション本部 鉄道DX部 担当課長 M.Yaoita 1999年 入社
Career Step
- 1999年京都支社 吹田工場(現 近畿統括本部 吹田総合車両所)
- 2004年神戸支社(現 近畿統括本部) 網干総合車両所
- 2007年車両部
- 2010年大阪支社 森ノ宮電車区(現 近畿統括本部 吹田総合車両所森ノ宮支所) 係長
- 2011年育児休職(第1子)
- 2014年(5月)大阪支社 森ノ宮電車区(現 近畿統括本部 吹田総合車両所森ノ宮支所)係長(復職)
- 2014年(11月)育児休職(第2子)
- 2016年近畿統括本部 吹田総合車両所 係長(復職)
- 2019年車両部
- 2021年車両部 課長代理
- 2024年イノベーション本部 鉄道DX部 担当課長
車両搭載装置の品質向上へ、
メーカーと一体になって取り組む
車両部企画のプロジェクト

1990年代から鉄道車両での導入が活発化した電子機器は、2000年頃からメンテナンスが必要な時期になりました。そこで立ち上がったのが、電子機器に関する不具合事象の現状把握や分析を行い、将来のメンテナンス方法を検討するプロジェクトです。本社車両部内の設計部門やメンテナンス部門、現業機関に加えて装置メーカーも参画する大きなプロジェクトだったのですが、入社後、現業機関に配属となり2年目の私は上司の勧めもあってメンバーに加わりました。
当時の私は、決められたメンテナンスメニューに従って実際のメンテナンスを行うという役割を担当していました。それに対してプロジェクトは、メンテナンス方法そのものを考えます。役割が異なるうえ、装置や他部門の仕事に関してなど、膨大な知識が必要でした。「とにかくメンバーと対等に話せるように」との思いで、がむしゃらに勉強した毎日でした。
鉄道車両は、鉄道事業者である私たちが仕様決定、基本設計を行い、それに基づいてメーカーが詳細設計、製造し、導入後は私たち自身がメンテナンスを行います。鉄道車両に一貫して関わることができるのが、鉄道会社で車両に携わる技術者として働くおもしろさだと知りました。さらに当社では、現場の要望や課題認識に真摯に耳を傾けてくれ、合理的であれば実現することができます。役職やキャリアに関係なく、良い提案は採用されます。実際、私の発案もその後の装置の基本設計に反映されています。JR西日本で働くことの魅力を実感したプロジェクトでした。

成長を支えたもの
年齢や経験など、その時々の私に応じたチャレンジングな仕事と出合えたことが成長につながったと思います。チャレンジングな仕事があるのは、業務の幅が広い当社だからこそだと言えます。また、そういった仕事に推薦してくれたりチャレンジを後押ししてくれたりする、上司をはじめとした周囲の環境があったからでもあります。「ポスト公募」のように、自分から手を挙げてチャレンジできる制度があるのも、当社のいいところです。

上司の言葉で迷いが吹っ切れ、
仕事と育児に前向きに取り組めるように
出産による休職と職場復帰、育児との両立

現業機関の係長になって2年目に、出産、育児にともなって育児休職を経験しました。その後、職場に復帰、第2子の出産と育児休職を経て、本格的に職場に復帰しました。
小さい子どもがいると、急な発熱などでどうしても仕事を休まないといけないことがあります。出産前は異常時対応などで土日に出勤することもあったのですが、それも難しくなりました。周囲の皆さんはとても協力的で、快く担当を替わってくれました。ただ、私の心の中には申し訳ない気持ちがありました。「係長としての役割を果たせていない。期待に応えられていない」という後ろめたさもありました。
そんななか、当時の上司である現場長から「すべての社員のあらゆるライフステージでも両立が可能となるようサポートすることが、人財の維持・確保として会社の利益になる」という言葉をかけてもらいました。この言葉のおかげで迷いが吹っ切れ、前向きな気持ちで仕事と育児の両立に向き合えるようになりました。自分を含めメンバーの仕事の進捗状況などをオープンにし、誰もがサポートし合える状態をめざすようになったのはこの言葉がきっかけです。
長い社会人生活のなかでは、さまざまなライフステージの変化を経験します。大切なのは、それぞれのライフステージに応じたベストを尽くし、できる限りの成果を出すことだと思います。上司の言葉のおかげで、そう考えることができるようになりました。私自身、さまざまなライフステージを経験する周囲の皆さんを、業務を通して最大限フォローしていきたいです。

実現したい未来
私たち車両部が携わる車両メンテナンスという仕事は、「安全、安心で、人と地球にやさしい交通」「持続可能な社会」の実現に直結しています。IoTやAIなどを用いた新しいメンテナンスの仕組みは、鉄道の安全性向上に大きく貢献してくれます。加えて、運行を支える社員の負担を軽減することにもつながります。プロジェクトメンバーとともに新たな技術やその活用方法を学び、より良いメンテナンスシステムをつくり上げたいです。

独自のメンテナンスシステム確立に向け、
プロジェクトの立ち上げから参画
車両メンテナンスのシステムチェンジ

車両のメンテナンスは、省令などによってその周期、検査項目が定められています。一方で、鉄道事業者が安全性を確保できることを証明した場合は独自のメンテナンスに見直すことが可能とも定められています。この省令などに基づき、当社独自のメンテナンスシステムを構築しようというプロジェクトが立ち上がりました。私は、当社が保有する車両に適したメンテナンスを企画し、必要な開発、ルールを整備することにおもしろさを感じ、プロジェクトに立候補、立ち上げから参画しました。
現在、導入を推し進める新たなメンテナンスには、新しい技術を積極的に取り入れています。例えば、車両搭載機器の動作状況や物性値などのビッグデータを地上システムに通信する装置を車両に搭載し、それと並行してビッグデータから車両、搭載機器の正常性を確認するためのシステムの開発を行っています。ちかく車両メンテナンスへ導入の予定となっています。
新たな技術に触れることができ、なおかつ今後の車両メンテナンスの在り方を変える仕組みをつくることができるという、非常にやりがいの大きな仕事です。
プロジェクトでは、「こうであればいいな」という構想を描く段階から、社内の各部署や現場の社員への聞き取りによる現状把握、関係省局などとの意見交換や調整を経て、構想を実現するまでの一連の流れに携わっています。関わる人の数が多いうえ、ルールや慣行など、新しい取り組みにあたっては壁となってしまう事柄も多いです。それらを一つずつ解決し、構想を実現していくことこそがこの仕事のおもしろさです。現業機関や本社の企画業務で身に付けてきた、技術力とマネジメント力が大いに役立っています。