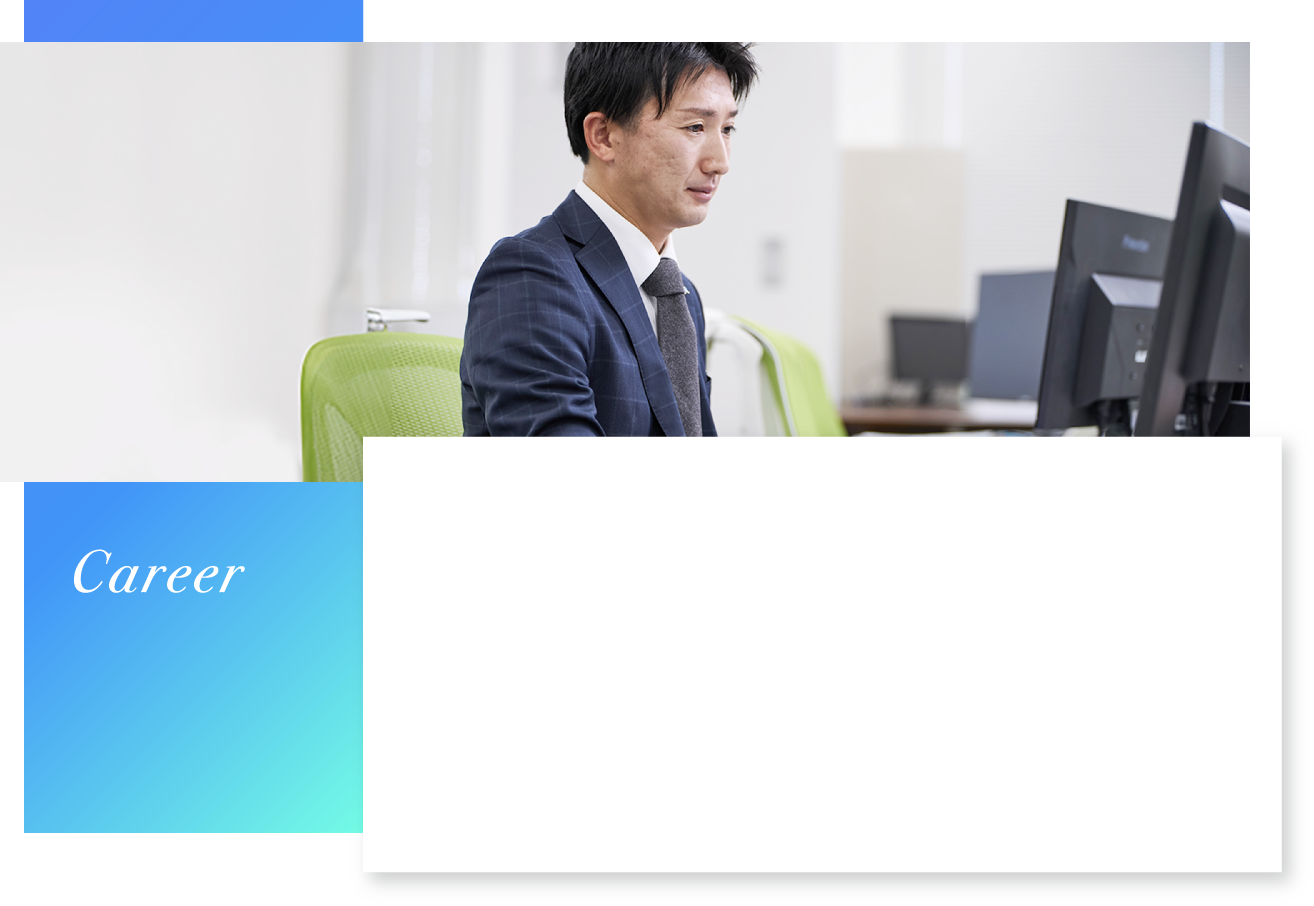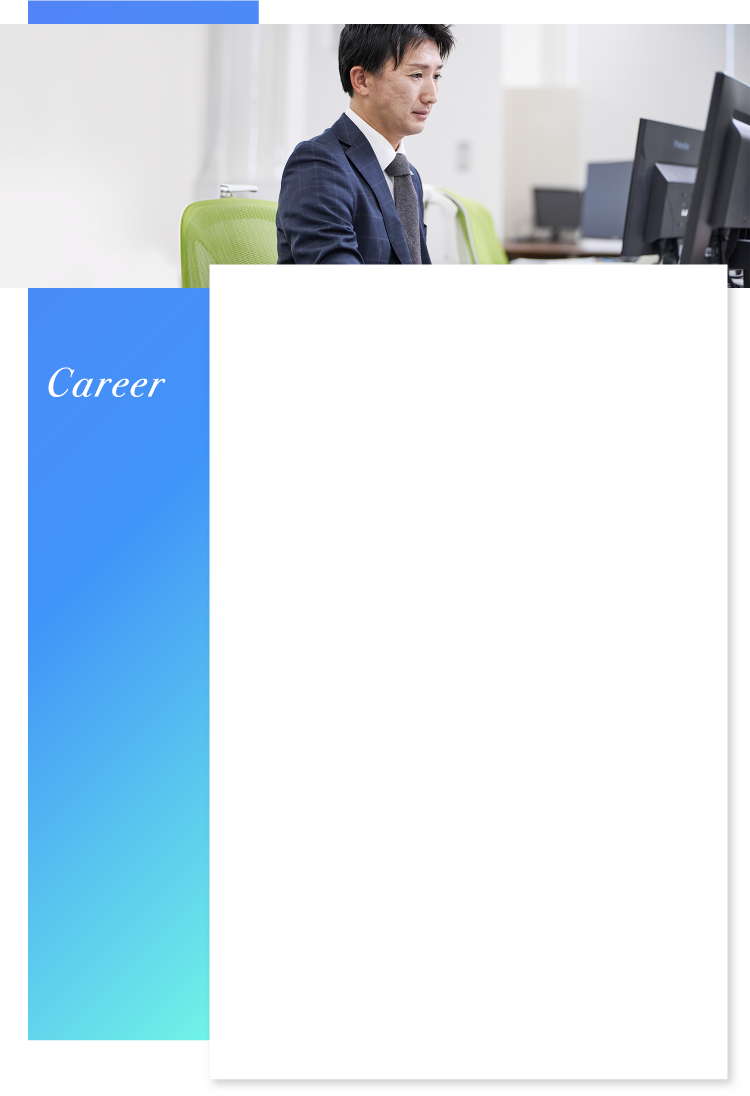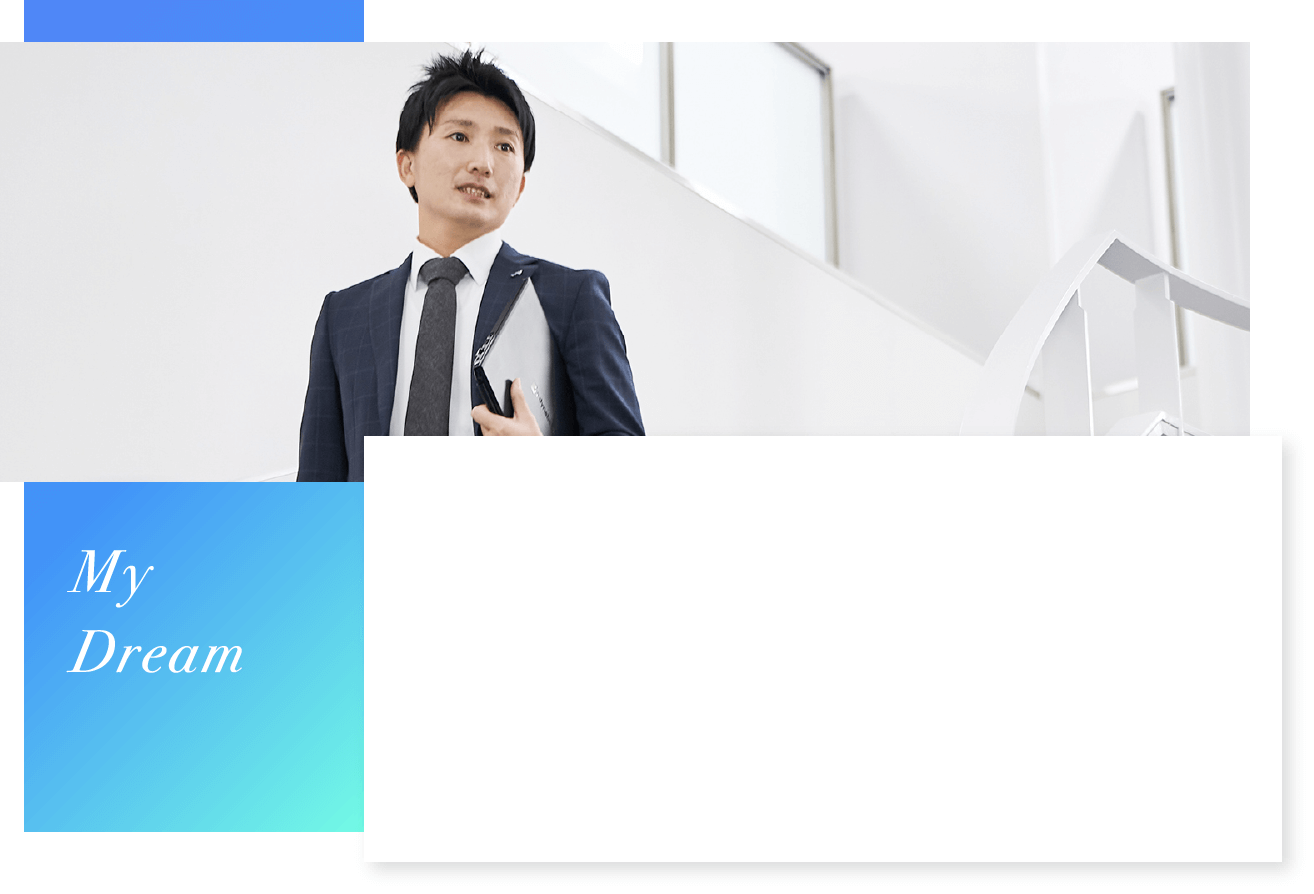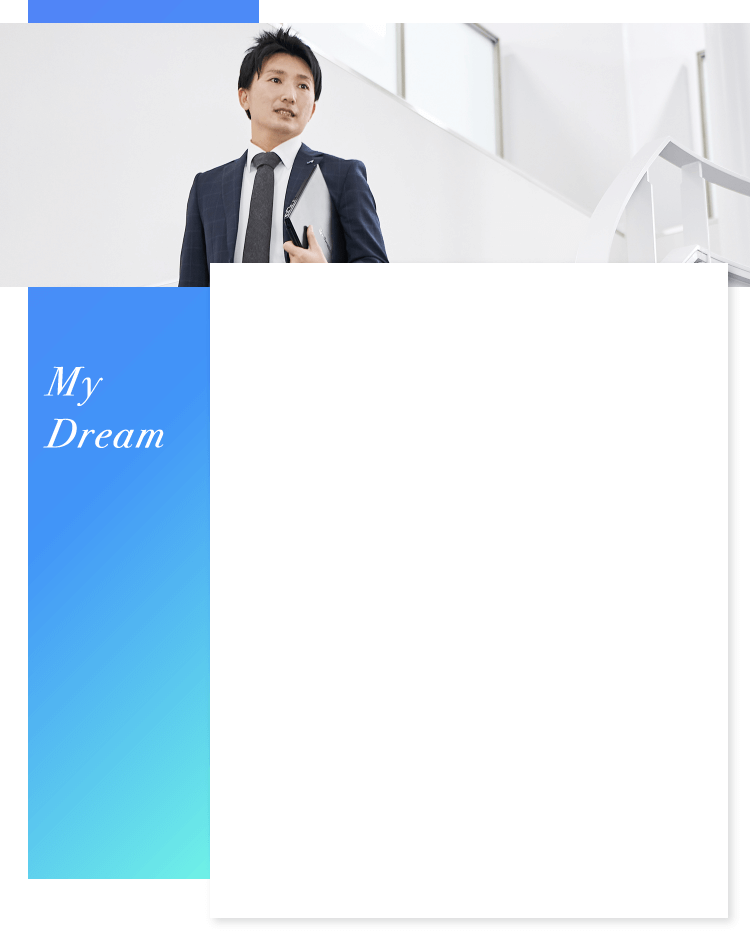高専卒採用
電気
近畿統括本部 電気部 安全チーム M.Yoshimura 2008年 入社
Career Step
- 2008年京都支社 湖西電気区 信号通信グループ
- 2009年京都支社 電気課 工事チーム(信号通信)
- 2010年京都支社 京都電気区 信号通信グループ
- 2012年近畿統括本部 大阪総合指令所 信号通信指令
- 2017年近畿統括本部 電気課 信号チーム
- 2018年鉄道本部電気部 企画課(安全・計画)
- 2021年和歌山支社 田辺電気区 信号通信グループ 係長
- 2023年近畿統括本部 電気部 安全チーム
貨物駅の整備プロジェクトで
信号機の統合作業に携わる
京都支社 京都電気区 信号通信グループ

入社以来、高専で学んだ電気関連の仕事に携わり、入社4年目に吹田信号場という貨物駅の設備を改善する「吹田基盤設備プロジェクト」に参加しました。私はこのプロジェクトで、駅内に複数あった列車の動きを制御する信号場をひとつに統合する作業に関して、「システムが設計通りにつくられているか」、「計画通りに機能しているか」を確認する役割を担いました。
駅の規模が大きく、工期も迫っている中でプロジェクトに加わったこともあり、当初は「この役割を果たせるのか」という不安がよぎったのが正直な気持ちです。また、業務は当社の社員だけでなく、JR貨物をはじめさまざまな会社や鉄道運輸機構の方々と連携して行う必要があり、戸惑うこともありました。当時は経験も知識もまだまだ乏しかったので、とにかく任された業務を正確に行うことに集中するとともに、できる限り効率的に進めるように努めました。
こうした状況で心強く感じたのが、チームをまとめていた先輩社員の存在です。リーダーシップを発揮して、メンバー全員が同じ方向を向いて取り組めるように引っ張ってくれたんです。チーム一丸となったことで工事は予定通りに完了し、JR貨物から感謝状をいただくというサプライズも。困難な目標に向かって取り組み、最後までやりきった経験は大きな自信になりました。

成長を支えたもの
まず、社員育成を重視している会社の姿勢が挙げられます。新入社員教育をはじめ、経験に応じてステップアップできる体制が整っていることは、成長するうえで大切な要素です。特に1年目のOJTでは段階的に目標設定されていることで、高いモチベーションを持って取り組むことができました。そして、大きな支えとなったのは、なんといっても先輩や上司のサポートです。若手時代の上司は、勉強会や自己学習の発表会などスキルアップの機会をつくってくれて、多くの知識やアプローチの方法を学ぶことができました。

管理システム導入プロジェクトを
ゼロから立ち上げる
近畿統括本部 大阪総合指令所 信号通信指令

電気機器や通信設備の保守を行う指令員として業務にあたった中で、特に印象に残っているのが、作業統制自動応答システムの導入です。当時、電気関連の工事に関して、「どこの現場で、どんな作業をしているのか」といった管理はアナログ作業で行われていて、多大な労力を要していました。そこで、業務効率化と管理の精度向上を目的に、ITを活用したシステム導入の計画を立ち上げたのです。ゼロの状態から開始したため、まずは予算の確保から始め、計画の有効性を理解してもらうために導入後の効果検証を行いました。しかし、効果を“見える化”するのは想像以上に難しい作業でした。また、私はITやシステムについて特に詳しいわけではなかったので、基礎から学習することに。こうした業務は、これまで経験してきた現場での仕事とは内容も役割も異なっていたためトライ&エラーの繰り返しでしたが、システムを導入すれば多くの社員の役に立つという想いがあったので、やりがいはありました。
もうひとつ成長につながった経験として挙げられるのが、踏切の長時間鳴動の解消です。駅の近くにある踏切は列車が駅のホームに停車している時でも動作するようにしており、事故などで列車が長時間駅に停車することになると、踏切が動作し続けることになります。安全を守るためには必要なことですが、一方で近隣にお住まいの方々への影響もありました。とはいえ、それは“仕方のないこと”として、特に問題視されていませんでした。ところが、当時の上司が事故などで長時間列車が停車することが見込まれる場合には近くに踏切のない駅に列車を停車させることで、安全性を確保しながら踏切の作動時間を短縮できるのではないかと考え、ルール化に向けて取り組んだんです。“当たり前”とされていることを“当たり前”としてそのままにしておくのではなく、問題意識を持って物事を捉える上司の姿勢に感銘を受け、自分自身も意識するようになりました。
また、プライベートではこの年に一人目の子どもが生まれ、新たなライフステージに。私自身、育休は取りませんでしたが、妻とともに初めての育児に取り組みました。日中は妻が子どもをみていてくれていたので、夜は私がみるようにしていました。家事は主に部屋やキッチン、浴室の掃除、洗濯などを担当しました。初めての育児で大変なこともありましたが、かけがえのない時間を過ごすことができました。

実現したい未来
「すべての人に安全で安心してご利用いただける鉄道サービス」を実現すること、私がこれまで携わってきた仕事は、すべてここにつながっていると感じています。“安全・安心”は、私たちの事業の根幹となるものです。広い視野と柔軟な姿勢を持って安全性向上に取り組み、これまで以上に社員や関係者、そして多くの利用者の方々から信頼していただける環境をつくりたいと考えています。

これまでの経験を活かし
電気関連の安全性向上に取り組む
鉄道本部電気部 企画課(安全・計画)
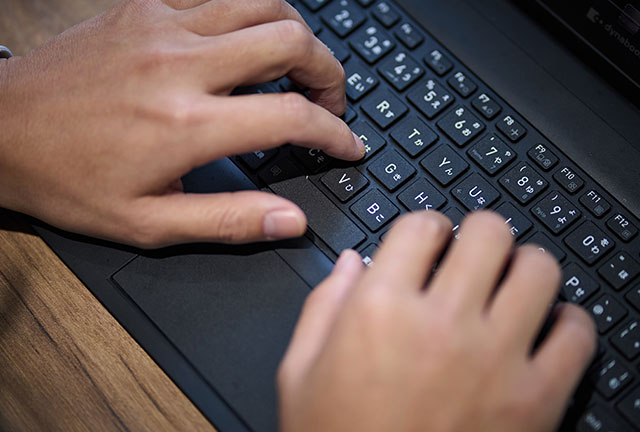
電気関連の安全担当者の業務内容は、安全性の向上に向けた施策の立案から実行、取り組みの評価まで多岐にわたります。それは新しいルールやシステムの導入に限らず、周知のためのツール制作まで及びます。また、取り組みの評価は、効果が出たプラス面だけでなく、他の領域で新たな問題が発生していないかといった面も慎重に見極めなければなりません。こうした業務を適切に行うためには、JR西日本の電気系統の全体像を把握することが不可欠であり、その点においてはそれまでのキャリアと経験が役立ったと実感しました。
これは今でもいえることですが、日々の業務で心がけていたのは、踏切の長時間鳴動の解消で学んだ、“当たり前”とされていることを“当たり前”として見過ごさない姿勢。そのためにアンケートなどを実施し、現場の声を吸い上げて精査することで、当事者自身も意識していない課題を明確化して、改善につなげるように努めました。 私のキャリアを振り返ると、基本的には電気関連一筋といえるでしょう。しかし、数多くの経験を重ねて知見を広げられていると感じています。今後もこれまで身につけたスキルを活かしながら、さらに磨きをかけて多くの人の安全に貢献したいと考えています。
また、2019年には二人目の子どもが誕生。この頃、上の子どもが保育園に通いはじめ、私が保育園まで送る係を担当。当社ではフレックス制度が採用されているので、余裕をもって準備できました。急な発熱など予定外の出来事に対応しやすい点もメリットです。さらに今は在宅勤務も導入されて、とても助かっています。
現在、当社では男性社員の育休取得を推進していて、みんな積極的に利用するようになりました。制度があるだけでなく、部署のメンバーも「みんなでサポートし合おう」という意識をもっています。男女にかかわらず、仕事と育児を両立できる環境が整っていることは、充実した人生を送るうえで重要な要素だと感じます。