

JR西日本採用サイト
総合職採用
施設(土木)
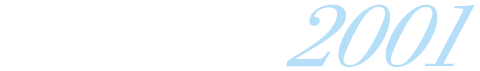
福岡支社 福岡工務所 博多基地保線駐在 工務管理係

入社から3年間、新幹線の博多基地で線路の形状変化を見つけて修繕を行うという業務に携わりました。基地内の線路は総延長約32km。当初は、10mの糸を張って1mごとに手作業で線路のゆがみを計測して不具合の有無を調べるという、気の遠くなるような作業を行っていました。「人海戦術ではきりがない」と感じた私は、同年代の先輩方と新たな方法を検討しました。そこで注目したのが、トラックマスターという簡易的に線路形状を計測してデータ化できる機器です。これを使うことで、「どこに、どの程度の形状変化があるか」を定量化して把握することができます。すると、「どの線路を優先してメンテナンスすべきか」も見えてきます。おかげで、基地内の線路を効率的に健全化することが可能になりました。この取り組みは本社にも伝わり、各地の支社にも展開。いまでは全社的に定着した仕事の進め方になっています。この経験から、設備も人の活動も、リソースを有効に投入していくには定量化・構造化することが大切だと学びました。また、「誰が言っているのかではなく、何を言っているかが大切だ」、すなわち権威や経験に頼る指示や行動ではなく、問題意識とデータに基づく意思決定・行動が大切だと学びました。これらは今に続く私の思考・行動様式になっています。
入社以来ずっと、人に恵まれてきました。上司は厳しくも熱意をもって指導してくれる方々ばかりでした。先輩方は問題意識を共有し、解決に向けて引っ張っていってくれました。後輩も優秀な人たちばかりで、さまざまな刺激を与えてくれます。また、2013年に英国サウサンプトン大学院に留学、当地のグローバルの建設コンサルティング会社でインターンをしたことも大きな財産になっています。ここでは、海外の鉄道ではどのように保守が行われているかを学びました。海外の鉄道事業者とのつながりもでき、貴重な情報やアドバイスを得られるようになりました。

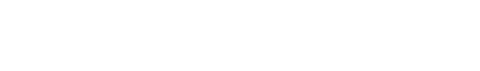
鉄道本部 施設部 企画課 主査

鉄道サービスは、車両や施設、電気など、数多くの部門による日々の丁寧なメンテナンスによって維持されています。社会の少子高齢化は、この分野にも影響を与えています。社外の協力会社も含めて、メンテナンスを担う人材が高齢化。技術やノウハウを継承する若手が減りつつあるのです。また、しっかりと休暇を取得できる職場環境や残業・夜勤の抑制など、働き方改革の推進も重要な課題です。将来にわたって安定して高品質な鉄道サービスを提供するためには、これらの課題を解決することが不可欠です。そこで、当社から外注先である協力会社までに至る、設備保守業務のサプライチェーンを維持・高品質化するための工事制度の変革に取り組むことになりました。少ない人手で高品質な保守を行うというのは、両立の難しいテーマでもあります。そこで、これまでのキャリアを通じて培われたファクト及び現地現物主義に基づいて意思決定することにこだわり、グループ会社・協力会社に足繫く通いました。制度変更した場合の現場の負荷を、ヒアリングを通じて定量化。そのインパクトをシミュレーションし、サプライチェーンの質の維持・向上のための経営改善施策を立案・導入しました。この制度変更は、当社内だけでなく鉄道の保守に関する業界全体に影響を及ぼすものです。難しい仕事ではありましたが、関係者の理解を得て協力の輪を広げていくという、大きなプロジェクトを動かすための力を養うことができました。
マーケティング領域におけるデータ活用を支えるツールが、当社の移動生活ナビアプリ「WESTER」です。WESTERを使って移動されたお客さまのデータが私たちのもとに集まり、その分析結果が新たなキャンペーンの立案などに活かされています。WESTERが利用されることは、地域の魅力発信や活性化につながっていると言えるのです。これからも、デジタルを活用して地域の課題解決などに貢献していきたいです。

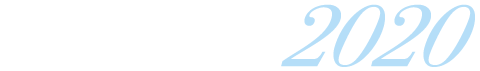
デジタルソリューション本部 データアナリティクス 課長

現在取り組むひとつの大きな分野は、鉄道車両や地上設備のメンテナンスにAIやIoTを活用することで、生産性を向上させるプロジェクトです。また、その過程で得られるデータ収集・分析のノウハウを活かし、効果的なマーケティングを実現することも大きなプロジェクトの目的のひとつです。鉄道会社には、データ化には至っていないものの膨大なノウハウや技術が蓄積されています。それらを数値に置き換え、AIと戦略的なアナリティクスとを組み合わせることで、さまざまなイノベーションが起こせると感じています。プロジェクト黎明期に取り組み、いまでは実用化どころか他社へ販売して収益源となりつつある自動改札機の故障予測モデルは、その代表例です。そういったイノベーションを起こすために、プロジェクトのリーダーとして私は、「誰が言ったのかではなく、何を言ったのか」にこだわり続けています。データという事実から見えてくる情報と、そこから浮かび上がる問題意識が大切なのです。メンバーに対していつも「あなたはどう思う?」とたずねているのも、そのためです。今、当社はデータ活用の黎明期です。着雪予測システムを開発した志の高いメンバー達が社内のまったく違う部署から異動してきたように、能力と意欲がある人にはどんどん加わってもらいたいと考えています。4人でスタートしたチームは今や20人規模になり、社長直轄の部署になっています。保守業務に加えてマーケティング領域でもデータ活用を進め、より良い経営に貢献することが今の目標です。
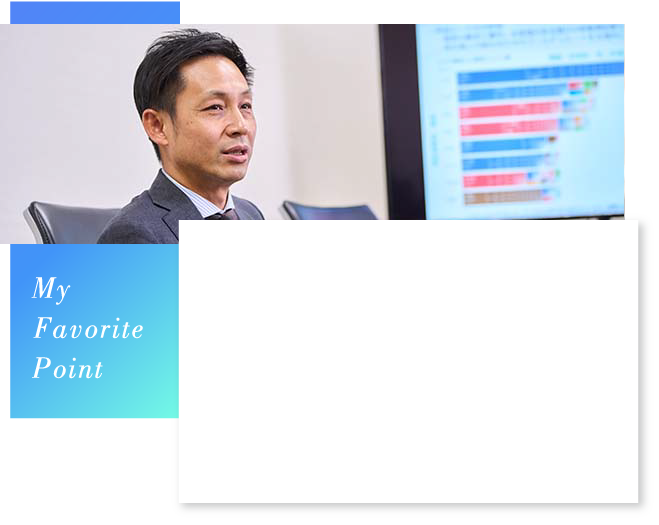
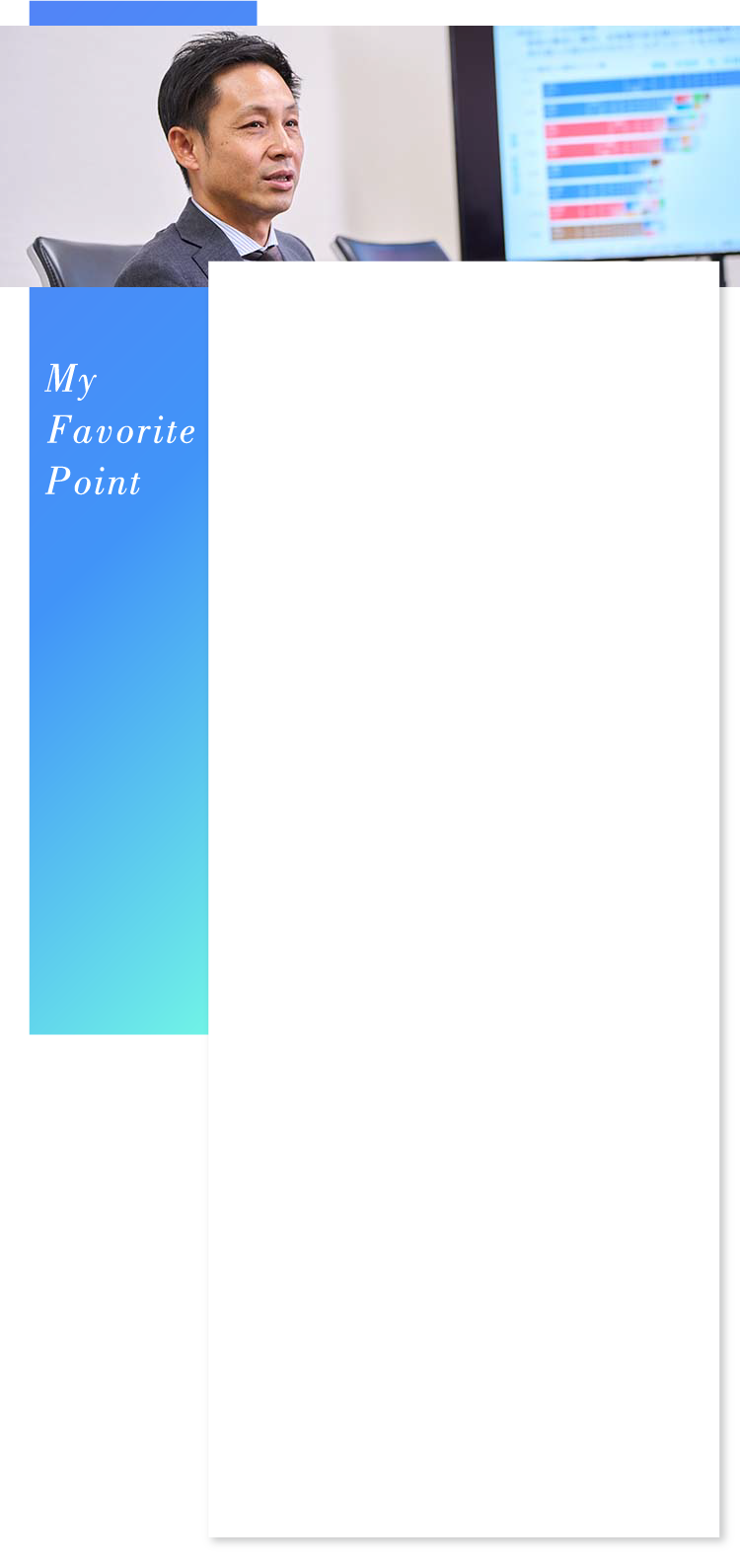
データ活用に取り組む立場としては、JR西日本は魅力にあふれた会社です。その理由はまず、長い歴史で蓄積した業務のノウハウや技術があることです。ここにデータが加われば、爆発的な進化を引き起こせると考えています。また、西日本地域はさまざまな課題が、首都圏に先行して顕在化しています。これは、データを用いたイノベーションで、西日本地域に所在する企業として課題解決の先例を示し、リードできる可能性を秘めているという意味にもなります。そして何よりも、社内で企画から実装まですべてを行ってしまえることが大きな魅力です。ITソリューション提供専業企業の場合、システムを「作る」ことはできても、「使う」場所は社外に求めざるを得ません。当社であれば、その両方が可能となるのです。
