

JR西日本採用サイト
プロフェッショナル職採用
電気
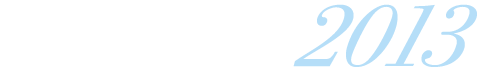
福知山支社 福知山電気区

入社して約半年間、電気設備の基礎となる研修を受けました。高校では電気分野を専門に学んだつもりでしたが、鉄道に関する実務では技術の幅が広く、研修期間中に学んだ知識が一つひとつ新鮮に感じました。現場に配属後、電気設備の維持管理に必要な点検や点検結果のデータ入力などの業務に就きました。ひとくちに電気設備といっても、転てつ機や信号機などの信号設備をはじめ、電車線設備、電灯・電力設備、情報・通信システムなど多岐にわたります。それぞれの設備の仕組みや操作方法、点検の手順などを日々興味深く学ぶことができました。また、電気管理係の業務に携わることで、列車の安全安定輸送に欠かせない設備の提供そのものが、お客様を目的地まで安全安心にお送りする重要な役割を担っているということを実感いたしました。その使命を特に感じたのは入社2年目のことです。まだ現場経験が少ないなか、担当する福知山の一部で集中豪雨による災害が発生。電気設備に故障が多発し、約1週間の運休という事態となりました。信号設備では多数の転てつ機や器具箱が浸水したほか、多くの機器が故障したのです。被災確認の指示を受けて出動し、やっとの思いで現地に到着すると、あまりに多くの機器が故障していることが判明し、復旧に要する時間がすぐに判断できず不安ばかりが募りました。しかし、先輩や上司、そして施工会社の方々が協力し合って設備を一つひとつ直し、鉄道を復旧させていく姿を目の当たりにして、安堵とともに尊敬の念を抱きました。そして、列車の運行が再開した際、踏切の現場に立ち会うことで問題なく動作したことがこの目で確認でき、あらためて、この仕事のやりがいと使命感を得ることができたのです。
入社当初の研修から始まって、電気設備の点検と検査データの入力作業、工事内容の検査、電気設備の管理、新設機器の導入にともなう工事の設計というように、数年の間でさまざまな業務を経験してきました。時には判断に迷ったり、悩んだりということがありましたが、その都度、上司や先輩の方々から助言をいただき、学ぶ機会に恵まれました。初めは難しいと感じた仕事でも、学ぶ姿勢を大切にすることで、知識と経験を得て困難を克服してきたことに自らの成長とやりがいを実感しています。これからも仕事を通じての学びを重ねていくことで、電気設備の技術者の道を着実に歩んでいきたいと思います。

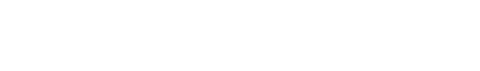
福知山支社 電気課

入社して約6年間にわたり、電気管理係の業務を経験し、設備障害の際、自ら積極的に動くことの大切さを学びました。積極的に動くためにはその裏付けとなる知識と経験が必要なのは言うまでもなく、設備の点検や点検結果のデータ管理などの仕事はかけがえのない学びの場となりました。こうした経験を踏まえて、2019年からは新設機器の設置にともなう設計や施工検査の業務を担当しています。仕事のなかでは、施工会社の方々に的確な指示を出していかなければなりません。そのため、事前の打ち合わせを綿密に行うとともに、複雑な手続きを確実に進めて安全な作業体制を築くことに努めています。また、工事の実施日にはあらかじめ詳細なスケジュールを作成し、それをもとに進捗状況を確認しながら監督業務を行っています。電気設備の多くは、数十年という長い年月にわたって運用されます。そのため、設備の大規模更新は電気技術者にとって大きな取り組みであり、貴重な経験を得る機会となります。私の場合、入社5年目に山陰本線にて自動進路制御装置の更新工事を経験しました。これは遠隔操作で転てつ機や信号機を操作するという鉄道の安全運行に不可欠な装置です。工事に際しては、試験責任者として複数回にわたって試験やシミュレーションを実施して慎重を期しました。工事の完了後、運輸指令室にて初列車が正常に運行したことを確認してほっとしたとともに、上司や同僚、施工会社や設備メーカーなどの方々と喜びを分かち合いました。
電気管理の業務は、デスクワークや施設内での業務が多い一方、検査や工事の立ち会いで現場に出ることも少なくありません。こうした機会に、地域の方々とふれあうことがあります。夏場に踏切の検査を行った際、地元の方が通りかかり、「暑い中ごくろうさま」と声をかけられ、うれしくなりました。そして、踏切を利用される方々の安全安心のために、点検をより慎重に行う必要があると実感しました。また、地域活動の一環として、沿線の幼稚園や保育所にて交通安全教育のボランテイア活動に毎年参加しています。園児の皆様に分かりやすいように、あらかじめ小道具を作成し、電車の乗り方や踏切の渡り方など伝えています。目を輝かせて私の説明を聞いている小さなお客様を前にすると、鉄道の安全安心を守るために一層がんばらなければと思いを新たにするのです。
