

JR西日本採用サイト
プロフェッショナル職採用
電気
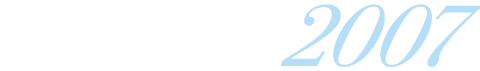
米子支社 米子電気区

入社して以降、米子電気区の電気管理係として、駅や沿線における架線・電気設備の検査などの業務に取り組んできました。電車はパンタグラフを通じて、トロリ線という電線から給電しているわけですが、列車走行時に線とパンタグラフが擦れ合い、摩耗されるので、パンタグラフの部品を一定期間で交換するのはもちろん、トロリ線も一定の細さまで削れると交換する必要があります。またトロリ線の上には吊架線があり、吊架線からトロリ線を吊っている金具(=ハンガーイヤー)に不具合がないかもチェックしなければなりません。これらの作業を軌陸車(きりくしゃ)という線路の上を走る自動車や架線に直接ハシゴを掛けて行うのをはじめ、信号機や踏切、駅舎への電気を送る配電設備、それら電気の供給源である変電所の検査、修理を手がけるのが主な業務となります。作業責任者に任命されたのは、入社4年目のこと。これまではベテランの技術者や作業責任者の指導の元、鉄道電気の知識・技術を学び、困った時はサポートいただいていましたが、今度は自分が皆を引っ張っていかなくてはなりません。若手作業員が中心のチーム、夜間という限られた時間の中での作業ということで、当初は不安もありましたが、無事に作業をやり終えた時の達成感、充実感は大きかったです。1日の作業が終わり、初列車のパンタグラフが自分たちの作業した架線を擦りながら走行する姿を見て、「お客様が乗られる列車の安全を守っている」ことを実感。それと同時に、そんな日々の繰り返しが技術者としての自信を深めてくれました。

入社したばかりの頃、右も左も分からなかった私を鍛えてくださった先輩方の存在を抜きにして今の私はありません。同じJRの先輩方だけでなく共に働くグループ会社の方にも鉄道電気の知識・技術はもちろん、作業時の目配り、気配り、緊急時の対処法など、教わったことのすべてが今の私の仕事につながっています。社員研修センターの講師となり、次世代の人財育成という観点から、「先輩たちのように、今度は自分が後輩を引っ張っていかないといけない」という想いも、日々強くなっています。

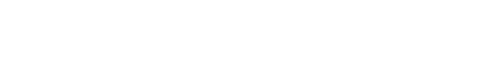
電気部

2019年6月より、大阪府吹田市にある社員研修センターで講師を務めています。指導するうえで私が心がけたのが、研修生たちと同じ目線に立ち、どんなことでもできるだけ一緒にやるという姿勢です。例えば、実習で使った道具を片付ける際にも「やっておくように」と指示するのではなく、「一緒にやろう」と輪の中に入っていく。そうすることで話しかけやすい雰囲気を作り、少しずつ関係性を築いていきました。結果として楽しいクラスになったと自負していますが、楽しいだけではなく、メリハリをつけ、やる時は徹底してやるという意識づけにも努めました。新人研修の期間は3カ月間。決して長い期間ではありませんが、そのわずかな期間でも技術的なことはもちろん、クラスの皆の人間的な成長を実感できたことが講師としてのやりがいに。私の地元の米子支社から来た研修生が「早く戻ってきてください。一緒に仕事をしましょう」と言ってくれたり、研修修了後しばらくしてから「ご飯行きましょう」と連絡をしてくれる子がいたり、そうした反応をもらった時はやっぱりうれしかったですね。私自身、先輩方から教わったことが今の自分の礎となっているので、今後も培ってきた知見を後輩たちにしっかりと伝えていければと思います。そしていつの日か、教え子たちと同じ現場で仕事ができるのを楽しみにしています。
米子電気区時代は、架線の保守管理だけではなく、駅構内の電球やコンセントの不具合などを直すことも間々ありました。その際に、近くにいる地域の方々から「直ってよかった」「ありがとう」と声をかけていただけるのがうれしかったです。また、沿線への倒木、倒竹の撤去などの仕事も行いますが、「うちの敷地内の木が線路に出ているから、こっちも伐っておいて」と直接ご依頼を受けたことも。快く引き受け、作業終了後にお茶を一杯いただくこともあり、日常的に地域の方と交流できていたことが私自身の仕事のやりがいにもなっていました。
