2008年度 省資源への取り組み
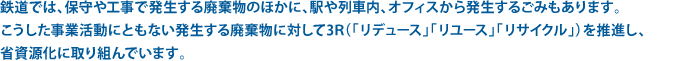
リデュース(使用資源の削減及び廃棄物の発生抑制)
ロングレール化・PCまくらぎ化
鉄道の安全を支えるレールやまくらぎは、安心して長く使用できる材料でなければなりません。レールについては、継目をなくしたロングレール化を進めることにより、レールの長寿命化と継目材料の削減を図っています。なお、ロングレール化は列車走行抵抗や騒音・振動の低減にも効果があります。
また、まくらぎは、昔から木材のものが多く使われてきましたが、木より長寿命なコンクリートなどの材質のまくらぎに取り替えることにより、廃棄物の発生の抑制を図っています。このことは原料となる木の伐採を削減し、森林保護にも貢献できます。

分岐PCまくらぎ
PCまくらぎとは、「プレストレスト・コンクリート・まくらぎ」のことで、コンクリート内に、鉄筋のほか、PC鋼線を挿入し、コンクリートが圧縮する方向に張力をかけているものです。これにより、ひび割れなどが防げ、まくらぎの強度も増します。
照明・信号機のLED化
機器の光源を蛍光灯や電球からLEDに替えることで、 省エネルギーだけでなく、長寿命化による廃棄物の発生を抑制することができます。照明や信号機などのLED化を進め、 廃蛍光管や廃電球の発生抑制に努めています。

ホーム下LED照明
IC乗車券「ICOCA」の導入によるきっぷ等の削減
IC乗車券「ICOCA」は繰り返し使用することができるために、利便性の向上だけでなく、従来の磁気きっぷや磁気定期券の発行枚数削減にも効果があります。
これまで平成15年に京阪神エリアに「ICOCA」を導入し、その後も、「Suica」との相互利用(平成16年)、「PiTaPa」との相互利用(平成18年)などにより利便性を向上させ、カードの利用を増やしています。平成19年には岡山・広島エリアにも「ICOCA」を導入し、これにより同エリアの近距離きっぷ(磁気きっぷ)の発売枚数が減少してきています。
今後も、利便性を高め、IC乗車券の利用率を向上させることにより、近距離きっぷや磁気定期券の発行枚数削減を図っていきます。

ICOCA
リユース(再利用)
新幹線から在来線へのバラスト・レールの再利用
新幹線で使用されたレールやバラストの一部は、社内のリサイクル施設で在来線の基準を満たすように整備したうえで再利用しています。また、再利用できないバラストについては、破砕や選別を行い再生砕石、再生骨材、再生路盤材にするなどリサイクルしています。

バラスト

レール再生プラント
洗浄剤のリユース
電車の部品をきれいにする際の洗浄剤や塗装装置の洗浄用シンナーをろ過装置を通して再利用し、全体使用量の節減に取り組んでいます。

吹田工場では部品洗浄剤と洗浄用シンナーの再利用で、年間6,000リットルを節約し、約200万円の経費節減にもなっています。
リサイクル(再資源化)
駅ごみ・列車ごみ(資源ごみ)のリサイクル
駅や列車から発生するごみのうち、新聞・雑誌、缶・ビン、ペットボトルはリサイクル可能な資源ごみであり、これらをリサイクルすることはごみ発生量の節減とともに原料となる資源の節約にもなります。当社では、駅を中心として分別回収を実施しています。
平成19年度は、資源ごみが7,934トン発生し、そのうち6,346トン(80.0%)をリサイクルしました。
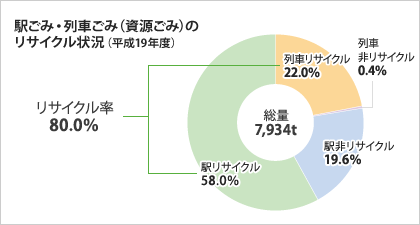
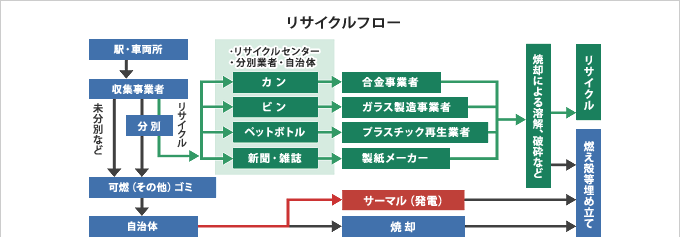
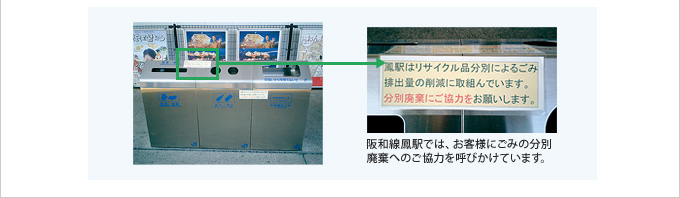
大阪リサイクルセンター
大阪リサイクルセンターでは、京阪神エリアの駅や車両基地から排出される資源ごみを細分化し、リサイクル業者へ引き渡しています。平成19年度は同リサイクルセンターの収集エリアをJR宝塚線沿線に拡大しました。資源ごみとして2,633トンリサイクルしています。
今後もリサイクル未実施箇所での分別によりリサイクル率向上を図っていきます。

分別ライン

再資源化されるスチール缶
駅ビルやホテルにおけるごみのリサイクル
鉄道だけでなく、駅ビルやホテルでのリサイクルも重要な課題と考えています。アクティ大阪ではテナントから発生したごみを分別回収しテナント毎に計量の上、食品ごみや段ボール、ビン、缶などはリサイクルしています。またホテルグランヴィア京都では、食品ごみの一部を堆肥化・飼料化して、収穫物をホテルの食材として利用する「食の循環」サイクルを構築しています。

アクティ大阪外観

アクティ大阪でのごみ計量
鉄道資材発生品のリサイクル
事業活動により、車両や線路、建物、架線などの設備のメンテナンス時に発生する廃棄物と外部からの受託工事を含む駅や構造物などの建設にともなう建設系廃棄物(汚泥を除く)が発生します。
このため、車両の新製や建設工事において廃棄物を抑制する設計や工法を取り入れ、廃棄物削減に向け努力するとともに、発生品については再利用、再資源化など、リサイクルしています。また、建設工事においては、法令上の排出事業者は請負業者ですが、発注者の責務として、正当な処理委託経費の支払い、委託契約内容の確認、処理業者の定期的な確認を行い、排出事業者への指導を行っています。
平成19年度は、19.6万トン発生し、そのうち18.3万トン(93.2%)をリサイクルしました。
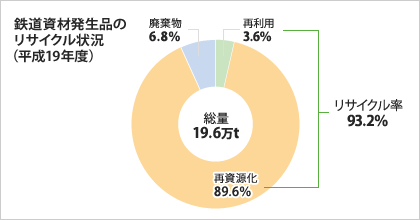

車両設計時には、使用から廃棄までのライフサイクル全体に配慮しています。
車体や車輪などはほとんどリサイクルされますが、リサイクル率をさらに高めるため、新型車両導入時には、車両の腰掛詰物を従来のウレタン系の材質から、リサイクル可能なポリエステル系の材質に変更しています。

レールとまくらぎの間で列車の衝撃を緩衝するために使用しているゴムパッドをチップ化し、踏切路盤材としてリサイクルしています。

架線張替え等で発生した廃電線をリサイクルしています。
きっぷのリサイクル
使用済みの乗車券は、正しく使用されているかチェックしたのち、製紙会社に送られ、トイレットペーパーや建材向けのパルプとしてリサイクルしています。
オフィスごみの削減
本社や支社で発生するオフィスごみのリサイクルに取り組んでいます。たとえば、本社ビルで発生したごみは2007年度87.8トンあり、分別回収の徹底を図り、そのうち62%をリサイクルしています。また、社内LANの構築や文書の電子化を進め、紙使用量の削減に努めています。さらに、プリンターのトナーなどリサイクル可能物品についてもリサイクルを行なっています。

リサイクルボックス


