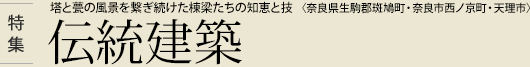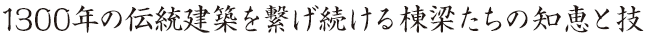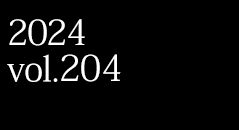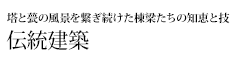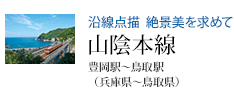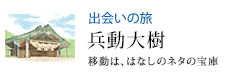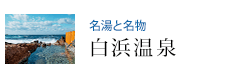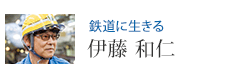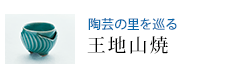「法隆寺の鬼」と呼ばれた法隆寺棟梁の西岡常一棟梁。法輪寺三重塔の再建では、鉄材の補強を推進した学者と対立。宮大工としての気骨を示した。
(提供写真以外は、全て法隆寺iセンターで展示されている)

西岡棟梁は柱の柔らかな曲線を描くために、飛鳥時代の工人が使用したという槍鉋を復元。法隆寺昭和の大修理に活躍した。

法隆寺大工に伝承される口伝には、「諸々の技法は一日にしてならず…」など、法隆寺の棟梁に求められる十カ条の心得が記されている。

西岡常一棟梁(写真提供:小川三夫)

西岡棟梁の愛用した大工道具。「西岡棟梁の道具は使わなくなっても、いつでも出番を待ち、身構えていたよ」と話す小川氏。道具は主のひととなり。気概のある心がまえで仕事をすれば、道具も育つという。
宮大工とは、法隆寺をはじめとする国宝や文化財の保全修理、寺社仏閣の建築や修復を手がける職人だ。宮大工の中でも「法隆寺の鬼」と呼ばれたのが、西岡常一[つねかず]棟梁だ。西岡棟梁は法隆寺昭和の大修理をはじめ法輪寺[ほうりんじ]三重塔の再建、薬師寺伽藍復興に棟梁として大きく携わった。
西岡棟梁は代々、法隆寺の修理や解体に関わる宮大工の家系に生まれた。生家は法隆寺にほど近い西里[にしさと]地区で、祖父の背中を見て育つ。20歳で法隆寺の営繕大工として認められ、昭和初期には法隆寺大修理に取り組む。飛鳥時代創建の法隆寺には、その長い年月の中で修理や再建の手が度々入っている。この大修理を通じて、西岡棟梁は飛鳥から鎌倉、室町、江戸と各時代の技術を自身の両眼で見て学んだ。そうした経験を経て、白鳳伽藍再興を宿願としていた薬師寺から金堂復興の依頼を受ける。

法輪寺三重塔。法輪寺には国内最古、最大の三重塔があったが落雷で焼失。作家 幸田文も再建に尽力し、1975(昭和50)年に再建された。小川氏は26歳の時に棟梁代理として三重塔再建事業に携わり、重責を果たした。

西岡棟梁が引く図面を見て学ぶ小川氏。薬師寺金堂の図面引きは、小川氏が全面的に任された。(写真提供:小川三夫)

法輪寺宝塔断面立面図
『宮大工と歩く奈良の古寺』(小川三夫著、聞き書・塩野米松/文藝春秋)より転載

槍鉋をかける小川氏。「刃物は自分の力量を表す鏡」だと話す。一心不乱に刃物を研ぐことで、大工としての感覚と研ぎ澄まされた精神が養われる。

鵤工舎の1日は5時半の起床で始まり、毎日顔を合わせて食事をとる。共同生活を重ねることで、一人前の宮大工として育っていく。


なら歴史芸術文化村内にある奈良県文化財保存事務所で指定文化財の修復に努める辻氏。「傷みの激しい文化財を自分たちの代で失わず、残して後世に伝える。それが、私の職務です」と話す。神社仏閣の修理にあたり、辻氏はその歴史や背景を学んでから修理に着手するという。
法隆寺とは異なり、薬師寺には建物もなければ図面もない。白鳳伽藍唯一の東塔だけを頼りに、西岡棟梁は徹底的に調査を重ねた。東塔の屋根裏に潜り込んでは白鳳の工人たちの仕事を見て感嘆する。幾百年も重さに耐え、屋根の下で悲鳴をあげている組物、傾きながら荷重を背負う柱…、西岡棟梁は先人たちの知恵や技、その執念を汲み取って見事に再現した。これが宮大工棟梁の凄みだ。
その西岡棟梁の唯一の内弟子が小川三夫[みつお]だ。小川は西岡の元で、法輪寺三重塔や薬師寺金堂、西塔再建にも副棟梁として関わった。「西岡棟梁から手取り足取り教わったことは、一度もない。でも、ずっと一緒やった。そうすると、棟梁の考えがわかってくる。それが大事なんや」と小川氏は言う。一緒に暮らし、共に仕事をする。親方を見ては、親方が何を考え、何をするのかを弟子は考える。すると、親方のやり方がわかってくる。鉋のかけ方や鋸の引き方にしてもそうで、それは親方の技や感覚を己の身体に写すために必要なのだ。それが、職人の修行なのだという。
小川氏が宮大工を志したきっかけは、高校の修学旅行で訪れた法隆寺五重塔だ。1300年の佇まいに衝撃を受け、紆余曲折を経て西岡家に弟子として住み込んだ。弟子入り後の一年間はひたすら刃物研ぎを課され、一心不乱にただ打ち込んだ。修行時代には自身の身体に親方の感覚を写し取るしかなかった。現在、総棟梁である小川氏が率いる鵤工舎[いかるがこうしゃ]本社(栃木県)には、10名の弟子が共同生活を送っている。食事は当番制で、必ず全員で食卓を囲む。就寝までの数時間は必ず刃物を研ぐ。切れない道具では、いい仕事ができない。そうした日々を積み重ね、じっくりと時間をかけることで若者たちは一人前になっていく。
奈良県天理市に、指定文化財を修復している「なら歴史芸術文化村」がある。そこで勤務する辻勝樹[まさき]氏は、薬師寺の東塔保存修理工事にも携わった。「どの文化財でも100年、200年後を想定して手を入れています。先人たちの知恵を読み、“ありのまま”に伝えていく。それも伝統だと思います」と、辻は話した。
水鳥が戯れる大池から薬師寺を眺めると、夕日が伽藍に射し込んでいる。先人たちの知恵と工夫に支えられた双塔が大和の風景として一つに溶け込み、白鳳の工人たちも眺めたその景観はまさに大和のまほろばであった。
参考文献/『木のいのち木のこころ〈天・地・人〉』(西岡常一、小川三夫、塩野米松 著/新潮社)、
『棟梁』(小川三夫 著/文藝春秋)、『宮大工と歩く奈良の古寺』(小川三夫著、聞き書・塩野米松/文藝春秋)