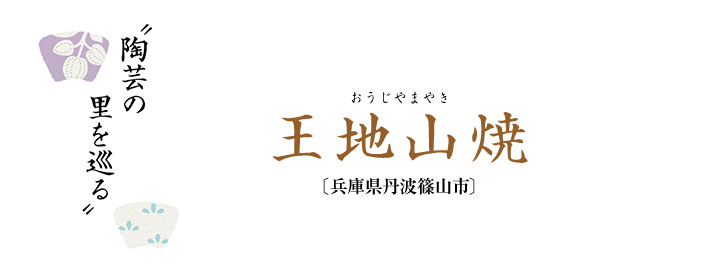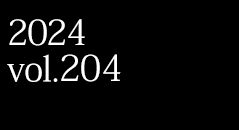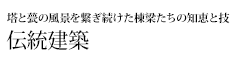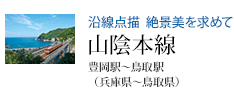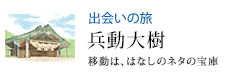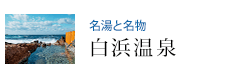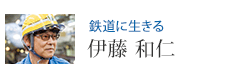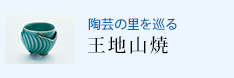青磁鹿牡丹文皿。王地山焼は白い磁土で作られ、釉薬により青磁、青白磁、白磁の3つに分けられる。釉薬によって生まれる濃淡が、さらに美しさを高める。
(写真提供:王地山陶器所 華工房)

最盛期の王地山焼を代表する「型」と呼ばれる技法。手彫りの土型に素地を押し当てて成形する。器を複雑な形状にしたり、表面に繊細な模様を描くこともできる。(写真提供:王地山陶器所 華工房)
兵庫県の中東部に広がる丹波篠山市は日本六古窯[ろっこよう]の一つ、「丹波立杭焼[たんばたちくいやき]」の郷で知られる。その丹波篠山の地には、かつて「幻の焼きもの」と呼ばれた王地山焼が作陶されていた。その歴史は、江戸時代末期に遡る。当時の篠山藩主が王地山に藩窯を築き、京都から青磁の焼成に成功した名工 欽古堂亀祐[きんこどう かめすけ]を招いたことに始まると伝わる。嘉永[かえい]年間(1848〜1854年)に最盛期を迎えたが、江戸幕府大政奉還の2年後の1869(明治2)年に廃窯。作陶期間は、50年ほどであった。
王地山焼は青磁をはじめ染付、赤絵など中国風の磁器を模したものが多い。原材料は主に石英や長石などの陶石で、手彫りの土型で素地を型押しし成形する。
1988(昭和63)年には、地域活性化の取り組みの一つとして王地山焼の復興が計画され、王地山山麓に王地山陶器所が再建された。陶器所では現在、2人の職人が当時の文献や作品を参考に、研鑽に励んでいる。

王地山焼の魅力の一つ、鎬(しのぎ)の技法が施された青磁流麗透ぐい呑。現在の王地山焼には、鎬と面取(めんとり)の技法が不可欠。鎬はカンナを使い、器の表面に溝を彫る技法。面取は、表面を平らに削る技法。
(写真提供:王地山陶器所 華工房)