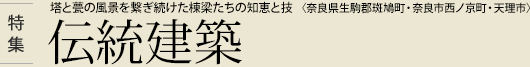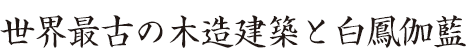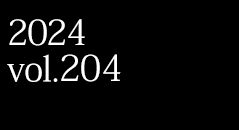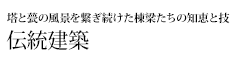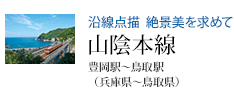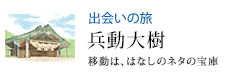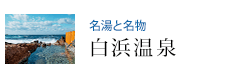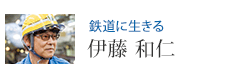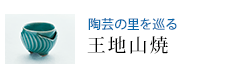荘重[そうちょう]な南大門を通り抜けると、矢田丘陵[やたきゅうりょう]を背後に控えた法隆寺の五重塔と中門[ちゅうもん]が正面に見えてくる。まっすぐに伸びた参道の両脇には築地塀[ついじべい]が続き、時代を積み重ねた情景が馥郁[ふくいく]とした飛鳥時代の香りを醸している。
奈良県斑鳩町[いかるがちょう]に鎮まる聖徳宗総本山 法隆寺は、聖徳太子によって607(推古15)年に建立された。『日本書紀』によると創建当初の法隆寺は、670(天智9)年の火災で焼失したとされる。その後、8世紀初期までに再建されたと考証され、いずれにせよ現存する世界最古の木造建築であることに間違いない。金堂や五重塔、中門、回廊は、幾たびかの修理を経ているが、現在でも建材の65%は、1300年もの時を刻んだ飛鳥時代のヒノキがそのまま活かされているという。
中門からは左手に五重塔、右手には金堂が拝観でき、中央奥の大講堂に通じる回廊が続いている。この伽藍配置は、仏舎利[ぶっしゃり](釈迦の骨)を納める五重塔と本尊を祀る金堂が東西に並立している。日本最初期の寺院である飛鳥寺や四天王寺では、塔と金堂が伽藍の中心部に南北に一直線に並び、塔を中心とした配置であった。しかし、時代とともに本尊崇拝が重要視され、寺院建築は金堂(本堂)を中心とした伽藍が構成されるようになる。

法隆寺五重塔と金堂。五重塔や金堂は現存する世界最古の木造建築で、建築様式は百済(くだら)から受け継いだ。五重塔は仏舎利を奉安するための神聖な建物で、寺院の本尊を祀る金堂とともに伽藍の中心に配置されている。

法隆寺様式の組物を雲斗(くもと)、雲肘木(くもひじき)と呼び、屋根の重さを分散する構造で装飾も施されている。金堂や五重塔の初重の下には裳階(もこし)と呼ばれる庇(ひさし)屋根がつき、雨などによる腐食を防ぐ役割を持つ。裳階は完成後につけられたと考えられる。
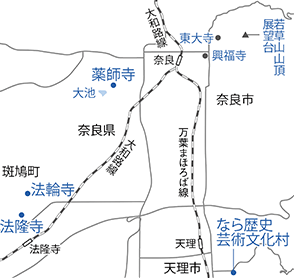

薬師寺の金堂。白鳳時代の二層の姿を復興した上層には、お写経が納められた納経蔵がある。屋根の軒を深く出して反りを持たせることで、優美な姿を見せる。これは日本独自の伝統建築の特徴。

金堂に安置される本尊の「薬師三尊像」。中央に薬師如来、如来に向かって右が日光菩薩、左が月光(がっこう)菩薩。

1981(昭和56)年に再建した西塔。三重の屋根とそれに付属する裳階がリズミカルな建築美を描く。緑の連子窓と朱色の柱や、金具の金色が色鮮やかだ。高さは基壇を含み、約36.4m。

「西塔には連子窓がありますが、東塔にはないですね。でも、昔は窓があったそうです。壁で補強するために、窓を埋めたのではないかといわれています。屋根の反りにしても、違います」と話す薬師寺伽藍副主事の河野師。
斑鳩の里より北東へ、白鳳時代(7世紀末〜8世紀)の伽藍を擁する薬師寺に参詣した。天武天皇は皇后の病平癒のため藤原京に造営を始めたが、その天武天皇は完成を見ずに崩御。その遺志を継いだ皇后が持統天皇として即位し、7世紀末頃に完了する。その後、平城京遷都に伴い平城京右京、現在の西ノ京に移された。
中門を入って対照的な二つの塔を仰ぎ見る。凛とした優美な佇まいの東塔、朱色が華やかな西塔だ。その正面中央には、本尊の薬師如来を祀る金堂が偉容を誇る。法隆寺の伽藍との大きな違いは、薬師寺には塔が二つあることだ。西塔は「舎利塔」として、東塔は「経[きょう]塔(法舎利塔)」として経典を祀っている。また、東塔の初層の内陣には、釈迦の誕生から悟りに至るまでが、西塔には、成道後入滅までの釈迦八相像が祀られている。
薬師寺の歴史は、災厄の歴史でもある。戦乱や落雷、地震、台風など記録に残るだけでも20回以上の被災を数え、1528(享禄元)年の兵火によって、創建当初の伽藍は東塔を除き全て焼失した。昭和に入り、百万巻写経勧進[しゃきょうかんじん]による浄財で伽藍復興に尽力した高田好胤[こういん]管主(当時)の奔走により、1976(昭和51)年に金堂が再建[さいこん]されると、1981(昭和56)年には白鳳時代の姿で西塔を落慶。次いで、中門や大講堂などが再興された。2021(令和3)年には約12年の解体修理を終えた東塔が甦り、薬師寺は白鳳期の姿を取り戻した。
「白鳳期より現在に伝える東塔が残っていたからこそ、伽藍の再興が果たせています」。そう話すのは、薬師寺伽藍副主事の河野泰隆師。金堂や西塔をはじめ、再建された全ての外観や装飾、組み方の基本が東塔にあるからだ。飛鳥以降、各時代の工人たちが修繕修復に携わり、古代より連綿と続く伝統建築を残してきた。その先人たちの知恵や工夫を読み取り、新たな信念を持って次の千年に繋げる現代の宮大工たちがいる。