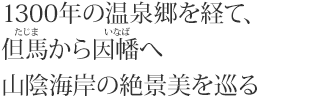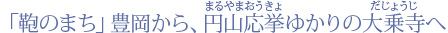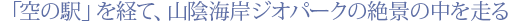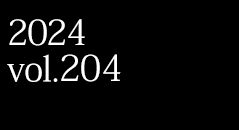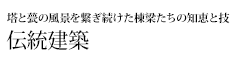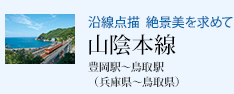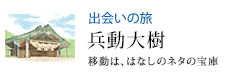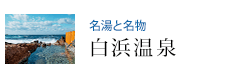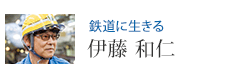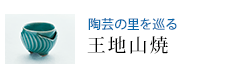![]()
日本海を車窓に、余部(あまるべ)鉄橋を渡る山陰本線の列車。(鎧駅〜餘部駅)
京都駅から本州の西端、下関市の幡生[はたぶ]駅を結ぶ山陰本線。長大な沿線上には日本海の絶景や名所、旧跡が点在する。今回の旅は、豊岡駅から鳥取駅まで81.9km。列車は山陰のリアス海岸に沿って走り、鳥取駅をめざした。

観光列車「はなあかり」は、「地域の華を列車に集めて、お客様と地域の縁を結ぶ列車」をコンセプトに新たにデビューした。敦賀駅から城崎温泉駅まで約5時間かけて結ぶ。
今回の旅の起点は豊岡駅。豊岡市は、日本最大級の鞄の産地だ。江戸時代、藩の奨励で「柳行李[やなぎこうり]」の生産が盛んとなり「行李かばん」が誕生。その伝統技術が後世に受け継がれ、国内有数の鞄産業に発展した。豊岡駅前の大開通りをしばらく行くと「カバンストリート」が南北に伸びている。通りの自動販売機に目をやると入っている商品は鞄で、随所に「鞄のまち」が演出されている。
豊岡駅を出発した列車は円山川[まるやまがわ]に沿って北上する。玄武洞[げんぶどう]駅の周辺には、自然の生い立ちを見せつける「玄武洞公園」がある。約160万年前のマグマが冷えて固まった、六角形をした石柱の柱状節理は迫力の景観だ。
列車はやがて城崎温泉駅に到着。城崎の温泉街は、“まち全体が一つの大きな宿”として旅人たちを迎えてくれる。文豪 志賀直哉をはじめ文人墨客が愛した温泉郷の中央に大谿川[おおたにがわ]が流れ、その畔[ほとり]には柳の木と老舗の旅館が整然と並び、6つの外湯が点在する。カランコロンと軽やかな下駄の音が心地よく、外湯を巡る浴衣姿が温泉情緒をさらに醸し出す。保温性のある古湯に浸かると、たちまち全身の力が抜け、「ほーっ」と口をついて出た。また、今秋の「北陸デスティネーションキャンペーン」に伴い、10月にデビューした観光列車「はなあかり」が運行。敦賀駅から豊岡駅を経由して城崎温泉駅間を走行している。
列車は進路を西に、兵庫県最北端に位置する佐津駅、柴山駅を過ぎるとやがて香住[かすみ]駅だ。駅より南側には、江戸中期に活躍した絵師、円山応挙ゆかりの名刹大乗寺が佇む。「応挙寺」の呼び名で地域に親しまれている。境内に保管される165面の襖絵は、応挙一門が手がけた傑作で、その全てが国の重要文化財だ。

「地場の産業と商店街の活性化」を目的に発足した「カバンストリート」。通りには、27軒のお店が営業している。写真のトートバックは、豊岡市のマスコット「玄武岩の玄さん」。


![]()
国の天然記念物に指定される玄武洞。六角形の無数の玄武岩が曲線を描きながら積み上がっているように見える。

![]()
写真上は「孔雀の間」。
大乗寺副住職の山岨眞應(やまそば しんのう)さんは、「襖絵は見つめるものではありません。応挙は、空間ありきで絵を描いています。人と座敷と襖絵があって完成する。それが、応挙の絵です」と話す。



開湯1300年の城崎温泉と大師山[だいしやま]の温泉寺を歩く

![]()
城崎の温泉街を流れる大谿川沿いには、柳や桜の並木が続く。城崎は湯めぐり発祥の地で、現在は6つの外湯(公衆浴場)が楽しめる。
兵庫県北部に位置する城崎温泉は、開湯1300年を誇る古湯だ。その始まりは諸説あるが、奈良時代の始め、道智上人(どうちしょうにん)が難病に苦しむ人々を救うために、この地で1000日間の仏道修行に専心。それによりに温泉が湧き出したと伝わる。
温泉郷より西の山腹に城崎温泉を守護する温泉寺の本堂が鎮座する。本堂は南北朝時代を代表する建物で、本尊の十一面観音立像が安置されている。
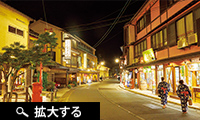
古い街並みを残す温泉街にはカフェや土産物店などが充実している。


城崎温泉守護の寺である温泉寺。本尊の十一面観音立像は、奈良の長谷寺の観音と同木同作で、国の重要文化財に指定されている。


![]()
東浜海岸沿いを走って、東浜駅に入るラッピング列車。(居組駅〜東浜駅)

![]()
鎧駅の地下道をくぐった先から望む日本海。全国でも珍しい「海を見下ろす駅」で人気だ。
香住駅の隣は鎧[よろい]駅。プラットホームから日本海が望める駅は、ドラマのロケ地にもなった。列車は駅を離れるとすぐトンネルに入り、やがて車窓に雄大な日本海が現れると餘部[あまるべ]駅に到着だ。余部[あまるべ]鉄橋「空の駅」展望施設として変貌を遂げた地上約40mの餘部駅は、全面ガラス張りのエレベーターが設置された。そんな展望施設からの眺めは抜けるような青空のもと、陽光で海面が鏡のようにキラキラと輝いている。今回の旅のビューポイントだ。


クリスタルタワーが人気の余部鉄橋と餘部駅

![]()
2017(平成29)年に完成した余部クリスタルタワー。地上から余部鉄橋「空の駅」をつなぐエレベーターが設けられている。高さ約40mの展望台からは、日本海のパノラマが望める。夜には、タワーがライトアップされる。

余部鉄橋の下は整備され、空の駅公園として生まれ変わった。旧余部鉄橋の橋脚やマクラギを利用した休憩所が設置されている。
旧余部鉄橋の誕生は、1912(明治45)年。鉄橋は完成したが、駅はなかった。鎧駅まで歩くなど、地域の人々は不便な生活を強いられたが、1959(昭和34)年に「餘部駅」が設置された。
より堅牢さが求められた新鉄橋は、2010(平成22)年にコンクリート橋に付け替えられた。2017(平成29)年には全面ガラス張りのエレベーターが設置され、地上には芝生の公園が整備されている。空の駅・餘部駅に連絡する愛称「余部クリスタルタワー」は、今では観光名所の一つになっている。

列車は進路を西に久谷[くたに]駅を過ぎるとまもなく浜坂駅。豊かな海の幸に恵まれた新温泉町浜坂には、6つの漁港があり、その中心が浜坂漁港だ。早朝の競[せ]りでは威勢のいい声が場内に飛び交い、たちまち競り落とされていく。浜坂漁港では冬の風物詩である松葉がにのほか、季節に応じてホタルイカやエビなどが水揚げされている。
列車はさらに進路を西に進み、居組[いぐみ]駅を過ぎると鳥取県に入る。日本海沿岸部を走る列車は、「TWILIGHT EXPRESS 瑞風[みずかぜ]」の停車駅でもある東浜[ひがしはま]駅へ。駅前すぐには、美しい白砂の東浜海岸が広がる。この山陰海岸一帯は、「山陰海岸ジオパーク」として、世界ジオパークに指定されている。その範囲は、険しいリアス海岸をはじめ奇岩や巨岩の岩礁地帯や砂丘、温泉など多岐に渡っている。
東浜駅から約30分で終着の鳥取駅。駅南口すぐのところに、鉄道遺産が展示されている「沢井手公園(鳥取鉄道記念物公園)」がある。鳥取駅の高架事業に伴い、移設した旧鳥取駅のホームや線路、信号機などが保存され、市民の憩いの場になっている。
ここから北へ足をのばすと、砂の世界が広がる鳥取砂丘だ。砂丘の風景は異国のようで、年間130万人以上の観光客が訪れる。来訪客はこんもりとした小高い丘(馬の背)をめざし、黙々と砂を踏みしめる。数万年前より砂と潮風で形成された砂の丘は、国の天然記念物だ。
温泉郷の名湯に癒やされ、太古より連綿と大地の歴史が続く山陰海岸ジオパークの自然の絶景美に触れた旅であった。

![]()
浜坂漁港の早朝の競り。漁場は隠岐諸島周辺や兵庫県、鳥取県の沖合で、11月の松葉がに漁解禁以降では、13隻のカニ漁船によって水揚げされる。


![]()
東西約16km、南北約2.4kmにわたる鳥取砂丘は、日本を代表する海岸砂丘。砂丘本来の姿を残すエリアは、起伏が大きく、風紋が美しい。鳥取砂丘は1955(昭和30)年に国の天然記念物に、1963(昭和38)年には国立公園に指定された。

鉄道遺産が展示される沢井手公園。旧鳥取駅で使われていた実物の施設や設備が展示され、実際に触ることもできる。



太古からの地球の変動を伝える山陰海岸ジオパーク

![]()
新温泉町の諸寄(もろよせ)港の夕暮れ。北前船が盛んであった頃、風待ち・潮待ち港として栄えた。

山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館

副館長を務める安藤さんは、「この施設で学んだ後に、実際にジオサイトに足を運んでもらうとより理解が深まります」と話す。
山陰海岸ジオパークは、京丹後[きょうたんご]市から鳥取市まで東西120kmに及ぶ。この地域では、日本列島が大陸の一部だった時代から日本海形成に関わる火成岩類や地層、地殻変動で形成されたリアス海岸や砂丘など、多彩な海岸地形を観察できる。
「山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館」副館長の安藤和也さんは、「大地の成り立ちは、我々の日常生活とつながっています。この施設を通じて気がついてもらえれば」と語る。館内では、ジオパークの魅力を資料や映像で紹介している。