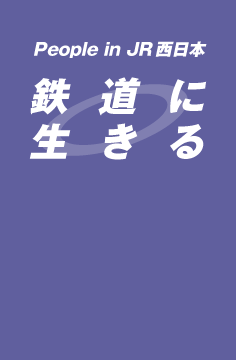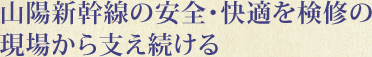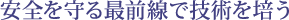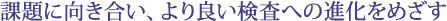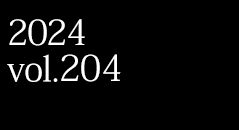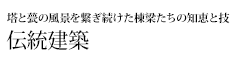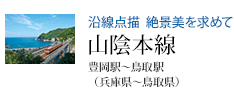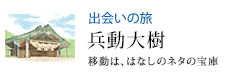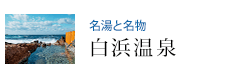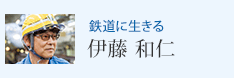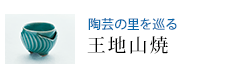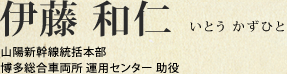

「停止」に関わるブレーキ部分の確認。新人にはパッドのズレや油切れなど、修繕のポイントを丁寧に指導する。
山陽新幹線は、2025(令和7)年3月に全線開業50周年を迎える。博多総合車両所はその検査・修繕拠点として、半世紀にわたる安全走行の歴史を支えてきた。現在、交番検査チームを率いる伊藤は、新幹線の揺るぎない安全を次代に繋ぐため、検査の将来像を見据えた取り組みに力を注ぐ。

運転台担当から各車両の検査項目について指示を出し検査が進む。指示通り正確に行われているか、進捗を見守る。
博多総合車両所は、山陽新幹線の車両基地として全線開業を翌年に控えた1974(昭和49)年に開設された。伊藤は1980(昭和55)年に当時の国鉄に入社。「全般検査」を受け持つ電車第二センターに配属され、定期検査の中で最も大がかりな検修業務の現場からスタートした。「走行距離120万kmまたは36箇月ごとに実施する全般検査は、車両と台車を切り離して搭載機器や配電盤などを外し、入念な点検を行います。新人の頃は一日中ワイヤブラシを持ち、車体からぶら下がる配線の端子に付いた汚れやサビを落としていました」。検査・修繕を終えた機器類を塗装され輝きを取り戻した車両に再び搭載した後、耐圧試験などを経て車両所から送り出す。一連の検修業務に携わる中で、伊藤は安全を守るための基礎を身につけていった。
転機が訪れたのは、入社からおよそ3年が経った頃。電車センター内に改造工事を担当する部署が立ち上がり、伊藤もその一員に加わったのだ。以降、伊藤はメンテナンスの枠を超え、新幹線車両に新たな息吹を与える改造工事においてキャリアを積み重ねた。

「日頃のコミュニケーションが仕事の場面にも生きてきます」と伊藤。相談には気軽に応じ、風通しの良い職場をめざす。
最高時速300kmという高速走行を誇る山陽新幹線は、車体のサビや塗装の劣化などによって老朽化が進むという。「腐食部分を新品に交換する工事や搭載機器のソフト変更に伴うバージョンアップなど、幅広い改造・改良を行っていました」。当時の車種は初代0系。丸みを帯びた形状の先頭部分を切断し、別の胴体車両と合体させる「頭付け改造工事」では、屋根上や床下の複雑な配線処理に苦労したそうだ。車両の延命を目的にした工事が多い中、0系では「ビュッフェ」の設備を組み込んだり、一両を丸ごと映画館に改造した「シネマカー」も登場させた。「映画を見たり食事を楽しむお客様の笑顔に接した時は、工事のやりがいを実感しました」と語る。
1997(平成9)年1月、伊藤は培った改造工事の技術を携え、現在のJR西日本新幹線テクノスに出向する。ここでは約8年間技術指導にあたり、若手社員の育成に尽力した。その後車両所に戻り、配属された技術科車両改造グループ(当時)では、工事の資材調達や人員調整を担うことになる。現場を離れ、これまでと逆の立場に戸惑いながらも、「プラレールカー」や『新世紀エヴァンゲリオン』とコラボした「500 TYPE EVA」など、人気の改造車両の導入に携わり、「のぞみ」から「こだま」専用車両となった500系の活性化を推進した。
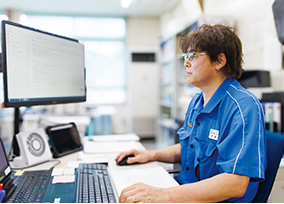
将来を担う若手の育成は喫緊の課題。技術導入による検査の省力化も含め、JR西日本グループ全体での取り組みを計画する。
現在伊藤は、運用センター交番検査グループの助役として、新人からベテランまで26名の技術者とともに安全運行の一翼を担う。新幹線には、走行距離と検査周期を基準に4種類の定期検査がある。「交番検査」は N700系の場合、走行距離6万kmまたは45日以内に実施され、集電装置やブレーキ装置、走行装置などが正常に作動するか、また車体の状態・機能についても在姿状態で点検する。現場は今、国鉄時代からのベテラン社員が退職していく中で、要員不足という課題に直面していると伊藤は話す。「検査を担当するには、号車や編成ごとに社内で定めた各カテゴリの基準に合格することが必要です。合格していない若手は限られた業務しかできないため、細分化されているカテゴリを見直し、若手の即戦力化に取り組んでいるところです」。少ない要員でいかに漏れのない検査を実行していくか。例えば、定点カメラや画像解析装置を取り入れ、ボルトの緩みを映像で確認することも検討中という。最終的には、交番検査の施工時間短縮に繋げるのが目標だ。安全を担う検査のあるべき将来像を見据え、JR西日本グループ全体での取り組みが続く。