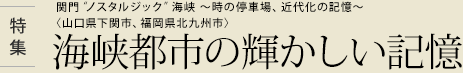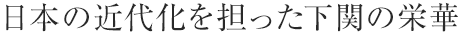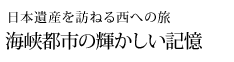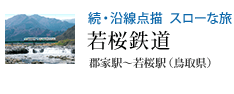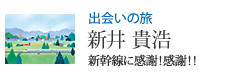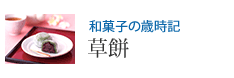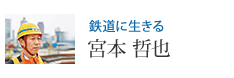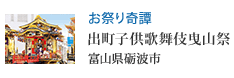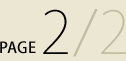

旧秋田商会ビル。秋田商会は木材などを扱う商社と海運業などを営んだ。建物は西日本初の鉄筋コンクリート造り。内部もほぼ当時のまま保存され公開されている。夜間にはライトアップされる。

江戸時代、下関は西日本一の港だった。「廻船寄らざるはなし」、「一日の中、出入各千艘に至る」と記されたほどの賑わいだった。シーボルト博士も「下関での滞在は本当に楽しい」と述べている。さらに長州藩は海を埋め立てて港湾を拡張整備し、新しい時代の港湾経営に乗り出した。この基盤の上に下関の発展がある。
明治になって下関が大陸への定期航路の寄港地に指定され、門司とともに国際港湾都市として飛躍的に発展したのも、藩政時代の港湾整備があったからに他ならない。下関英国領事館の開設も町に活力をうながす契機となった。
海路、陸路の物流拠点として下関がいかに注目されたかは町の佇まいからもよく分かる。明治から昭和初期の下関は「西の大阪」、「西のウォール街」に例えられるほどの一大金融街を形成していた。1876(明治9)年に旧三井銀行が一等出張店を設立。以後、そうそうたる銀行の支店が次々に設立され、日本銀行も大阪支店に次いで開設した。大正時代の開設ピーク時には銀行の本支店が13もあった。これは破格のことだ。

老舗料亭 春帆楼に隣接する日清講和記念館。講和会議で実際に用いられた調度品を使い、当時の様子を紹介している。

春帆楼のトラフグの薄造り。伊藤博文が解禁させたといわれる「下関のふく料理」は、春帆楼から全国に広まったという。

唐戸市場のふく専門仲卸商の「道中」の主人、道中さん曰く、「ふく料理は下関の文化遺産です」。

下関市教育委員会の藤本さん。「ノスタルジックな町の佇まいだけでなく、2つの海峡都市が担った近代化の歴史もぜひ、知っていただきたいです」。
1901(明治34)年には山陽鉄道が下関まで開通。下関は経済都市としてますます注目を集めた。海峡を眺める通りに沿って歩くと、幕末維新の史跡とともに、近代化で沸きたった往時を物語る重厚な石造りの建造物が点在している。
この頃には、欧米や大陸と交易で繋がる華やかな大都市だった。埠頭は出船入船の客で賑わい、鉄道から次々に人々が降り立った。旧下関駅は現在の下関港近くの細江町にあって、ここから列車ごと船に載せて対岸の門司に連絡した。旧駅周辺の繁華街には銀行のほか船会社、貿易商社などが社屋を並べていた。
旧秋田商会ビルや旧赤間関郵便電信局は当時の姿を今に伝える下関観光のシンボルの一つだ。交差点を渡ると、大きな「ふく」が目印の唐戸市場がある。「フグ料理」は日本遺産構成文化財の一つ。「下関のふく」の由来は、日清講和条約の場となった料亭「春帆楼[しゅんぱんろう]」と明治の元勲、伊藤博文に深く関わっている。
フグ食は豊臣秀吉によって全国的に禁じられていたのだが、下関の春帆楼に逗留していた伊藤博文が所望し、あまりの美味にフグ食を解禁したといわれている。以後、フグ料理は近代化とともに、下関の「郷土の味」として全国に広まった。絵皿に花びらのように盛られた薄造りのフグはまさにアートだ。
因みに下関ではフグとはいわない。「地元では福に通じる、ふくと呼びます」。そう教えてくれたのは唐戸市場でふくと鮮魚の仲買商を営む「道中」のご主人の道中哲也さん。「関門地区の海はふくの好漁場であるだけでなく、下関には全国唯一のふく専門のせり市場があって全国からふくが集められているのです」。

唐戸桟橋付近から眺めた早朝の関門海峡。命からがら遣唐使船が通ったことを思うと感慨深い。潮の流れは昔も今も変わらない。
そして、旧秋田商会ビルで会った下関市教育委員会・文化財保護課の藤本有紀さんは、日本遺産「関門“ノスタルジック”海峡」に関わった一人としてこう話した。「日本の近代国家の建設に2つの海峡都市がどう貢献したかを、より多くの人に認識していただけたらと思っています」。火の山公園に登ってあらためて海峡を見渡した。帯のような海峡を無数の船が行き交う。
本州と九州を隔てた海峡は今では海底トンネルと橋梁で結ばれている。海峡を挟んで向き合う2つの海峡都市は今や海峡をとり囲む一対の都市に見えた。