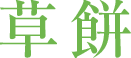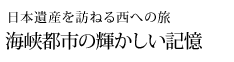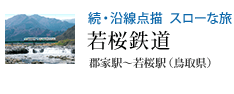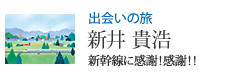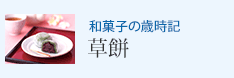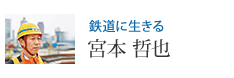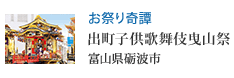待ちわびた春の到来を告げるように、よもぎの新芽が芽吹く。その柔らかな若葉を搗[つ]き混ぜて作る「草餅」は、色合い、香りも清々しい春の代表菓だ。
よもぎは、日本人の暮らしに馴染み深い薬草として知られる。北国街道の宿場町、木之本の老舗菓匠に受け継がれるこだわりの草餅に、その由来を訪ねた。

宿場町の面影を残す木之本の「菓匠 禄兵衛」本店。(撮影:Satoshi Asakawa)

移りゆく季節の中で、自然の色や姿を写し取る和菓子。四季折々の意匠は、日々の暮らしに季節の訪れを告げる役目も果たす。春に芽を出すよもぎを摘み、その若葉を入れて搗[つ]いた餅でつくる「草餅」も、そんな季節菓子の一つだ。よもぎは、「蓬」や「艾」と書かれるキク科の多年草。餅やだんごなどの材料に用いるだけでなく、独特の香りと薬効を持つ生薬としても活用されてきた。よもぎの葉の裏側にある綿毛から作られる「もぐさ」は、灸[きゅう]の材料として知られている。
草餅の歴史は古く、由来を辿ると古代中国の風習に行き着く。かつて3月3日の上巳※[じょうし]の節句には、けがれを祓う意味で香りの強い草を混ぜた餅を食べる習わしがあったという。日本に伝わったのは9世紀頃とされ、平安時代の歴史書『日本文徳天皇実録』にその名が現れる。ただし、現在よもぎを搗き込むことで作られる緑色は、当時は春の七草の一つ母子草[ははこぐさ](ゴギョウ)が使われていた。江戸時代になると、上巳の節句は女児の健やかな成長を願う桃の節句の行事として広く祝うようになり、厄除けの願いを込めて草餅を食べる風習も変わらず受け継がれていった。雛人形に供える菱餅の色にも、その名残が見て取れる。そして次第に、母子草はよもぎへと置き換わっていく。その理由として、母子草では餅にする際に母と子を搗き混ぜるようで縁起が悪いためといわれるが、よもぎの香りの強さ、また入手しやすさなども背景にあると考えられる。
※上巳とは、旧暦3月の最初の巳の日のこと。江戸時代の初め、五節句の制度が整えられたのをきっかけに「桃の節句」として広まった。

かつては、山に自生するよもぎを摘んでいたが、年々取れにくくなったことから自家栽培に。草の繊維が残らないよう、葉の上の柔らかな部分だけを使用する。

餅に使う滋賀羽二重糯米は、創業当時から変わらず地元近江の農家から仕入れる。柔らかく歯切れが良いことから、大福生地に最適の品種という。

北海道十勝産の小豆は風味が良く、柔らかな餅菓子との相性が良い。熟練の技で、あっさりしながらコクのある餡に仕上げる。
北国街道の宿場町 滋賀県長浜市木之本町は、古くは京阪神と北陸とを結んだ要衝の地。日本三大地蔵の一つ「木之本地蔵院」の門前町としても賑わい、湖北の多彩な文化を醸成してきた歴史を持つ。往時を偲ばせる風情ある町並みの一角、地蔵坂と呼ばれる緩やかな坂道の中ほどに、重厚な外観と白い暖簾[のれん]がひときわ目を引く「菓匠 禄兵衛[ろくべえ]」が店を構える。前身は、初代が1926(大正15)年に創業した「居川菓子舗」。現在は4代目の居川信彦さんが、古き良き伝統に新たな息吹を吹き込みながら暖簾を守る。
店の看板商品は、ういろう、でっち羊羹などとともに代々受け継がれてきた「名代[なだい]草餅」。素材を選りすぐり、一つ一つ丁寧に作られる「菓匠 禄兵衛」の和菓子の中でも、素材へのこだわりが際立つ自慢の逸品だ。草餅に使われるのは、社員が土を耕して苗を植え、成長を見守りながら育む自家栽培のよもぎを主にして、地元滋賀県産の羽二重糯米[はぶたえもちごめ]に入れて搗いている。緑が色濃く、しっとり柔らかな餅で包むのは、味の要となる餡[あん]。北海道十勝産小豆を、季節によって火加減や砂糖の分量を調節し、なめらかに炊き上げる。この、「餅」と「餡」の一体感ある味わいが、昔も今も変わることのない人気を支える。素朴な姿ながら、お祝い事や進物用の和菓子としても選ばれる地域の銘菓。収穫したての新よもぎで作る草餅が店頭を飾る頃、湖北は本格的な春を迎える。