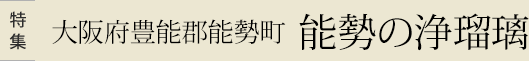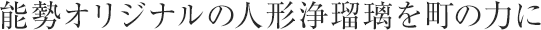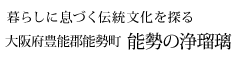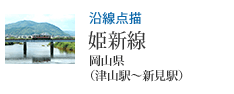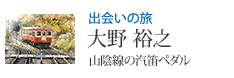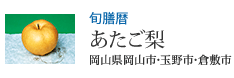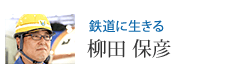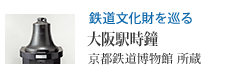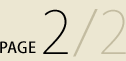
能勢町の中央を小高い尾根が南北に横たわり、地形的に町は東西に分かれ生活圏も異なるが、浄瑠璃は地区を越えた町ぐるみの文化として育まれている。この町では家族、親戚、知人、ご近所の誰かが浄瑠璃と何らかの関わりがあるという。

「淨るりシアター」は能勢人形浄瑠璃の発信拠点。ロビーには竹本井筒太夫の系図や能勢の浄瑠璃に関する古い道具や資料が常設展示してあり、鹿角座による定期公演が行われる。

地元の匠の技を活かして商工会青年部が結成した「伝統文化の黒衣隊」は、各地から依頼を受けて人形や道具類を修理している。人形衣裳(左)、床本を置く見台(中)、太棹三味線(右)。
町の施策も、伝統の浄瑠璃を地域振興の一翼に位置付けて「人材の育成と能勢文化の創造」を掲げる。その拠点となるのが「淨るりシアター」だ。隣は町役場。すぐ近くを鮎の棲む川が流れ、裏手には田畑が広がっている。訪ねたのはシアターの館長、松田正弘さん。
「シアターは多目的の町民ホールですが、名称には地域に長く伝えられた浄瑠璃文化を財産として守るだけでなく、町の発展の力にするという強い決意を込めています」。さらにつけ加えて、「ただし、町づくりの力にできるかどうかはプロデュース次第」。
「面白いでもカッコいいでもいいから、観る人に訴え支持される」内容でなくてはならないという。そこで取り組んだのが、三味線と語りの能勢の伝統である浄瑠璃に人形と囃子[はやし]を加えた「能勢人形浄瑠璃」。2006(平成18)年には町制施行50周年を機に劇団を旗揚げする。「能勢人形浄瑠璃 鹿角座[ろっかくざ]」である。太夫ほか三味線方、人形遣い、囃子のメンバー全員が地元や近郊の住人。職業もさまざまで、主婦もいる。旗揚げ以前から人材の育成に努め、浄瑠璃監修に大阪日本橋の「人形浄瑠璃文楽座」の竹本住太夫、人形監修に人間国宝の吉田簑助[みのすけ]、それに加え、桐竹勘十郎さんやお弟子さんらプロの技芸員による直接稽古で技を磨き、今では定期公演のほか各地からの依頼公演も行っている。

「鹿角座」座長の岡本さん。「メンバーの職業は多彩です。会社勤めの方が多くて練習も大変です」と話す。

能勢の地を舞台とする「鹿角座」オリジナルの作品、『閃光はなび』の1シーン。
現在の座長は、44代目竹本井筒太夫で“おやじ”を引退してからは、竹本薬研斎[やげんさい]を名乗る太夫の岡本勲[いさお]さん。本職は薬局店を営む薬剤師。その岡本さんが、鹿角座が目指すところをこう話した。「能勢オリジナル。他所では観られない能勢だけの人形浄瑠璃。伝統とは勝手が違うけど」。
キーワードは創作性とビジュアル性で、野心的に新作に取り組む。オリジナル演目『閃光はなび』は能勢に宇宙人が降り立つ奇想天外な物語。『能勢三番叟[のせさんばそう]』、『名月乗桂木[めいげつのせかつらぎ]』、『風神雷神』も能勢オリジナル。囃子も表舞台に登場させてより華やかに視覚的な舞台を演出する。
そればかりか人形の首[かしら]も現代的な顔立ちで、人形の衣裳は洋服地。舞台衣裳に舞台美術も全て能勢オリジナルにこだわる。また、こども浄瑠璃の公演やワークショップも行うなど、世代を超えて住民を繋ぐ人形浄瑠璃の普及を図っている。さらに商工会青年部ら有志による「伝統文化の黒衣隊[くろこたい]」では、木工や漆など昔から受け継ぐ地元の匠の技で、修理に苦慮する全国の人形浄瑠璃の衣裳や道具類を修繕したりもしている。それは地場産業の育成を促すことにもなる。

中学生らによる「こども浄瑠璃」の公演。太夫、三味線とも大人顔負けだ。

「三味線ワークショップ」。鹿角座では、能勢人形浄瑠璃の時代を担う人材の育成にも力を入れている。語り、人形、囃子、こども浄瑠璃のワークショップも行っている。
「能勢人形浄瑠璃を全国に発信し、多くの人に能勢に足を運んでもらい、能勢を元気で潤いのある町にしたい」と松田さん。鹿角座を含めた能勢の特色ある町ぐるみの取り組みは全国でも注目を集め、2007(平成19)年に「サントリー地域文化賞」を受賞。これは能勢の浄瑠璃文化に重ねられた新しい伝統の証でもある。
無理を承知で座長の岡本さんに浄瑠璃の一節を披露していただいた。背筋をピンと伸ばし、シアターの隅々まで朗々と響き渡るその語りぶりは、いいようもなく胸を揺さぶる迫力があった。太夫に口説かれ、最初は嫌々だった弟子が「やってみて面白さにはまった」ということが体験的に理解できた。200年以上も引き継がれる理由の一つだろう。
収穫が始まった谷間を風がそよっと吹き撫でていく。集落のどこかの家から浄瑠璃が聞こえてきそうだ。昔と変わらない、豊饒で平穏な山里の風景である。