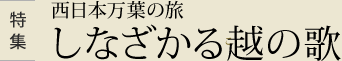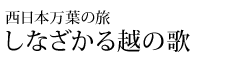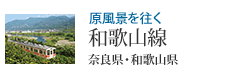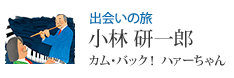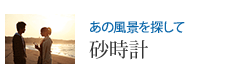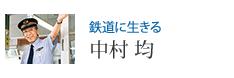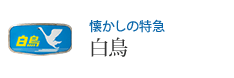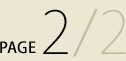
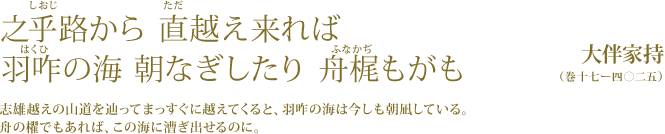
家持には国守として年一度、越中国内を巡視する重要な役目があった。官の稲を民に貸し付けて利子の稲を納めさせる出挙[すいこ]の巡行だ。能登四郡の巡行に向かった時に詠んだのが上の歌だ。伏木から氷見を経て能登半島を横断する志雄街道の山道を行くと、やがてその先に羽咋の海があった。

能登一宮として信仰を集める気多大社。
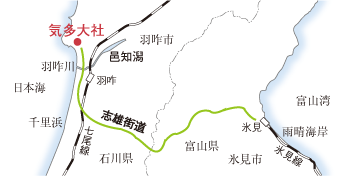
羽咋の海とは邑知潟[おうちがた]との解釈もあるが、歌の前書きの題詞[だいし]には「北方の能登一宮気多[けた]大社に参拝しようと海辺を行く時に作った歌」とあるから、おそらく広々した千里[ちり]浜を気多大社に向かっていたのだろう。目の前の羽咋の海、日本海は朝凪で風も波もなく穏やかだ。朝の穏やかな海辺を馬に股がってのんびりと行く家持の姿が歌から想像できる。
歌では、渋谿の海とは異なる外海の広大さを素直に写実した。そして、こんな静かな海なら船を漕ぎ出してみたいものだと詠むことで朝の陽光や、光り輝く海面さえ描き出す。この出挙の巡行で9首の歌を残しているが、すべて訪れた土地の風土を詠んでいる。いずれの歌も初めて見る新鮮な驚きと体験が詠ませたのだろう。越中の風土が、家持の歌の写実性をいっそう開花させたのかもしれない。
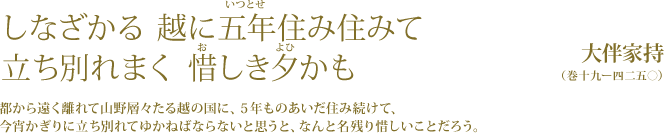

越中に家持が滞在したのは746(天平18)年から751(天平勝宝3)年までの5年間で、年齢では29歳から34歳まで。この越中時代にもっとも旺盛な作歌活動をし、生涯の作品の半数近くを詠んでいる。望郷の思いを紛らわすためという説もあるが、越中万葉は家持によって開かれ、越中の風土がそれまでにない歌ごころを育んだ。
家持は越中の四季を、海や山や川、雪月花、鳥を詠み、初めて見るものの驚きを鮮やかな写生の目と観照の目であるがままに詠んだ。宴のたびに、行幸のたびに詠んだのである。しかもそれらは歌日記の体裁で、優れた文学であるとともに万葉時代の越中を知る貴重な記録にもなっている。中でも「立山[たちやま]の賦[ふ]」「二上山[ふたがみさん]の賦」「布施[ふせ]の水海に遊覧する賦」は越中のすばらしい風土を詠った名作として、「越中三賦」と呼ばれている。

家持の「立山の賦」にも詠まれた、立山連峰の雪解水を集めて下る片貝川の流れ(富山県魚津市)。

勝興寺境内の国庁跡の石碑。
そして751(天平勝宝3)年8月、家持が越中を去る時が来た。少納言となって奈良の都へと帰郷する前日の餞別の席で詠んだのが上の一首だ。都に帰る喜びと、親しんだ越中との別れとが胸中複雑に織りなして感慨深い。家持が最後に脳裏に焼き付けたのはどんな風景だったろう。二上山の高台に立つと、富山湾の向こうに立山連峰がそびえている。家持がきっと最後に眺めたであろう山並みは今も万葉時代と寸分も変わっていない。