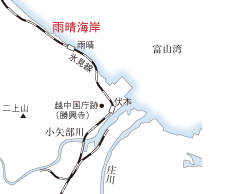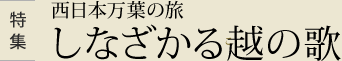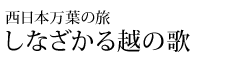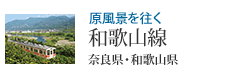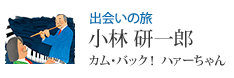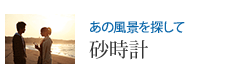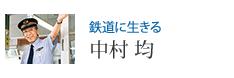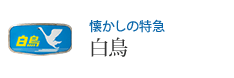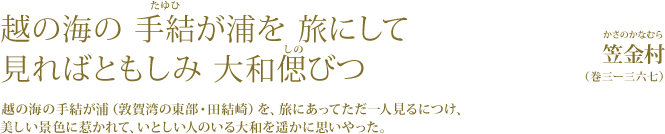
歌の作者、笠金村は聖武朝(724から749年)の前期、万葉集第三期の宮廷歌人で、35首の歌を万葉集に残している。上の歌は、角鹿[つのが]の津(敦賀の港)から船出して北陸路を行く心模様を詠んでいる。奈良と敦賀は、今なら電車で2時間ほどの距離だが、万葉時代にはなにしろ「しなざかる越」「天ざかる越」と詠われた異郷の地だ。
奈良の都を旅立ち、琵琶湖の北の海津、塩津を経て愛発山[あらちやま]の関を越えて越前に入る。あるいは湖西の今津から山を越えて若狭から敦賀へ。そして敦賀から先の北陸路は南条山系の折り重なる山々を越えなければならない。ようようの思いで敦賀にたどり着いた金村は、海路で敦賀湾を北上したというが、陸路も海路も困難を伴う道行であったに違いない。
金村が詠んだ手結[たゆひ]が浦(現在の田結[たい]崎)は、敦賀湾内の漁村で朝廷に献上する塩の産地だった。この浜で都に送られる塩を焼く煙に目をとめて、思わず郷愁を覚えたのだろうか。大和はあまりにも遠い。そのもの寂しさを歌に託した。「ともし」とは、心惹かれてたまらない気持ちを表す言葉だ。朝廷運営を定めた延喜式[えんぎしき]によれば、越中へは「上十七日、下九日、海路廿七日」とある。都人にとって北陸路はしなざかる越であった。
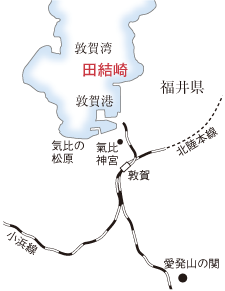
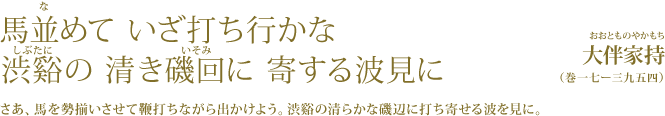

朝焼けの渋谿(雨晴海岸)と女岩。
万葉集全20巻のうち、巻16から巻19には越中にかかわる作品が約300首収録され、そのほとんどが大伴家持が国守[くにのかみ]として越中赴任中に詠んだ歌だ。父は大宰府の長官を務め、万葉歌人としても名高い大伴旅人[たびと]。大伴家は朝廷を警護する武門の名門で、家持は746(天平18)年、29歳で能登国を含む越中国の長官として着任した。

浄土真宗中興の祖・蓮如上人が開いたとされる名刹、勝興寺。この境内に越中国庁があったとされる。
国庁は、現在の高岡市伏木町、氷見線の伏木駅に近い高台にある名刹勝興寺[しょうこうじ]の境内にあったとされる。上の歌は着任1カ月後の夜の宴の席で詠んだ一首で、越中の地名を詠んだ最初の作品だという。渋谿[しぶたに]は現在の雨晴[あまはらし]海岸付近で、ここからは富山湾を隔てて立山、劔[つるぎ]山の連峰が屏風のようにそびえたつ絶景が望まれる。その反対側には能登半島が横たわり、荒磯には白波が寄せ、延々とつづく白砂の浜は今も富山県を代表する景観だ。
宴の席で聞いたまだ見ぬ異国の海の風景に、家持は胸躍らせる。弾む気持ちで、「馬を並べてすばらしい海を見に行こうじゃないか」と宴のみんなを誘っているのだ。家持のはつらつとして新鮮な抒情性がよく表れている。海がめずらしい都育ちの家持には、渋谿の海の景観ほど創作意欲をかりたてた素材はなかったといっていい。