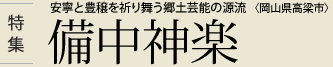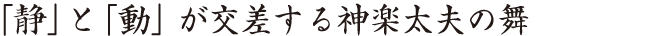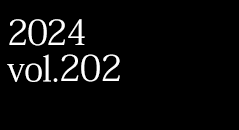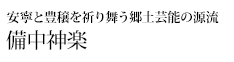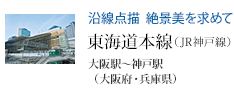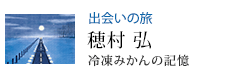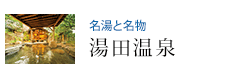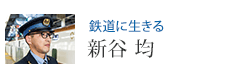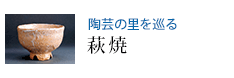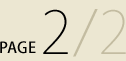

神殿中央の天井に吊り下げられた白蓋。白蓋神事を通して、八百万の神々は神殿に鎮座する。

現在も現役の神楽太夫である三宅さんは70歳。「幼い頃から太鼓の音を身近に、神楽に親しんできました。昔から、同じことをしていますが、飽きることがない。だから、やめられないですね」とにこやかに話す。

白蓋は奉書を縦二つに折り、旭日、社殿、鳥居の模様を切り刻んで仕上げる。この切り紙を広げ、木枠の四面に一枚づつ貼り付けることで白蓋ができあがる。

白蓋の切り紙は、三宅さんが作ったもので全て手作業で作られている。切り紙の準備だけでも丸一日を要するという。
國橋の顕彰碑からほど近く、旧小学校の跡地に新設された「日名交流館かぐら」がある。毎年4月の最終日曜日に、國橋を顕彰するための「國橋まつり大神楽」が大々的に催される会場となる。館内には、備中神楽の舞台である「神殿[こうどの]」が常設されている。神殿は「神座[かむくら]」のことで、この神座が、神楽の語源ともされている。神楽とは神々が楽しむ芸能を意味し、「神遊び」ともいう。神楽は神々の招魂や鎮魂のための神事が芸能化したもので、神迎えをして神殿を建て、清めや祓[はら]いを行い、八百万の神々を勧請[かんじょう]し鎮座していただくことから始まる。この日名交流館かぐらで、備中神楽上房神能社[じょうぼうしんのうしゃ]による荒神神楽の主だった演目を披露していただいた。
まずは神々を勧請する神殿を清める「榊舞[さかきまい]」、神の鎮座を願う「白蓋[びゃっかい]神事」、降り立った神を先導する「猿田彦[さるたひこ]の舞」などの「神事舞[しんじまい]」、次いで神を楽しませる「神代神楽[じんだいかぐら]」となる。清めの儀である榊舞では、舞手となる神楽太夫が榊と鈴を手にそろりそろりと歩き回る。やがて、霊力を秘めた榊の葉を口にくわえ、罪や穢[けが]れを除去して心身を清める禊祓[みそぎはら]いをする。次いで白蓋神事となり、清めた神殿の天井中央には白蓋と称する切り紙飾りが吊り下がり、神職役の太夫の綱さばきによって紙吹雪が乱舞する。続けて、太鼓を叩く太夫の頭上で白蓋が縦横無尽に動き回る。その激しさは、荒ぶる神々のようだ。神殿に神々が降臨すると、眼光鋭い鼻高面に白いシャグマ(頭髪)の猿田彦命[さるたひこのみこと]が、神々を導きながら力強く踊り回る。最後に神代神楽の一つ「大蛇退治[おろちたいじ]」の素戔嗚尊が姿を現した。素戔嗚尊と対峙した八頭大蛇[やまたのおろち]は所狭しととぐろを巻き、軽快な太鼓の音が神殿の舞台を盛り上げていく。

神殿の座を清める榊舞。霊力のある榊を手にして舞い、最後に榊の葉を口にくわえ、「無上霊法神道加持」と呪文を唱えて禊祓いとする。

白蓋神事。神殿中央の天井に吊り下げた白蓋が自由自在に激しく動き回る。白蓋の揺れが鎮まることで、神々が鎮まったとされる。

神々の降臨の道中安全を守護する猿田彦の舞。鼻高の赤い面に赤い鎧の猿田彦命は、両手に扇を持ちながら急テンポの太鼓に合わせて勇壮に舞う。
「“国譲り”と並び、“大蛇退治”は観衆の心をとらえる最も人気の高い演目です」と話すのは、上房神能社 社長の三宅貫也[かんや]さん。神楽を演じるのは神楽太夫と呼ばれる人たちだ。神楽太夫は岡山県の神社庁に登録され、日常は地元で農業や会社員などに従事している。舞や太鼓をはじめ、白蓋に用いる紙飾りの小道具製作など、太夫には一連の技能が求められる。一人前になるには10年かかるそうだ。備中では、そんな神楽太夫が170人を超える。社中は一社につき7人ほどで構成され、神社や個人の依頼で神楽を奉納している。

神楽の奉納に用いられる神楽面。写真は、「大蛇退治」で使用される素戔嗚尊と奇稲田姫の古面。作者や時代は不明だが、貴重な文化財として保存されている。
(写真提供:美星吉備高原神楽民俗伝承館)
上房神能社の若手太夫で、普段は小学校の先生を務める山田さん。「神楽を通じて、人と人とを“つなぐ”。さらに備中神楽という郷土の伝統芸能を、次の世代に“つないでいく”ことです」と話す。神楽教室では、保育園児から中学生までの生徒たちが稽古に励んでいる。

一連の演目を終えた太夫たちは、激しく息を切らしながら汗を拭っている。それほど舞は体力が必要だ。「幼い頃から三宅さんの舞を見て育ち、太夫は地域の憧れでした。自分がそうであったように、この伝統を子どもたちの未来に“つなぐ”ことが重要です」と話すのは、太夫の山田望[のぞみ]さん。6歳から神楽を始めた山田さんは、後進育成のために子どもの神楽教室を開いている。神楽に触れるきっかけになればという思いからだ。備中では定期的に「子供神楽」が催され、子どもたちが鍛錬の成果を披露している。
備中神楽の見どころは、「静」と「動」の舞に尽きる。全ての演目を終えた社殿には紙吹雪が残り、耳の奥には太鼓の残響が残っている。余韻に浸る間もなく、また観たくなる。それが備中神楽の醍醐味にほかならない。
備中神楽は毎年10月〜11月の秋祭りの時期に、各地区の神社で奉納される。
詳しくは高梁市のホームページに掲載される予定。
参考文献/『備中神楽』(山陽新聞サンブックス)、
『中国・四国地方の神楽探訪』(三村泰臣 著/南々社)