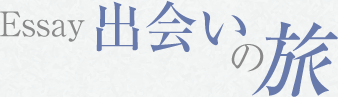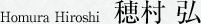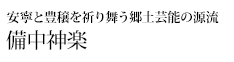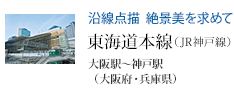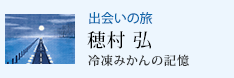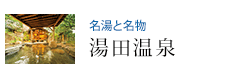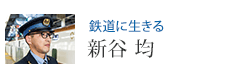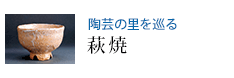歌人、随筆家。1962(昭和37)年、北海道札幌市生まれ。1990年に歌集『シンジケート』でデビュー。『短歌の友人』で伊藤整文学賞、『楽しい一日』で短歌研究賞、『鳥肌が』で講談社エッセイ賞、『水中翼船炎上中』で若山牧水賞を受賞。歌集、エッセイ集以外にも、詩集、対談集、評論集、絵本、翻訳など著書多数。加藤治郎、荻原裕幸とともに1990年代の「ニューウェーブ短歌」運動を推進した、現代短歌を代表する歌人の一人で、現在も第一線で活躍を続けている。
先日、山口県の湯田温泉に行った。旅行ではなく、中原中也賞の授賞式に選考委員として出席するためだ。湯田温泉は詩人中原中也の故郷である。東京駅から新山口駅まで新幹線の中で、お弁当を食べたり、好きな本を読んだり、眠ったり、また本を読んだり、楽しく過ごした。久しぶりの自由時間だ。
無事に授賞式を終えて、その夜は宿泊。翌日、帰りの駅でお弁当を探した。どれにしようか、あれこれと迷いながら、ふと思った。そういえば、この頃、冷凍みかんを見かけないなあ。
若者は知らないと思うけど、旅といえば冷凍みかん、みたいな時代がかつてあったのだ。子どもの頃、親と一緒に出かけると、よく買ってもらった。縦長の袋に四つか五つくらい入っていたと記憶する。まだ売っているらしいけど、あの頃のようにポピュラーな存在ではない。アイスクリームはこんなにバラエティ豊かに並んでいるのに。
冷凍みかんはその名の通り、果物のみかんを凍らせただけのものだから、較べれば最新のアイスクリームのほうがおいしいとは思う。でも、汽車の窓辺で溶けかけていた姿は妙に懐かしい。そう思うのは、自分が昔の人間だからなのか。鮮やかな色が不思議な甘美さとともに甦る。
そういえば、とさらに思い出したのは半世紀近く前のこと。大学一年生だった私は、ワンダーフォーゲル部の合宿で夜汽車に乗っていた。車輌には同じような山男がぎっしり。通路にまで溢れて、登山前夜の興奮のせいか、辺りはがやがやと騒がしかった。列車は雪の原野を突き進んでゆく。
その時、不意に大きな声が響いた。
「うるせえ!」
驚いて振り向くと、そこには一組の男女がいた。コートを羽織った男のほうは見るからにカタギではない。その怒声に辺りは静まりかえった。さすがの山男たちも気を呑まれたように黙ったのだ。それにしても、ピッケルを持った屈強な山男の群れを相手にたいした度胸だ。
さらに驚いたことがある。そんな怒鳴り声にも拘わらず、連れの女は男の肩にぴったりと寄り添って目を閉じたままだったのだ。そこには絶対的な信頼の気配があった。いや、それは錯覚で、実際にはただ疲れきって熟睡していたのかもしれない。わからない。ただ、なんとなく逃避行という言葉が頭に浮かんだ。そんな二人の窓辺には冷凍みかんが置かれていた。
自分も本当の大人になったら、あんな旅をするのかな、と思った。怖いような、憧れるような、不思議な気持ちだった。十代の私には、片道切符の逃避行が究極の旅のように思えたのだ。
あれから半世紀近くが経った。幸か不幸か、自分には今日までそういう旅はなかった。きっとこれからもないだろう。私の旅は、いつも安全で清潔で快適。ポケットには帰りの切符もちゃんと準備されている。
汽車の中では、まったく異なる運命が交錯する。あの夜の二人は、あれからどうなっただろう。もちろん知るすべはない。ただ、もう一度、私も冷凍みかんを食べてみたい気がする。
雪の野原の中に、一条[ひとすぢ]のレールがあつて、そのレールのずつと地平線に見えなくなるあたりの空に、大きなお月様がポツカリと出てゐました。レールの片側には、真ッ黒に火で焦がされた、太い木杭が立ち並んでゐて、レールを慰めてゐるやうなのでありました。
そのレールの上を、今、円筒形の、途方もなく大きい列車が、まるで星に向つて放たれたロケットのやうに、遮二無二走つて行くのでした。
(略)
汽車はゴーツといつて、青い青い雪の原を、何時までも停まらず走り続けました。
『夜汽車の食堂』(中原中也)より