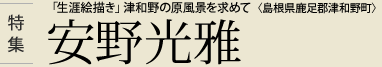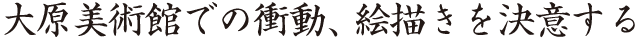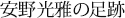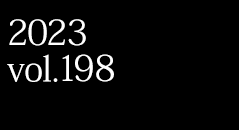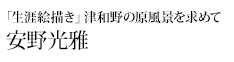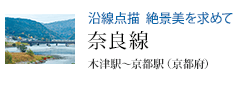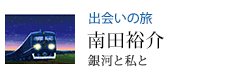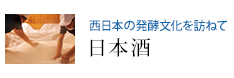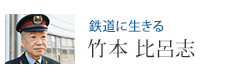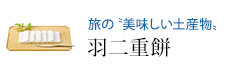「津和野へ帰るとき、わたしは胸をどきどきさせながらトンネルの数をかぞえたものだ。徳佐の駅を出た汽車が六つ目のトンネルを抜けると、そこには間違いなく津和野があった」(『安野光雅の記録  』安野光雅美術館)
』安野光雅美術館)
故郷に戻る際に、山口線の車内での思いを安野自らがそう記している。当時は蒸気機関車の頃で、汽車が小学校の横を通過するとまもなく駅に着いたという。
中国山地の山々に覆われた山峡の町 津和野は、“絵描き”安野光雅の生誕地だ。安野は「画家」よりも、「絵描き」と呼ばれることを好んだ。なんでも描くのが「絵描き」だからだ。安野は宿屋を営む家に生まれ、13歳まで津和野で過ごした。幼少期より絵が大好きで、見るのも描くのも好きだった安野少年。あまり裕福な家庭ではなかったが、母が唯一買ってくれた雑誌『少年倶楽部』は夢中で隅から隅まで読み込み、載っていた絵はすべて覚えたそうだ。そうした雑誌の挿絵や広告など、あらゆる絵を眺めていた。なによりも絵が好きであった安野少年だが、最短の道で絵を志したわけではなかった。兄の出征に伴い、山口県の宇部工業学校に入学する。「手に職をつけよ」という父の方針により、採鉱科に入学した。そんな安野少年に、大きな転機が訪れる。

国道9号線の南谷大橋(西津和野大橋)からの眺望。安野はここからの見晴らしを『津和野』に収めている。手前の木々が高く成長しているが、表紙のスケッチ画と比べても町の風景は変わっていない。

開業100周年でリニューアルした津和野駅舎。島根県産の杉材をふんだんに使用している。

-
1926(大正15)年…
島根県鹿足郡津和野町に生まれる
-
1939(昭和14)年…
津和野を離れ宇部高等小学校に転校
-
1942(昭和17)年…
倉敷の大原美術館で本物の西洋絵画を初めて見る
-
1948(昭和23)年…
徳山市立加見小学校の代用教員となる
-
1950(昭和25)年…
玉川学園の美術教員として請われ上京する
-
1957(昭和32)年…
『現代児童名作全集』の装丁を担当。装丁の仕事が増える
-
1961(昭和36)年…
画家として独立
-
1968(昭和43)年…
初めての絵本『ふしぎなえ』を刊行
-
1979(昭和54)年…
初めてのエッセイ集『空想工房』を刊行
-
1991(平成3)年…
司馬遼太郎『街道をゆく』の挿絵を担当
-
2001(平成13)年…
津和野に安野光雅美術館が開館
-
2020(令和2)年…
晩年まで創作活動をする。12月24日永眠
16歳の頃に、倉敷市の大原美術館に足を運んだ。初めて目にした西洋絵画に感銘を受け、そこでの衝動が自分の一生を決定づけた。展示される画家のフルネームから絵の配置まで暗記し、特にゴッホの絵画の前で、こんな画家になりたいと切望したという。

加見小学校代用教員時代の写真で左が20代前半の安野。採用面接でついピアノが弾けると言ってしまい、その後、猛特訓をしたという。
(写真提供:安野光雅美術館)

安野の代表作『旅の絵本 中部ヨーロッパ編』(1977年福音館書店)。その他、描かれた国は、イタリア、イギリス、アメリカ、スペイン、デンマーク、中国、日本、スイス、オランダなど。異国の街並みや風景、そこで暮らす人々を想像力豊かに描いた作品。

安野の絵本デビュー作『ふしぎなえ』(1968年福音館書店)。安野が42歳のときの作品で、当時は文字のない絵本は斬新で珍しかった。

『ついきのうのこと 續 昔の子どもたち』(2005年日本放送出版協会)の「勉強部屋」。勉強部屋は自宅裏の蔵で、弟や友達とのやりとりを絵日記風に描いている。(提供:安野光雅美術館)
学校を卒業後、安野は九州の炭鉱で働き、後に香川県で兵役生活を送り、復員後には、父の郷里であった山口県徳山市(現周南市)に移る。そこで、看板描きや測量のアルバイトで生計を立て、1947(昭和22)年に徳山市の加見小学校に代用教員として採用される。戦後まもなくのことで、安野は教員資格を持っていなかった。資格を得るために山口師範学校研究科に入り直し、そこで東京美術学校西洋画科出身の図画教師の勝見謙信と出会う。勝見との邂逅[かいこう]は安野が人生の師と仰ぐほどで、多くを学び大きな影響を受けた。
機会が訪れたのは、1950(昭和25)年。東京町田の玉川学園学長から美術教師としての誘いを受け、上京する。しかし、そこでの役割は教師ではなく、百科事典の編集だった。安野は一年で退職するが、ここで学んだ編集ノウハウが後の安野の絵本づくりの糧となる。
その後、三鷹市や武蔵野市の小学校で図工科教員として務めるなど、この頃より画業に力を注ぎはじめ、小金井市に自宅兼アトリエを新築する。1957(昭和32)年に『現代児童名作全集』(講談社)の装丁を任されると、これを機に出版関係の仕事が増えていく。
教師と絵描き。兼業生活をしていた安野は、35歳で独立を決意する。ただ、完全に教師を辞めたわけではなく、週に1度、2時間という制約のもと、私立明星学園で図工を教えていた。このときの生徒に、児童書を手がける福音館書店の松居直[ただし]の子供が通っており、松居は安野と一緒に絵本の構想を始めた。「文章が書けない」という安野に対し、「絵だけでいい」と応じる松居。そんなやりとりから完成したのが、文字のない絵本『ふしぎなえ』だ。
また、絵描きとして順調にキャリアを重ねる安野は、見聞を広めるために度々海外へ赴く。最初は中部ヨーロッパを中心に各地の美術館を巡り、異国の風景を切り取った。その後も世界の各地を訪ねる。その集大成が、40年以上も描き継がれた代表作『旅の絵本』だ。