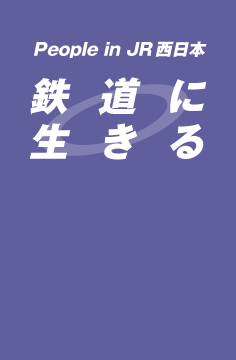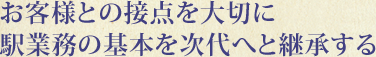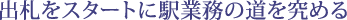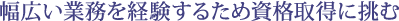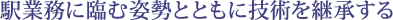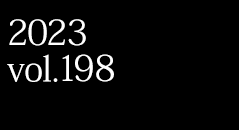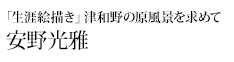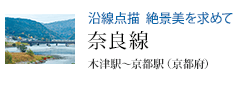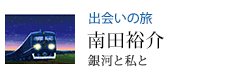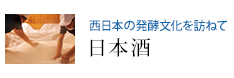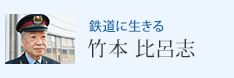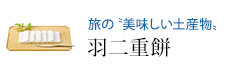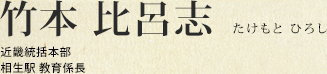

「駅はお客様との出会いがある場所。その接点を大切にしていきたい」。竹本は自ら先頭に立って挨拶を行い、若手にその姿勢を示す。
相生[あいおい]駅は、山陽新幹線と山陽本線、赤穂線の3路線が乗り入れる。通勤・通学の乗降客が行き交う朝の在来線改札口。駅業務のスペシャリスト竹本は、「ご乗車ありがとうございます」「行ってらっしゃいませ」という挨拶に笑顔を添えて、改札での立哨を行う。

コロナ禍では自動きっぷ売り場や精算機など、お客様が手を触れる場所を消毒して回るのが朝一番の習慣に。
駅業務は、「みどりの窓口」でのきっぷの販売をはじめ、改札におけるお客様へのご案内、列車の運行管理など多岐にわたる。旧国鉄時代の1977(昭和52)年に入社した竹本は、当初は東灘操車場で「突放[とっぽう]」と呼ばれる貨車の切り離しや仕分け作業にあたり、続いて神戸駅で小荷物の扱い業務などを数年担当した。その後、1987(昭和62)年のJR西日本発足を契機に、神戸駅「みどりの窓口」で出札※1業務に携わるようになり、以降、駅係員としてのキャリアを積み重ね現在に至る。
「国鉄からJRへ移行するにあたって希望の業務を打診された際、出札の仕事がしたいと願い出ました」と、竹本は当時を振り返る。もともと旅行や鉄道が好きだった竹本は、入社後にはさまざまな路線の列車に乗り、鉄道の旅の魅力に触れてきたそうだ。その経験や知識をきっぷ販売時の接客に活かし、役立つ情報を伝えていきたい。そう思い立ったことが駅業務の道を歩む出発点だという。
※1.乗車券などを販売すること。

きっぷの種類や取り扱いなどを学ぶ「営業制度研修」では、自身の失敗談も交えながら分かりやすい説明を心がける。
安全で快適な輸送サービスの一翼を担う駅業務には、出札や接客サービスを担当する「営業業務」と別に、駅の信号制御や線路の分岐器の切替といった「駅運転業務」がある。この業務に携わるには、「在来線駅長業務」という資格が必要になる。竹本がその資格取得に挑んだのは、1995(平成7)年1月に発生した阪神・淡路大震災の翌月のこと。当時在勤中の新長田駅は駅舎がほぼ全壊の状態で、周辺も火災のために大きな被害を受けていた。自身も避難所から通勤し、駅の片付けや定期券の払い戻し対応などにあたっていた中で、竹本は合格を果たす。同年5月に異動した兵庫駅では、出札業務に駅運転業務が加わり、さらに「国内旅行業務取扱管理者」という国家資格も取得して、添乗などの「旅行業務」の3役をこなしていたそうだ。「どんどんスキルを高め、業務の幅を広げることをめざしていた時期。忙しくても好きな仕事だから楽しんでやっていました」。また、それぞれ異なる業務を経験することは、他の担務との関わりや仕事の流れが理解でき、駅業務全体の連携にも役立てられたと話す。
駅の改札では、近隣の病院や交番の場所などを尋ねられることが多いという。竹本は、新しい駅に赴任すると、非番の日には駅の周辺を歩いたり、バスに乗って病院までの道のりを確認するなど、正確なご案内のための情報収集を心がけてきた。「私たちにとって、お客様からの“ありがとう”のことばが一番の励み。その声を聞くための地道な努力が駅のサービスを支えています」。

研修プログラムの立案をはじめ、研修時に使用する資料づくりにも竹本の知識や経験が活かされている。
現在、竹本は相生駅の教育係長として社員育成の業務を担うとともに、「みどりの窓口」の収入管理を行う当直係長を兼務する。長年培った駅業務の経験や実績を請われ、教育係長となって相生駅に赴任したのは2018(平成30)年6月。1年後には定年を迎えたが、シニア社員※2となった今も接客サービスや安全に業務を遂行するための知識や心がけなど、駅係員としての基本をより多くの社員に伝える。教育の対象は、山陽本線竜野〜上郡駅間と赤穂線の播州赤穂駅までの各駅に所属する若手や中堅社員など約50名。「新入社員はこれからの会社の宝。今、新人教育を担う若手社員の育成にも力を入れています」。入社5年目までの社員を対象としたこの取り組みで、竹本はきっぷを販売する上で必要な営業制度を学ぶプログラムや資料を作成し、それをもとに若手が新人を教えるそうだ。基礎知識をきちんと身につけた上でお客様と接する。竹本の信条は学びの中で受け継がれる。
※2.定年後に再雇用された社員。