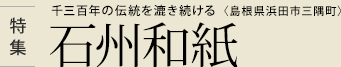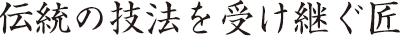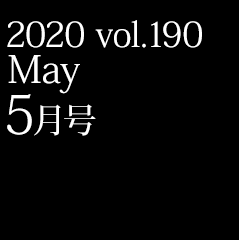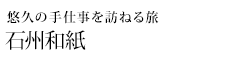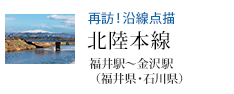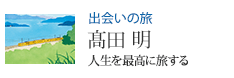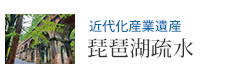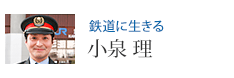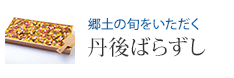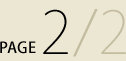
三隅川沿いに、特徴的な赤い石州瓦の家々が点在している。前に海、後ろに山々が迫る町は耕作地に乏しい。代わりに澄んだ水と、紙の原料となる楮などが方々に自生していた。紙漉きの里を育んだ一因は、海と山との間の手狭な地形と紙の素材に恵まれた自然環境であった。江戸時代には浜田藩が石州和紙を管理し、藩の財政を支える貴重な財源となった。
石州和紙会館にあった石州和紙の沿革によると、1889(明治22)年には製造業者は6,377戸もあった。それが1948(昭和23)年には279戸になり、現在は4軒の事業所が地元産の楮にこだわり、古来から伝わる「竹簀[たけす]による流し漉き」の技法で、和紙の里の伝統を守っている。古くから石州和紙が漉かれていたのは三隅町古市場地区。そこの「本石州紙 西田和紙工房」を訪ねた。
西田誠吉[せいぎ]さんは7代目で、京都で手描き友禅の絵師をしていたが、27才で郷里に戻り家業を継いだ。「子どもの頃は、近所のあちこちでチャポン、チャポンという紙を漉く音がしたものです。今や4軒とは寂しいですが、1300年の伝統を絶やすわけにいきません」と話す。西田さんがこだわるのは、材料から一貫した手づくりの「自給自足の和紙」だ。

右側手前の赤い石州瓦の屋根の家が西田和紙工房。手前は刈り取った後の楮の栽培地。西田さんは原料である楮を自家栽培している。

西田和紙工房の7代目である西田さん。「作り手と使い手の顔が互いに分かる関係で和紙を作りたい」と言う。主に文化財の修復などの表具や神楽用、大英博物館やボストン博物館など海外からの依頼も少なくない。

①石州和紙の原料、左からトロロアオイ、楮、三椏、雁皮。それぞれに味わいが異なり、最も上質の紙は雁皮紙。三椏紙は繊細で弾力性があり、楮は庶民の紙で強靭。

②黒皮そぞりの工程では水に浸し柔らかくした表皮を一枚一枚包丁で丁寧に削る。

③そぞった白皮を地下水で入念に水洗いし、不純物を取り除く。

④煮熟(しゃじゅく)。ソーダ灰を入れて煮釜で煮る。その後、塵取り、叩解(こうかい)などの工程を経て漉きの作業に入る。

⑤漉き上げた和紙は天日干しした後、一枚一枚、厚さやムラ、傷などを確認して選別する。

⑥京都二条城の襖の裏打ちに用いられた石州半紙。何層にも重ねて裏打ちされる。

⑦石見神楽のヤマタノオロチの胴を作るのに用いられる石州和紙。オロチだけで年に150頭も作られるという。
丹念に自家栽培した楮を用い、素直に誠実に紙と向き合う。「使い手が求める和紙職人に徹したい」と西田さん。その工程は実に多く、大変な手間を要する。楮やトロロアオイ(紙料を均等分散し、繊維を繋ぎ止める補助材料)を栽培し、刈り取り、裁断して蒸す。表皮を剥いで、黒皮を乾燥させ、水に浸した後、包丁で丁寧に表皮を削り、不純物を洗い流す。煮窯で2度煮る。塵を取り、繊維を叩いて砕く。漉き舟に水と紙料、そしてトロロアオイを混ぜて均等に攪拌[かくはん]し、ようやく紙漉きの作業となる。石州和紙は竹簀による流し漉きで、縦の前後の動作だけで行うのが特徴だ。西田さんは言う。「紙漉きには人それぞれの調子とリズムがあって、個性が出ます。百枚漉いて百枚とも同じ厚さ、薄さに漉くことができて一人前です。でも、そこからが難しい。使う人の注文に応じて紙を漉くのは一回一回が真剣勝負です」。
西田さんの漉く石州半紙は、国宝の屏風絵や襖絵、障子のほか文化財の修復に欠かせない。神楽面やヤマタノオロチの胴のほか、この地の神事や祝事にも需要が多く、石州和紙は風土に育まれてきた。民藝運動を提唱した柳宗悦[やなぎむねよし]は『和紙の教へ』という随筆で石州半紙に触れている。「誠に凛としたところがあって(中略)思わず触れる快さを抑えることができない。(中略)それ自身で既に美しさに溢れる」。そして手漉き和紙に「日本の姿が見える」と記す。
西田さんが漉いた和紙を眺めて、柳の言葉を実感した。それ自体で和紙は美しく、麗しい。そんな西田さんには、3人の若い後継者がいる。一人は息子さんの勝さん。生まれ育ちが地元で、神楽も舞うという前原亜沙季さんは弟子入りして5年。そしてこの春、神奈川県出身の菊地悠さんが工房の職人に加わった。近所のご婦人たちを含めて大所帯だ。
三隅町にはほかに伝統の担い手として期待される3人の若い研修生がいる。いずれも県外の若者だ。西田さんは「和紙で生計を立てるのは決して楽ではないけど、石州和紙の伝統を繋いでくれたらと願っています。目標は100%、自給自足の石州和紙です」と語る。手漉き和紙の里はゆっくりと時が過ぎていく。この地の穏やかな風景に溶け込んで、1300年前と同じ紙漉く音が心地よく響いていた。

西田和紙工房の8代目の西田勝さん。人気漫画家とタイアップし、石州和紙を用いたプレミアムな版画など新たな企画を手掛ける。「石州和紙の可能性をいろいろ試したい」。

三隅町出身の前原さんは紙を漉いて5年。男性と変わりなく力仕事もこなす。「三隅が誇る伝統を守りたい。でも、慣れれば慣れるほど紙漉きは難しいです」。

菊地さんは、京都の工芸学校で手漉き和紙を学び、浜田市が支援する研修生を卒業。「私の漉く和紙が欲しいといわれるような紙職人になりたいです」。