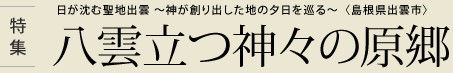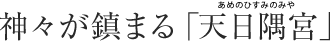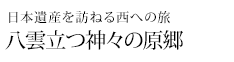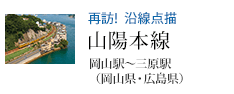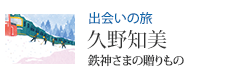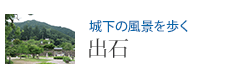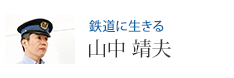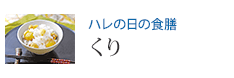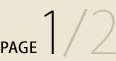
出雲大社の西に奉納山[ほうのうざん]という小山がある。展望台に登ると眼下に白く輝く砂浜が弓なりに続いている。薗[その]の長浜[ながはま](約13.5km)。快晴なら、はるか先に姿の良い三瓶山[さんべさん]が見える。この長々とした砂浜は出雲の国生みに関わる伝承地、『出雲国風土記』冒頭の「国引き神話」の舞台である。
明治の文豪ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)は「出雲は、わけても神々の国」と書き残している。『古事記』に誘われて日本を訪れ、英語教師として1年3カ月を松江に過ごしたハーンは、短い滞在ながら、神々が鎮まる出雲という土地に威厳に満ちた気配、名状しがたい神秘さに感応したのだろう。

手前の筆投島(ふでなげじま)には、平安初期の宮廷絵師が朝夕刻々と美しさが変化する様を描ききれずに絵筆を投げたという伝承が残る。その左奥に見えるつぶて岩は、国譲り神話で建御雷之男神(たけみかづちのおのかみ)と建御名方神(たけみなかたのかみ)が、力比べで稲佐の浜から投げあった岩が落ちて積み重なった岩だという。
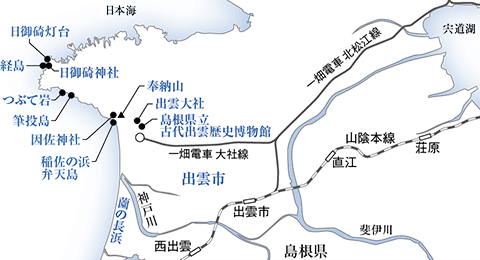
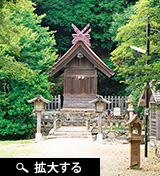
稲佐の浜から少し内陸に入ったところに鎮座する因佐神社には、大国主大神に国譲りを迫った建御雷之男神が祀られている。
『古事記』神代巻の3分の1は出雲神話。『日本書紀』や『出雲国風土記』にも記された神話の伝承地が各所に残っている。旧暦10月を出雲では神在月[かみありづき]と言う。年に一度、全国から神々が集い合議するという「神議[かみはか]り」がなされる古事に由来する。『出雲国風土記』に載る神社は五百余、現在、大小七百社を超える出雲は、なお神々の国である。

島根県立古代出雲歴史博物館に展示されている古代出雲大社の10分の1の復元模型。千木までの高さが約48.4m。国造家に伝わる古図「金輪御造営差図(かなわごぞうえいさしず)」では、神殿に昇る階段は長さ「引橋長一町」(約109m)と記され、伝説の空中神殿の現実性が高まった。

2000(平成12)年に出雲大社の境内から発見された巨大な字豆柱(うづばしら)。直径約1.3mの柱を鉄輪で3本1組に束ねた巨大な柱を3本ずつ3列に並べて高床式の神殿を支えた。
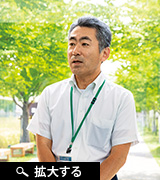
「約50mの高さはビルなら16階。まさに空中神殿です」。古代出雲歴史博物館の浅沼さんは話す。
しかも出雲では神話はときに現実と重なる。素盞嗚尊[すさのおのみこと]の八岐大蛇[やまたのおろち]退治の神話も、単なる冒険譚でなく、そこに古代出雲の歴史が見え隠れする。神話が歴史を彷彿とさせるのが出雲という土地の不思議さで、国引き神話にもそれは当てはまる。
神代の出雲は小さい国だった。出雲の祖神 八束水臣津野命[やつかみずおみつぬのみこと]は、栲衾志羅紀[たくぶすましらき]の三埼[みさき](朝鮮半島)や高志[こし]の都都[つつ](能登の珠洲の岬)に綱をかけ「国来[くにこ]、国来」と手繰り寄せてできたのが島根半島。東側の綱が弓ヶ浜で綱をかけた杭が大山。西側の綱が薗の長浜で三瓶山を杭に綱を手繰り、国を引き寄せたと『出雲国風土記』は語っている。
この神話に、古代出雲の勢力や文化圏を重ねて考えられないだろうか。薗の長浜の北端の稲佐の浜も出雲の歴史の重要な舞台で、ちょうど弁天島辺りが、「記紀」に記される「国譲り神話」の伝承地。神在月に全国から八百万の神々がやって来るのもこの稲佐の浜だ。
国譲り神話は、『古事記』では葦原中国[あしはらのなかつくに]を治めていた素盞嗚尊から数えて6代目となる大国主大神が、天津神[あまつかみ](天照大御神)から「国を譲りなさい」と迫られて国を譲る話で、それに従うかわりに壮大な神殿の造営を求めた。そうして創建されたのが出雲大社で、ご祭神は大国主大神、祭主は天照大御神の子 天穂日命[あめのほひのみこと]。現在の国造[こくそう]家の先祖で現当主は84代目にあたる。
まさに現代に生きる神話だ。その出雲大社で2000(平成12)年に大発見があった。直径1.3mの柱を鉄輪で3本1組に束ねたと考えられる巨大な心柱の柱根が発掘された。伝説だった巨大な空中神殿が実在したことが証明されたのである。島根県立古代出雲歴史博物館には古い差図[さしず]をもとに復元された古代神殿の10分の1の模型が展示してある。
説明には、千木[ちぎ](本殿屋根の先端にある交差した2本の木)までの高さは約48m(現在の御本殿は約24m)。神殿に続く階段は約109mとある。模型から想像するだけでも圧倒的な威容で、古代人にはまさに天空に届く、神が創り出した神殿に疑いなかったに違いない。学芸部長の浅沼政誌さんはさらに、「上古の神殿は96mの高層だった説もあります」と話す。
そして出雲大社は『日本書記』には「天日隅宮[あめのひすみのみや]」と記され、出雲は古代から日が沈む聖地として人々の尊崇を集めるところであった。

出雲では旧暦10月は、全国から神々が集まる「神在月」。例年稲佐の浜では旧暦10月10日の夕刻から夜に全国から参集する八百万の神々をお迎えする「神迎神事」が執り行われる。お迎え後に神々は「神議り」という会議を行う。