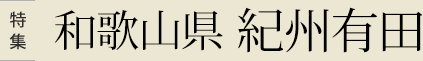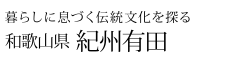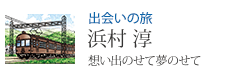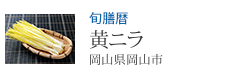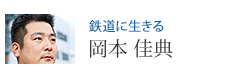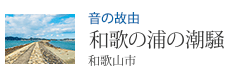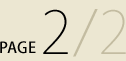

今日の寿司の原型といわれる鯖のなれずし。有田の家庭の味だ。
食材豊富な有田にはさまざまな郷土食があるが、中でも誰もが一番に挙げるのが「鯖のなれずし」。鯖を粗塩につけて酢飯でなく塩で練った白飯を、「アセ」という近辺に自生する笹に似た植物の葉に包み、樽に漬けて乳酸発酵させる。800年以上の歴史があり、祭りや行事に欠かせない有田伝統の味だ。
こうした発酵食は全国的に見られるが、有田には日本人の味覚の原点がある。訪ねた先は湯浅町。江戸時代の風情を今に残す町の北詰めには、荷物を船積みする小舟を舫[もや]った大仙堀[だいせんぼり]があり、白壁の土蔵が水面に影を映す。軒の低い連子格[れんじごうし]子の商家や町家、小路が迷路のように入り組み、家々が密集する界隈は重要伝統的建造物群保存地区になっている。

湯浅名物の金山寺味噌。

白壁が美しい醤油蔵。建物は創業の江戸時代のままで今も現役。蔵裏の大仙堀は醤油を船で積み出すために開削した。
北町通りに老舗の暖簾をさげているのは金山寺味噌の「太田[おおた]久助吟製[きゅうすけぎんせい]」商店。当主の太田庄輔さんは伝来の製法のまま金山寺味噌を造り続けている。金山寺味噌は紀州藩が長く門外不出にした有田湯浅の名産。炒った大豆と裸麦に米麹と塩を加え、茄子、瓜、シソなどを刻んで一緒に発酵、熟成させた味噌だ。
味は少し甘くまろやか。調味料の味噌とは違ってご飯と一緒に食べたり、酒の肴となるおかず味噌だ。伝来したのは700年以上前で、隣町の由良の興国寺を開いた禅僧、覚心が中国から製法を持ち帰った後に、水質が良く、気候風土が発酵、醸造に適していたこの湯浅の地で造られるようになったという。
金山寺味噌を仕込む際、自然と桶に溜まった醤[ひしお]が醤油の原点である。大豆など穀類を発酵させたものが醤油で、複雑な旨味がある。この醤油の誕生がその後の日本人の食文化を大きく変え、日本の食卓に欠かせないものとなった。今や世界中に輸出される日本の味覚の代表だ。
そもそもの醤油は「たまり醤油」で甘く濃厚な味。江戸時代に有田から大消費地の関東に移住し、生産量を多くするために製法を改良して造られたものが「濃い口醤油」だ。そして「薄口醤油」が生まれるのはさらに後。関西の薄口醤油の文化は、素材の彩りや昆布出汁[だし]の風味を生かす京料理の影響が大きいようだが、和歌山では古くから濃い口醤油の文化だという。
そんな醤油の発祥の地、湯浅の全盛期は江戸時代。「文化文政期に湯浅の醤油醸造家は92軒を数えましたが、今は味噌醤油合わせて7軒です」。そう話すのは1841(天保12)年創業の「角長[かどちょう]」6代目当主の加納誠さんだ。加納さんの案内で醤油蔵を覗くと、中は薄暗く、天井や太い梁、壁は長い年月を経てくすんでいる。170年以上の歴史がある仕込み蔵だそうで、角長では「湯浅たまり」という昔のままの伝統の製法で、職人の経験を頼りに手間を惜しまず、吉野杉の木桶で醤油を誠実に仕込み、育む。

角長6代目の加納さん。家訓は「一業(いちぎょう)」、わき目もふらず醤油造りに精進せよ、という意味だ。

170年以上を経た仕込み蔵。天井や梁には「蔵付き酵母」が住み着き醤油の醸造を促す。
加納さんがこだわるのは、受け継いだ「昔ながら」の流儀で「本物の醤油」を造り続けることだ。使用する大豆、小麦は全て国産。「少量生産だからできることで、材料がまっとうであればあとは自然の力に任せ、微生物の働きを愛情深く見守ってやればいい醤油はできます。醤油発祥の誇りに恥じない、自分が納得できる醤油を造りたい」と、6代目はそう話す。

角長の醤油。たまり醤油で魚の刺身を口にすると、旨味の違いは歴然。
7代目の恒儀さんも一徹だ。「170年以上続く醤油造りは絶対に絶やしてはいけないと思っています。だから造り方も絶対に変えません」。世界的に和食が注目される中で、角長の醤油は外国人シェフからも注目を集めている。「温暖で雨が多くて多湿。それに水の良い湯浅の風土は微生物の発酵を促し、醤油造りに最適の土地なんです」。醤油発祥の伝統を守り続ける6代目はそう話した。
古い家々が並ぶ北町の通りを歩くと、馨[かぐわ]しい醤油の香りが漂っている。それはこの町の歴史と伝統を伝え教える匂いである。有田の馥郁[ふくいく]とした風土が今も豊かな食文化を育んでいる。