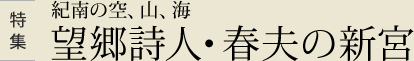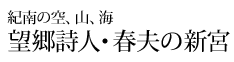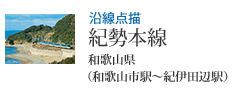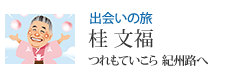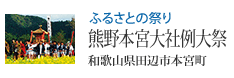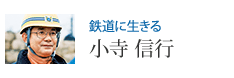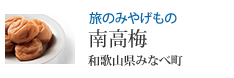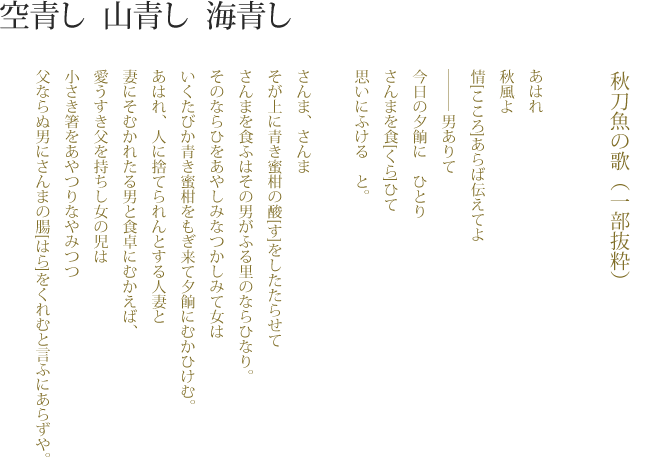
熊野灘の海は遮るものがない。海は空と溶けあって無辺に広がり、あふれる光の種子をまいたかのように海原はまばゆく輝いている。王子ケ浜の砂利石の渚に波が打ち寄せる。空は抜けるように青い。
ふと、口ずさんだのが佐藤春夫の『望郷五月歌[ごがつか]』の詩の一節だ。「空青し山青し海青し…」。熊野灘に臨む新宮は、詩人が巧みに切り取ったように、海と山と川の自然が交じり合ったところである。
町の南西にそびえ立つ岩山の上に神倉神社がある。ここに鎮座する巨大なゴトビキ岩に神が最初に降臨した。そこから後に新しく宮を遷したのが熊野速玉大社であり、新宮とはその伝承に由来している。この熊野速玉大社境内の一角に、東京にあった佐藤春夫の旧邸を移築、再現した「佐藤春夫記念館」がある。いわば望郷詩人の帰郷だ。
1892(明治25)年、佐藤春夫は新宮に3人兄弟の長男として生まれた。代々医者の家柄で、名前は父親が詠んだ「よく笑へどちら向いても春の山」から名付けられた。病院を開業し俳句を嗜む父の豊太郎のもと、進歩的で自由な家風の中で春夫は育つ。
また、鉄道のない時代、新宮は地勢的には隔離された地だったが、熊野川上流の山々から切り出された木材の集散地として大いに栄えた。「新宮は材木の取り引きで、東京と海路でつながっていたため、その時代の新しい物や情報が直接入ってくる町でした」と、佐藤春夫記念館の辻本雄一館長は、新宮の町が春夫に与えた影響を指摘する。春夫は、新しいものを見聞きするなかで、西洋の近代思想に共鳴し、進取と反骨の精神を養いながら、文学に目覚めていった。新宮中学校(現・新宮高校)卒業後は、慶応義塾大学予科に入学し永井荷風に師事したものの、文学をするのに大学は無用と退学した。


写真は1921(大正10)年頃、春夫29歳前後で、この年には代表作となる詩集『殉情詩集』を刊行し、その詩才は高く評価された。文壇では芥川龍之介と良きライバルで、谷崎潤一郎ほか多くの文人と交流があった。彼の人柄が慕われ、門弟は3,000人といわれる。
(佐藤春夫記念館蔵)

ゴトビキ岩をご神体として祀る神倉山を見上げる。春夫が通った新宮中学校はゴトビキ岩を見上げる場所にある。

『殉情詩集』初版本
(佐藤春夫記念館蔵)
文壇へのデビューは、谷崎潤一郎らの勧めで1919(大正8)年に刊行した小説『田園の憂鬱』。自身を思わせる芸術家「彼」が都会を離れて、東京郊外の田舎に一人の女性と犬と暮らす平凡な日常。物語性はなく、芸術家の倦怠と懊悩[おうのう]、憂鬱の日常が描かれた不思議な作品だが、若い人間が陥る生きることへの普遍的な憂鬱は、極めて新鮮で今日にも通じるものがある。
やがて春夫は気鋭の作家となった。太宰治、井伏鱒二、遠藤周作らは春夫を師としたが、本質的に春夫は詩人といわれ、有名な『秋刀魚の歌』はその代表作である。全41行からなるこの詩は、さんまの味覚ではなく、春夫の不徳の狂おしい恋心を切々と綴っているのだった。人妻への恋に憔悴し神経症を病んだ春夫は、療養のために新宮に一時帰郷する。この詩はその時に詠まれた。熊野のさんまがその日の夕餉[ゆうげ]だったのだろうか。
『秋刀魚の歌』だけではなく、春夫はさまざまな作品に故郷を描いている。出世作『田園の憂鬱』の主人公の故郷も「ずっと南方の或る半島の突端に生まれた彼」と書き、「荒い海と嶮しい山とが激しく咬み合って」「小市街の傍を、大きな急流の川が、その上に筏[いかだ]を長々と浮かべさせて…」と描く。
訪ねた熊野川にはもう筏の姿は見られないが、それは春夫が育った新宮の今も変わらない風景である。空青し山青し海青し。

新宮市街をU字形に大きく蛇行して太平洋に注ぐ熊野川。

「佐藤春夫記念館」2階のサンルーム。建築にも興味があった春夫は窓枠や手すりの金具などを自らデザインした。階段を上がった窓の下で座って執筆もした。