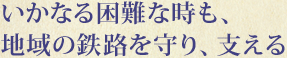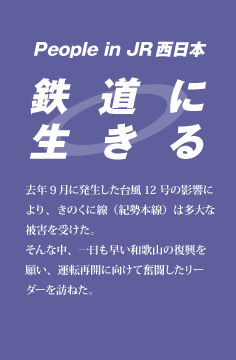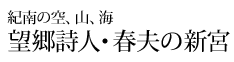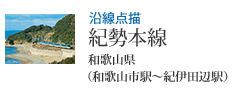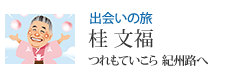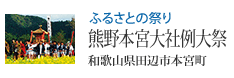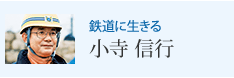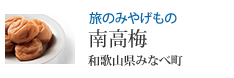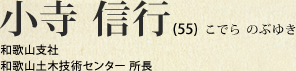

本年1月から始まった新家川橋りょう改修工事の現場での打ち合わせ。「現場をよく見ることが責任者の務め」と小寺。
記録的な豪雨により紀伊半島を中心に、大きな爪痕を残した昨年9月の台風12号。和歌山支社管内のきのくに線では、駅や車両、変電所の冠水、さらには護岸の流失や盛土の崩壊など、甚大な被害が発生した。その直後より、和歌山土木技術センターの所長である小寺のもとには、各所から続々と被害の状況報告が届いた。
「きのくに線の全域で想像を絶することが起きている、それが最初の印象です。同時に一刻も早く現場を確認したい、そんな気持ちでした」。管内には約800の橋りょう、100を超えるトンネルがあり、切土、盛土など250キロメートル以上に及ぶ土工設備がある。普段の検査業務でも、「石橋を渡る時は徹底的に叩く」のが信条という小寺。非常事態であるこの時も所員とともに真っ先に現場へと向かい、管轄する設備を、微に入り細にわたり、徹底的に調べ上げた。
「管内にあるすべての橋りょうのチェックを行いましたが、幸いなことに大半の構造物が無事と分かりました。しかし、那智川の橋りょうは、橋脚ごと流されて被害がひどく、ここは復旧、運転再開まで相当な時間がかかると直感しました。同時に、被害が大きい現場を目の当たりにし、これはもう絶対に自分たちがやるしかないと、腹が決まりました」。

各地で行われている工事の進捗について、各部署を交えてミーティング。
日ごろの確かな連携が鉄道の安全輸送を支える。
1980(昭和55)年の入社以来、30年以上にわたり保線と土木の技士として歩んできた小寺。わずかでも疑わしい箇所があれば「絶対に車両を通せない」、そう肝に銘じているからこそ、いかなる時でも現場での判断は慎重にならざるを得ない。
小寺は現場を預かる長として、構造物の状態を細部にわたってつぶさに観察し、安全性に関する判断をくだしていった。「安全を担保することが、検査業務の最も重要なポイントです。確実に安全か否かの判断をくだすために、鉄道技術の研究開発・調査機関である公益財団法人鉄道総合技術研究所(JR総研)や、社内の研究機関である構造技術室とも連携を密に、何度も一緒に現場に赴いて納得できるまで調査を重ねました」。
また、早期の復旧には地元の方々の理解と協力が欠かせない。「今回は、JRグループの総力の結集だけでなく、地域の皆様の工事への理解、『ご苦労様』という温かい応援があったからこそ、早期の全線運転再開を実現することができました」。
異常時での対応力は、日ごろの訓練と過去に培った経験から生まれる。小寺には1995(平成7)年の阪神・淡路大震災の時、構造物の復旧に携わった経験があった。阪神・淡路大震災では、道路と通信が寸断され、救援物資も工事に必要な機材も届かなかった。しかし今回は、国道42号線が無事であり、かつ携帯電話やインターネットが普及していたことで関係各所と常に情報共有ができたことも、早期復旧への後押しとなったという。
こうした要因が奏功して、当初2012(平成24)年春頃としていた全線開通の予想を大きく短縮し、災害発生から3カ月後の12月3日に復旧を果たすことができた。

「地域の皆さんの期待に応えたい」という思いが3カ月という短期間の運転再開につながった。
「今回の経験を通じて、若手社員は“人を知った”と思います。自分が持っていない知識や情報は、他の人から借りる。多くの仲間と支えあうことで、新たな知恵が生まれ、大きな力となり苦難を乗り越えられる。それを知ったことが大きいと思います」。
仲間が大切。特に異常時は作業優先となりがちだからこそ、若手には“同じ現場にいる人はみんな家族と思うように”と指導し、安全で確実な作業を徹底した。「もしも自分の家族が危険にさらされたら、危ないと注意するはずです。また家族なら注意してくれたことに感謝もするでしょう。現場でもこの意識が必要なのです」。
小寺が担当した中でも、最も被害が甚大だった那智川橋りょう。この現場だけでも毎日50人以上のスタッフが70日も通ったという。それぞれの現場でケガ人を一人も出すことなく無事故で工事を完遂することができたのは、1日も早い復旧を願い日夜工事に勤しんだ多くの人々が心をひとつにして挑んだからにほかならない。災害発生の9月から復旧を果たした12月まで、「季節の移り変わりを感じることさえなかった」という小寺。全線復旧を翌日に控えた12月2日、安全を確認する試運転のために那智川橋りょうをゆっくりと進むDD51形機関車の先には、昼夜を分かたず苦難を共にした多くの仲間たちの誇らしい笑顔があった。

台風12号により大きな被害を受けた那智川橋りょう。橋桁2連と橋脚1基が流失した。