|
かすんだ水平線の先に、うっすらと佐渡の島影が見える。日本海を隔てて向き合う新潟県出雲崎町は、江戸時代には幕府直轄の天領として佐渡金山で採掘した金の陸揚げや、北前船の寄港地として栄えた。良寛は、代々この出雲崎の町名主、現在でいうと町長と神主を兼務する橘屋山本家の長男として、1758(宝暦8)年に生まれた。

良寛とは出家後の法号で、本名は山本栄蔵。幼少のころより、栄蔵は町名主の家督を継ぐ身として、読み書きそろばんを習い、寝食を忘れて読書に夢中になる聡明な少年だったという。

13歳で、家から離れて江戸帰りの儒学者の学問塾に通って和漢の教養を深めた。しかし周囲は、そんな利発な栄蔵を「名主の昼行灯息子(役立たず)」とからかった。もともと、無口で人見知りの激しい内気な性格で、人とのつき合いが苦手な栄蔵の姿は、周囲には愚鈍に映ったことだろう。

18歳で、栄蔵は名主見習いになるが、人間関係のいざこざに辟易し、一カ月半で家督を捨てて隣町にある光照寺 に飛び込んで出家してしまう。そして出家先の光照寺で、栄蔵は生涯の師と出会うことになる。備中国玉島の曹洞宗・円通寺の住職、大忍国仙[だいにんこくせん]和尚だ。こうして良寛は故郷を後に、備中玉島へと旅立った。

玉島は倉敷市の西、瀬戸内海に臨む温暖な港町である。良寛が移ってきた頃は備中松山藩の飛び地で、港には備中の各地からの物資が集散し豪商の蔵が並ぶ、活力に満ちた豊かな土地だった。

和尚とともに向かった円通寺は、道元を宗祖とする曹洞宗の古刹で、禅の修行道場である。玉島港から白華山に至る坂道を登って行くと、円通寺に辿り着く。巨岩と竹林の池を過ぎると、正面に座禅堂の白雲閣、右手に本堂、その奥には高方丈[たかほうじょう](住職の居室)がある。正面の左手には衆僧とともに良寛が寝起きした衆寮がある。現在は良寛堂と呼ばれ、当時の佇まいを今に残している。良寛はこの円通寺で12年間の修行に明け暮れた。
|
|
 |
|
 |
|
| 出雲崎の良寛の生家である橘屋山本家の屋敷跡に建てられた良寛堂。 |
|
 |
|
| 備中玉島の白華山。瀬戸内の風光明媚なこの山の中腹に円通寺がある。 |
|
 |
|
| 備中玉島の曹洞宗円通寺。手前の萱葺き屋根の堂が良寛堂。良寛時代の建物として唯一残っている。 |
|
|
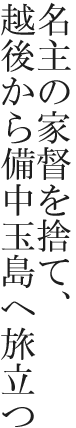 |
|
 |
|

出雲崎尼瀬地区に建つ、海を見つめる栄蔵の像。 |
|
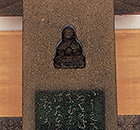
良寛堂には、良寛が昼寝の枕にしたという石地蔵が、良寛自筆の歌とともに安置されている。 |
|

光照寺に建つ「良寛剃髪の寺」の石碑。 |
| |
|