 |
 |
|
初秋に白い花を咲かせ、晩秋に実を結ぶ秋そば。
そばは、夏と秋を収穫時期とし、呼び名が分けられる。
俳句においては、秋に収穫されるそばが季題とされ、
多くの句に詠まれてきた。
俳聖芭蕉に師事し、蕉門の俳人としては
異彩を放つ存在であった広瀬惟然[いぜん]の句とともに
そばと日本人との関わりをたどってみた。
|
 |
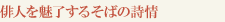 |
白く可憐な花が咲き競うそば畑の情景は、日本の秋を代表する風物詩である。収穫されたその実を挽いて打つそばは、「新蕎麦」や「走り蕎麦」といった季語にもあらわれる。冒頭の句は、気温の低下とともに赤みを帯びるそばの茎を、深まりゆく季節の情趣として詠んでいる。

作者広瀬惟然は、芭蕉門下の中でも特に異色に富む俳人とされる。1648(慶安元)年頃、美濃国関村(現岐阜県関市)に生まれ、本名は源之丞[げんのじょう]といい、生家は酒造業を営むたいへんな資産家であった。父久兵衛は風流人として知られ、惟然の誹諧への志は父によって宿されたと考えられている。蕉門入りは1688(元禄元)年。師事した年月は数年という短さであったが、師弟関係はたいそう親密であった。1694(元禄7)年に芭蕉が病没した後も心酔は変わることなく、芭蕉の霊を弔うための像を百体彫刻、さらに芭蕉の発句を七五調の和讃に仕立て、瓢箪を打ち鳴らし踊るという「風羅[ふうら]念仏」を唱えて諸国を行脚したという。

句は、芭蕉が亡くなる1カ月前、郷里滞在中の芭蕉を訪ねたときのもので、伊賀上野はそばの花の盛りであった。肌寒さを覚える頃の季節感を視覚的に表現した佳句として、俳諧撰集『続猿蓑』(1698年刊)に入集している。
|
 |
 |
|
| 中央には瓢箪を叩き風羅念仏を唱えて踊る惟然が描かれている。(『近世畸人伝』大阪市立中央図書館蔵) |
|
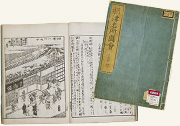 |
|
| そば切りが名物であった大坂砂場(現大阪市西区新町)の「いづみや」のようす。「砂場そば」とよばれ、たいそうな賑わいをみせていたという。(『摂津名所図会』(179698年)大阪市立中央図書館蔵)
|
|
|
|
 |
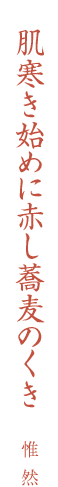 |
 |
 |
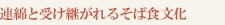 |
そばは、古くから食べられてきた穀物のひとつである。原産地については諸説あるが、中国南部の雲南省地域と考えられている。日本に残る最も古いそば栽培の記録としては、『続日本紀』にある722(養老6)年の詔[みことのり]で、将来の飢饉に備えてそばを植えるよう奨励する記述がみられる。そばは、普通種と韃靼[だったん]種とに大別され、一般に食べられているのは普通種である。このそばは褐色の実で、甘みがあることから「甘ソバ」とも呼ばれている。一方、韃靼種のそばは別名「苦ソバ」ともいわれ、さわやかな苦みが特徴。江戸時代の百科事典『和漢三才図会』(1712年)においても、「苦蕎麦」の名で紹介されている。

現在のように、そば粉を練って麺棒でのばし、包丁で細く切ったそば切りとして食するのは江戸時代からとされる。それ以前は、「そばがき」や「そば団子」といった菓子のような食べ方が主流であった。江戸時代中期の『摂津名所図会』には、大坂砂場の「いづみや」に、そば切りを求めて遠来の客が毎日数百人は訪れていたという繁昌ぶりが描かれている。この頃には、今と同様に麺を茹であげていたが、小麦粉などつなぎが使用される前はセイロで蒸されていた。もりそばがセイロで出されるのは、当時の名残である。
|
 |
 |
 |
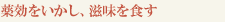 |
良質のたんぱく質を豊富に含むそばは、栄養バランスの整った食といわれている。近年では、ポリフェノールの一種であるルチンを多く含んでいることから、現代人の生活習慣病予防に対する期待が高い。特に、韃靼種のルチン含有量は普通種の100倍ともいわれ、健康への一層の効果が注目されている。

薬効はもちろんのこと、専門の職人の技から生まれる打ちたて、切りたて、茹がきたての味わいこそ粋なそばの楽しみ方である。古都・京都の玄関口、JR京都駅のホテル内にある「日本料理浮橋」では、韃靼そばを旬の食材ととも会席仕立てで提供するというめずらしい「蕎麦会席」を楽しむことができる。韃靼そばは、中国では古くから漢方薬としても用いられてきたいわば薬膳素材。口に入れるとほのかに感じる苦み、コシの強さが韃靼そばの持ち味。さらに、豊富なルチンが溶け出すことから、そば湯まで味わうことこそ、そばの理想的な食し方なのである。
|
 |
 |
|
| 打ちたての韃靼そばは、やや緑がかった色合いが特徴。 |
|
|
 |
 |
|
|
 |