|
 |
 |
天保年間(1830〜44年)、大坂に集まった米は年に約150万石、約400万俵にも達した。大川や堂島川、土佐堀川の川沿いには、邸宅を兼ねた諸大名の蔵屋敷が100を超え、幕末期に至っては135を数えたという。川には荷を満載した無数の舟がひしめき、通りや筋は人や荷車がせわしく往来していた風景はさぞ活気に溢れ、壮観であっただろう。

蔵屋敷や豪商の屋敷は、大坂の物見遊山の名所でもあったという。鴻池、住友、天王寺屋、三井越後屋…。その風景は「天下の台所」と謳われたこの街のまさに象徴であった。幕末に日本を訪れたイギリス人外交官はその賑わいを「大坂はパリに相当する」とした上で、「そこは奢侈と富裕の地である」と記している。

ドイツ人医師のシーボルトも、江戸の退廃的な爛熟の文化に対し、大坂の闊達で庶民的な文化を高く評価している。町人の町とは、人口比率上のことだけではなく、たとえば「なにわ八百八橋」にも町人の気風がよく表れている。実際の橋の数は200ほどだが、そのほとんどが「町橋」と呼ばれる町人が架けた橋で、淀屋橋は豪商の淀屋が架けた。対して、江戸の橋はすべてが幕府の「公儀橋」である。町橋は、架け替えや修理も各町が費用を負担し、通行料もとらなかった。財力あればこそだが、それは大坂町人の心意気でもあったに違いない。

そんな気風が「実学」も育んだ。実学とは、理屈よりも実証性、合理性、現実性を尊び、空理空論の対極にある大坂の伝統的精神である。緒方洪庵の私塾「適塾」は実学の代表で、大村益次郎や福沢諭吉など、日本の近代化を牽引する逸材を多く輩出した。洪庵は種痘やコレラ治療に業績を残した医師だが、志ある者には身分を問わず平等に医学や蘭学を指導した。現在の大阪大学医学部の母体になった適塾は、淀屋橋近くの瓦町に当時のままに保存されている。

「懐徳堂」も5人の町人が開いた私塾だ。後に官許の学問所になるが、数多くの町人学者がここから巣立っている。山片蟠桃[ばんとう]もその一人で、大名貸の大店の番頭であった蟠桃は、徹底した合理主義を貫き百科全書的な大著「夢ノ代」を著わし、壮大な宇宙論を説いた。懐徳堂の秀才であった中井履軒[りけん]は、日本で初めて顕微鏡の構造と記録に関する本をまとめ、また、緻密な人体の解剖図譜なども著わしている。

木村蒹葭堂[けんかどう]の名で知られる坪井屋吉右衛門は、じつにユニークな町人学者だ。家業は造酒屋だが、本草学者にして博物学者、そして万物の収集家。蒹葭堂は、学者にも不明な解毒、万病薬に効くとされた薬の正体を、洋書を調べ尽くして解明したという実証主義の町人学者であった。本来の身分は商家の「旦那」。「何事も、まず見てみまひょ、試してみまひょ、調べてみまひょ」という精神が、町人文化によって培われた実学である。大坂商人の才覚とは、好奇心と合理性に根ざしているのである。

しかし、明治維新を迎えた大坂の活力は近代化を前に停滞する。首都は東京に移り、新政府令で蔵屋敷は廃止。経済の原動力であった豪商は相次いで姿を消していった。
|
|
 |
|
 |
|
| 適塾の2階。大村益次郎や福沢諭吉をはじめ、大勢の塾生たちが狭いこの部屋に同居して勉学に励んだ。 |
|
 |
|
| 初代学主、三宅石庵書の「懐徳堂幅」。懐徳堂の名の由来は諸説あるが、『論語』里仁篇の「君子懐徳、小人懐土(君子は徳を懐ひ、小人は土を懐ふ)」に拠るとされる。(大阪大学大学院文学研究科蔵) |
|
 |
|
| 『摂津名所図會』に載る「伊藤東涯含翠堂講義図」。当時の大坂の学問所の学習風景をうかがい知ることができる。含翠堂(がんすいどう)は、懐徳堂の前身ともいえる私塾で、有力商家7家が出資し設立された。後の懐徳堂の初代学主となる三宅石庵などが講義を受け持っていた。(大阪大学大学院文学研究科蔵) |
|
 |
|
| 薬の町、船場道修町の少彦名神社(薬祖神)。少彦名と中国古代の医薬の神、神農氏を祀り、神農さんと呼ばれて親しまれている。道修町には薬酒問屋が100以上もあり、問屋が薬を調合していた。 |
|
|
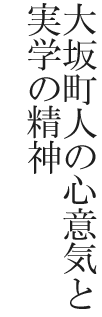 |
|
 |
|

オランダ語の辞書「ヅーフ辞書(ヅーフ・ハルマ)」。写し書きした一冊しかない貴重な辞書だったため、塾生たちは辞書を見るにも順番待ちをしたという。(大阪大学附属図書館蔵) |
|

今橋3丁目のビルの傍らに建つ懐徳堂跡碑。 |
|

「緒方洪庵肖像」。1850(嘉永3)年、洪庵40歳のときの肖像。髪は総髪で蘭学書を読み耽る姿が、いかにも凛とした壮年の学者として描かれている。 |
|