|
輝政亡き後、池田利隆、光政に継がれたが、1615〜16(元和元〜2)年の大坂夏の陣を境に徳川四天王の一人である譜代大名の本多忠政が姫路城に入る。外様からより信頼のおける譜代への城主の交代は、国盗りの時代から領地を執政する新時代の到来を意味した。輝政の姫路城をさらに整備したのが忠政である。

優美な西の丸は忠政が、嫡子忠刻の正室で2代将軍徳川秀忠の娘である千姫のために造営した。千姫輿入れの御化粧料として10万石が与えられ、この千姫の存在が姫路城の整備に強く影響を及ぼしている。武蔵野御殿や向屋敷、東屋敷に西屋敷などを新たに設けたほか、忠政は城の西を流れる船場川を拓き、瀬戸内海に面した河口の飾磨とを結んで物流の促進を図るなど、安寧の時代にふさわしく防備の欠陥を補いつつ、城下町の経営にも取り組んだ。こうして今日の都市としての姫路の原形がほぼ完成した。この忠政の一時期に宮本武蔵が城に身を寄せたという伝承も残る。

関ヶ原の戦い以降、歴代城主を数えると、池田、本多、松平(奥平)、榊原、松平(結城)、酒井の6氏31代に及ぶ。もっとも長く姫路城主を務めたのは明治維新まで119年間、10代つづいた酒井家で最後の城主は酒井忠邦である。その間、姫路城は鉄壁の防御を備えているにも関わらず、不戦の城であった。維新の戊辰戦争の折にも倒幕軍に対して無血で開城している。そして明治という新しい時代にあって姫路城はもはや封建時代の遺物でしかなく、主不在の城は放置され荒れるままだった。雑草が生い茂り、多くの施設は取り壊されて軍の施設に代わっていった。火災で焼失した建物も含め、城は廃城の危機にさらされた。古い史料写真を見ると屋根は落ち、壁は剥がれ、朽ち果てる寸前の無残な城の姿が写っている。

そんな城の惨状を見かねて市民の間で保存運動が盛り上がり、姫路城は国宝に指定される。そうして姫路城は長期に及ぶ保存工事がつづけられるようになった。なかでも1956(昭和31)年から8年を要した天守閣の「昭和の大修理」だ。この大天守の修理は「新築造」ともいわれたほどの大工事だった。瓦の一枚一枚、柱の一本一本を解体撤去し、そして元の姿に復元するという工事はまさに新しく姫路城を築城するのに等しい。地盤調査、大天守を覆いつくす巨大な架設工事。解体する過程で先人の匠の高度な技と正確さに驚嘆することが度々だったという。課題は山積み。なかでも姫路城大天守の最大の特徴である地階から6階床下まで貫通した東西2本の大柱の取り替えは困難を極めたが、現代の匠たちは先人に挑むように「400年先を想定した工事」を見事に完了させた。

そうして昭和の時代に姫路城は新しく甦った。築城から約400年、近代城郭建築のほぼ完全な姿と構造を残しているといわれるが、それでも『播州姫路記』の記録に照らし合わせると、半分以上の建物が失われている。それにしても、目の前にそびえる姫路城天守閣の姿は池田輝政が築城した当時と寸分も変わらない。遠目も良し、近くも良し。どこから眺めても白鷺が舞っているかのような優雅な佇まいである。
|
|
 |
|
 |
|
| 大天守の最上階から西方の眺め。手前右の小山が男山。最上階からは播磨灘や姫路平野を一望できる。 |
 |
|
|
| 西の丸の化粧櫓。千姫が身繕いした場所に因んでその名がある。西の丸は本多忠政が嫡男忠刻の正室である千姫のために造営した。 |
|
 |
|
| 雑草が生い茂る備前丸から撮影された昭和の大修理前の天守。よく見ると大天守が傾いているのが分かる。漆喰壁が方々で剥げ落ち、廃虚のようだ。(姫路市立城郭研究室蔵) |
|
|
|
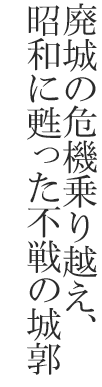 |
|
 |
|

「千姫奉納の羽子板」。千姫が奉納した羽子板は『源氏物語』を主題にした金彩の豪華な蒔絵がほどこされもので千姫天満宮で保存されている。(男山千姫天満宮蔵) |
|
|

男山の麓には、千姫が本多家の繁栄を祈願して造営した男山千姫天満宮がある。西の丸の居館から天満宮に向かって毎日手を合わせていたと伝えられている。 |
|
|

西の丸、長局内部。百間廊下と呼ばれる長い廊下に沿って、いくつもの小部屋が連なる。 |
|

本丸の北側にある腰曲輪には、多聞長屋があり井戸や、塩・米を蓄えて籠城に備えた。緩やかな美しい弧を描いたこの建物は姫路城のほかに例がない。 |
|

部材の継ぎ手に記された茄子の絵合番付。城を建てる時に大工が各部材の位置や接合部分を示す番付(記号)を植物や、昆虫、鳥、魚などを図案化して用いた。(姫路市立城郭研究室蔵)
|
|