 |
 |
 |
 |
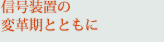 |
上田泰彦は、30年近くにわたって天王寺駅の輸送業務に携わっている。鉄道業に携わるようになったきっかけを聞くと「父も国鉄職員でしたし、小さい頃から自宅近くを走るSLを見て育ちましたから、当然のように国鉄を職場として選びました」と上田。

昭和44年に入社し、かつて大阪港の物流を担っていた貨物専用駅である浪速駅での運転業務を9年間担当した後、信号操車の試験を受け、東岸和田駅の信号係として配属。昭和55年から天王寺駅で信号操車を担当する。

「昭和61年に、これまでの手動の信号装置から電子連動装置が導入されることになり、新宿駅と、ここ天王寺駅に新システムが設置されました」と上田。新システムを使いこなせるようになるまでは悪戦苦闘の日々だったという。
|
 |
 |
 |
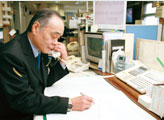 |
| 関係各所と連絡を密にすることも大切だ。 |
 |
|
 |
 |
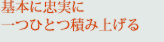 |
平成10年、上田は運転整理員の資格を取得し、信号業務に加えて運転整理の業務も行えるようになった。

「運転整理は、列車の入線の順序を変えたり、着発線を入れ替えたりと、列車運転をどうするかを決めて信号係に指示をする業務です。指示をする側、受ける側の両方を理解している担当者がいれば、それぞれの業務の連携がよりうまくいきます」と話す。ダイヤが乱れた時などは、信号と運転整理の連携が非常に重要となる。そこで、自らの信号業務の経験を活かし、伝達事項の正確さを期すために独自の書式の伝達用紙をつくるなど、業務改善にも貢献した。

「大切にしているのは、基本に忠実に仕事を行うということ。そして、一つひとつ確実に積み上げることです。後輩には、最後になっても油断するなといつも言っています」とほほえむ上田だが、このにこやかな笑顔が業務に臨むときは厳しい眼差しへ変わる。 |
 |
 |
 |
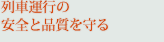 |
「お客様の安全を守る大変責任の重い仕事です」と上田。安全で正確な運行のために、万に一つの間違いも許されない。1分1秒が真剣勝負だ。

「天王寺駅は阪和線、大阪環状線、大和路線が乗り入れています。悪天候などで1つの路線で少しダイヤが乱れただけで、全体に影響します。このため、各線区の列車ダイヤと遅れを見ながら列車の順序などを整理して、各線区のダイヤの乱れを最小限に留めるかが、私たちの仕事です」と上田。天王寺駅を発着する列車本数は1日約800本、繁忙期には1,000本にも及ぶ。この全列車の運行を担う重責は計りしれない。

「私たち輸送屋にとっての使命は、商品である列車の安全を最優先に、かつ正確に動かすことです。そしてこの品質を守るのが自分の仕事だという責任と自覚をもって業務にあたっています」と上田は言う。趣味は音楽鑑賞。「無事に仕事を終え、自宅のオーディオルームでジャズやクラシックを聴くのが最高の喜びですね」と、音楽で気持ちをリフレッシュさせ、次の仕事にあたることが大切な時間になっている。この切り替えが、細やかな神経で緊張を持続させ、日々の安全運行を守りつづける匠の秘訣なのだろう。 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 駅構内の信号を監視する。 |
 |
 |
| 運転整理のためダイヤを引き直す。 |
 |
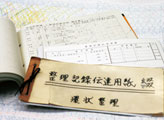 |
| 伝達事項の正確さを期すため、上田の提案が採用された天王寺駅独自の仕様でつくられた伝達用紙。 |
 |
 |
| 異常時には手動で信号を制御することもある。CTC(列車集中制御装置)を手動操作に切り替える解放訓練を行い、若手に技術を継承するのも大切な役目。 |
 |
 |
|
|
 |