|
播州の空は青く、広い。その蒼天を突いて、漆喰で化粧された白壁の大天守が君臨するようにそびえている。標高45.6mの姫山の頂に建つ5層6階、地下1階の大天守は石垣を含めると高さ46.3mだ。そして渡り櫓で3つの小天守を従えた複雑な構造と様式の美しさは近代城郭建築の最高傑作といわれている。8棟が国宝、74棟が国の重要文化財。そして今日では世界の遺産でもある。

飛び立つ白鷺にたとえられる現在の姫路城を築いたのは池田輝政だが、姫路城史を辿ると南北朝時代に遡る。播磨国の守護、赤松則村[のりむら]が姫山にはじめて縄張りし、次男貞範[さだのり]が築城したという説がこれまで有力だった。赤松氏以後は姫路に隣接する御着[ごちゃく]を本拠とした小寺頼季[こでらよりすえ]を築城者とする説もあるが、いずれも江戸時代に書かれた『姫路城主之次第』にもとづいていて信憑性は低い。史料的に姫路城の存在が明らかになるのは1561(永禄4)年の「姫路正明寺[しょうみょうじ]文書」の記述である。

文書には、1555(弘治元)年に姫山の主要部分を売却したことが記録されている。この頃、姫路を預かっていたのは小寺氏の重臣、黒田重隆、職隆父子だ。『黒田家譜』にも「姫路の城は小寺の端城」の記述がある。つまり御着の出城として小寺氏が黒田父子に姫山に城を築かせたというのが最近の説だ。城といっても砦程度の規模か、姫山の地形をそのまま利用した小さな山城だったと推察される。そして後に登場するのが黒田孝高[よしたか](官兵衛)だ。高潔な人格で知られる孝高は、秀吉の天下取りを後押しした不世出の軍師、参謀である。

天下統一をほぼ掌中にした織田信長は羽柴秀吉に摂津、さらに西国諸国の平定を命じる。有名な三木城の兵糧攻めなど播州の戦国大名を次々に攻め落とし、やがて山を越えた因幡、西国諸国へと攻略の矛先は向かう。秀吉がその西国攻めの拠点としたのが姫路の城だ。その折、孝高は自らの居城を秀吉に献上したといわれている。秀吉に賭けたのである。そして西国攻めを万全とするために、秀吉は新たに城を築いた。姫路城と呼ばれるようになったのは秀吉の時代からであり、単に土塁を築いた山城でなく、名実ともに姫路城の誕生といっていいだろう。時は1581(天正9)年だった。

秀吉の姫路城は、高い石垣を積み上げた見るからに堅固な構えの3層4階から成る望楼型の天守だ。再現模型をみると白鷺の白亜の天守とは対照的に、天守全体が烏のように真っ黒である。素っ気ないほど装飾性はなく、質実剛健の城普請で、山陽路で初の天守を備えた城だった。『豊鑑[とよかがみ]』には「石をたたみて山をつつみ、地をうがちて水をたたえ、やぐらどもをあまた造りつづけ」とある。この新たな姫路城を拠点に秀吉は官兵衛を伴って備中に入り、高松城を水攻めする。大事件はその最中に起こる。1582(天正10)年6月2日、本能寺の変だ。その報を聞いた秀吉は有名な「中国大返し」で急ぎ姫路城に戻り、明智光秀の討伐に赴く。そして一気に天下人へと昇りつめた。出世の足がかりとなったため、秀吉の「出世城」とも呼ばれる。

その後、秀吉は大坂城を築いて本拠と定め、姫路城に戻ることはなかった。代わりに異父弟の羽柴秀長、次いで木下家定が姫路城主となった。
|
|
 |
|
 |
|
| 三の丸から菱の門をくぐってすぐにある三国濠。築城当時は水のない捨濠で、天守への通路を狭くし侵入した敵を追い落とすための濠。城内の排水溝を導いて雨水を溜める。石垣塀は秀吉時代のものが一部手直しされているという。 |
|
 |
|
| 写真左から黒田孝高(官兵衛)、羽柴秀吉、池田輝政。黒田氏の居城だった姫路の城を秀吉が譲り受けて西国攻略の足がかりとして姫路城を築城。関ヶ原戦以後、池田輝政が今日目にする姫路城を築いた。
(写真左から福岡市博物館蔵、光福寺蔵:『週刊名城をゆく 2 姫路城』小学館2004より、島根県立博物館蔵) |
|
 |
|
| 「真柴久吉公播州姫路城郭築之図」。播磨灘を背景に築城中の姫路城のようすが描かれているが、江戸時代のもので想像で描かれたのだろう。徳川期であり、豊臣の名はあからさまに書けなかったため羽柴を真柴、秀吉を久吉と記している。(兵庫県立歴史博物館蔵) |
|
 |
|
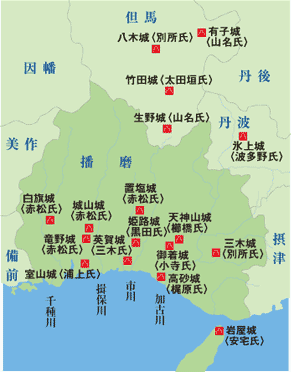 |
|
| 姫路は古代から国府が置かれた播磨国の中心。陸路・海路の要所で、その地勢の利ゆえに国盗りの戦国時代には戦略的に極めて重要な拠点。赤松、黒田、小寺、別所氏などが群雄割拠していた。 |
|
|
|
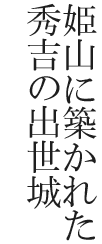 |
|
 |
|

秀吉姫路城の復元模型。秀吉は山陽道で初めて天守閣をもつ城を築城した。3層4階構造で最上部は信長の安土城と同じ望楼型。現在の白鷺城とは対照的に黒い板張りで烏を思わせる。ただし外観には諸説ある。(姫路市立城郭研究室蔵) |
|

「ほ」の門と「水の一門」との間の築地塀の油壁は、粘土に砂利、米のとぎ汁を混ぜて突き固めており、秀吉築城の名残りの壁といわれている。 |
|

秀吉時代の大手口であったといわれる「との一門」。ここを下ると搦手登閣口(裏口)である「との四門」へといたる。 |
|

備前丸から仰ぎ見た大天守と西小天守。高い石垣の上にそびえる5層6階、地下1階の大天守の姿は華麗さもさることながら人を圧倒する存在感がある。
写真下は夕日に染まる姫山の姫路城大天守群。 |
|
|