|
山紫水明という言葉がある。山は陽に映えて紫に見え、川の水は澄んで清らかであることを讚え、日本の風景の美しさを表している。そして、繊細で陰影に富む山紫水明の風景を演出しているのが、水である。四季折々に、流水や水蒸気に、また雪や氷に姿を変化させる水の多様性が風景に奥深い趣を醸して日本人の感性を育んだ。「日本語ほど水にちなんだ言葉や表現が豊富な国はなく、多くが正確に翻訳できない」(国語学者・金田一春彦氏)と語られるほど、水は日本の生活と文化に深く浸透している。

そんな人と水の関わりを、「水の循環」という自然のサイクルを通して教えてくれるのが琵琶湖だ。一級河川だけでも119もの川が流れ込む日本最大の淡水湖は周囲が235km、貯水量は275億k。しかし閉鎖性水系で出口は唯一琵琶湖南端の瀬田川だけである。水は地表と大気中を絶えず循環し、ゆえにそのサイクルのどこかに狂いが生じると水は汚染され、琵琶湖の場合だと回復に20年近くの時間を要するといわれている。水を供給する山と川、水を溜める琵琶湖、人々はその循環の中で水を利用して生活を営んでいる。つまり、水は水系に棲息するすべての生命を育み、また生き物たちは水系を守るのにそれぞれに分担する役割があるのだ。そういう水循環の連鎖を、大きな風景として教えてくれるのが琵琶湖とそれを取り囲む山河、そして人の暮らしだ。

琵琶湖の北西、湖上に大きくせり出した湖西平野は肥沃な田園地帯だ。すぐ背後に1,000m級の急峻な比良山系の山々を有し、その山奥に源を発する小さな幾筋もの渓流が安曇川[あどがわ]となり、麓の田園地帯をその豊富な水量で潤しながら琵琶湖へと注ぐ。もう一つは比良山系の釈迦岳を源流とする鴨川で、湖西平野は太古に2つの河川が土砂を運んでできた巨大な扇状地である。そして安曇川の上流にある朽木[くつき]地区の豊かな原生林が貯えた水は地中に涵養[かんよう]され、やがて湧き水となって地表に現れる。

朽木は琵琶湖から遠く離れた山間の集落だが、山林は林業のためだけでなく「水源の一滴」のために人の手で守り育てている。山を守ることは水源の管理でもあり、大事なのは適地適材の森のバランスだ。朽木の山林は保水力の高い広葉樹林と林業に適した針葉樹林とがみごとに共存する。降った雨水を蓄えてくれる広葉樹の山を「止め山」といい、木を伐採する山林と区別して管理している。この昔からの決まりを無視すると、多量の降雨は一気に地中や河川に流れ込み、土砂災害を招くことになるからだ。

それは、山の斜面に段々に築かれた里山の棚田にもいえる。鴨川の上流、畑地区にある大小359枚の段々の棚田は美しくすばらしい。そもそもは土地の狭い山間部の傾斜地で耕作できるように切り拓いた水田だが、棚田は川の水や降った雨の水を一時的に留め込み、川に流れ込む水量を自然に調整するダムの役割を果たしている。

そして水の旅は、琵琶湖畔の代表的な風景である葦[よし]原の湿原地帯へと至る。葦はイネ科の植物で、安曇川の河口には葦の大群落がある。葦は成長する過程で窒素やリンを吸収し、光合成によって水中に酸素を供給し水質を浄化する力があり、この働きが水質を劣化させる富栄養化を防ぐ。葦の湿原は餌が豊富で、身を隠すにも繁殖にもよく、水鳥や水辺の小さな生き物たちの恰好の棲処となっている。一年草である葦は毎年刈り取らないと弱くなるため、人々は葦を刈ってさまざまな生活用品に加工し、水の循環と自然の摂理に上手く関わってきた。しかし、高度成長とともに琵琶湖の湖岸から葦原は次々と消え、近年の再生保護事業で残された一つが安曇川の葦原だ。琵琶湖の風景に欠かせないだけでなく、葦原は琵琶湖の水を守るためにどうしても必要なのである。

山林に棚田に、葦原。そしていま一つ、人の暮らしそのものが水とどう向きあっているのかを教えてくれるのが、湖西平野の高島市新旭町である。 |
|
 |
|
 |
|
| マキノ町の山から琵琶湖を望む。遠望中央に見える湖上にせり出ているのが湖西平野。比良山系に源を発する安曇川、鴨川が土砂を運んでできた肥沃な扇状地が豊かな田園を育む。(地図内(2)) |
|
 |
|
| 琵琶湖へと流れ込む安曇川。田畑を十分に潤した安曇川は、河口付近で葦原やさまざまな水生植物など小さな無数の生命を育む。(地図内(5)) |
|
 |
|
| 琵琶湖畔・針江地区の葦原。低湿地に生きる小動物の恰好の棲処となる。成長した葦は、冬の始まりに刈り取られ、春先に葦焼きが行われる。(地図内(6)) |
|
 |
|
| 琵琶湖畔の「新旭水鳥観察センター」の湖岸の景観。このあたりは琵琶湖でも有数の野鳥の飛来地でさまざまな野鳥を観察できる。(地図内(7)) |
|
|
|
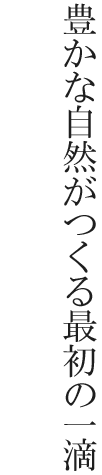 |
|
 |
|

山々に囲まれた畑地区。秋頃の棚田は一面、黄金色に輝く。高齢化とともに棚田の管理が難しくなり、最近は「棚田オーナー制度」を設けて景観を守っている。(地図内(1)) |
|

高島市朽木地区を流れる安曇川。よく管理された広葉樹や針葉樹の山林が最初の一滴を生み、幾筋もの小さな渓を集めて琵琶湖へと旅する。(地図内(3)) |
|

八ツ淵の滝の一つ大摺鉢。清冽な流れは、比良山系釈迦岳の山懐を下り鴨川となって琵琶湖へと注ぐ。(地図内(4)) |
|

針江大川が琵琶湖に注ぐ河口付近は水生植物が豊かに繁り、野鳥、魚、昆虫たちの聖域となっている。 |
|