 |
 |
 |
 |
琵琶湖最北の町、塩津浜は
「塩津海道」の拠点として
大津と並ぶ繁栄と賑わいを極めた。
畿内と日本海側を結ぶ物流の十字路、
古道と海道の町、
塩津の今を訪ねた。 |
 |
 |
 |
 |
 |
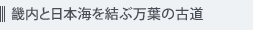 |
森閑とした杉木立の森の奥へとひと筋の古道がつづいている。紫式部も、越前武生の国守に赴任する父・藤原為時の供をして歩いた道だ。峠の名をとって深坂古道という。

この古道を含む、畿内と敦賀や北国とを最短距離で結ぶのが塩津海道で、起点となったのが現在の西浅井町塩津浜だ。琵琶湖の最北に位置する塩津の湖畔には、静かにさざ波が寄せているが、今も交通の要衝であることに変わりない。近江塩津駅は北陸線の主要駅であるとともに、湖西線の起点駅である。

国道脇に「海道[かいどう]繁栄」と刻まれた古い常夜燈がある。街道でないのは、塩津の繁栄が「淡海」という琵琶湖の水運なくして語れないからだ。とくに江戸時代の塩津港には、北国から米やにしん、昆布などの海産物、鉄や銅…。京・大坂からは呉服、綿、酒、醤油などの大量の荷が集散した。

舟の数、荷の扱い量、廻船問屋の数において塩津の賑わいは、琵琶湖の浦々の中でも抜きんでていたという。物資を満載した舟が琵琶湖南端の大津との間を頻繁に行き交った航路は、まさに「海道繁栄」だった。 |
 |
 |
 |
 |
| 杉の木立が美しい深坂古道を行く。深坂峠は「深坂越え」といわれ、塩津海道の難所だった。この峠が敦賀〜塩津浜を結ぶ最短経路で、多くの人とさまざまな物資がこの古道を行き交った。 |
 |
 |
今秋には、北陸本線、湖西線が一部直流化され、新快速電車などが敦賀まで乗り入れできるようになる。 |
 |
 |
「海道繁栄」「五穀成就」の文字が刻まれている常夜灯。人と物資の往来が盛んだった頃を偲ばせる。 |
 |
 |
深坂古道にある深坂地蔵。深坂越えをする旅人たちが道中の安全を願い、当時は貴重品だった塩を供えたことから別名「塩かけ地蔵」とも呼ばれる。 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
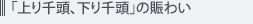 |
塩津の名の起こりは、日本海側から塩が運ばれたことにちなむのだろうと想像してしまうが、塩津神社の縁起によるとそうではない。上古の時代、ここに塩池があって間断なく塩水が湧き、これを製塩して他所から塩を求める必要がなかった…と伝わる。神社の祭神は塩土老翁神[えんどろうおうじん]だ。

塩津神社の近くに、繁栄の歴史を刻んだ塩津の町並みが残る。ゆるやかにカーブした旧道に沿って軒を連ねる家々は古格な佇まいだ。広い間口の廻船問屋や造り酒屋、旅籠、物資を貯蔵した蔵が、物資の集散地であると同時に、宿場町として活気に沸いていた町のようすを想起させる。

ニシンを貯蔵したという蔵は1868(慶応4)年の建築で、庇瓦に施した龍のみごとな飾り一つにも往時の繁栄が分かる。もっとも町の全盛は寛永年間(1624〜1644)といい、米だけでも年間30万石も塩津海道を通過したそうだ。街路には荷を運ぶ馬や大八車など人馬が盛んに往来し、塩津の賑わいは「上り千頭、下り千頭」と形容された。

この最盛期には、物資を運ぶ琵琶湖独特の丸子船が大小およそ1,400隻も湖上を行き交っていたという。丸子船は昭和30年頃まで活躍していたが、現存するのは2隻で大浦に保存展示されている。丸子船は海道の歴史を伝える貴重な遺産だ。 |
 |
| 塩土老翁神を祀る塩津神社。その昔、この付近に塩水池があり、製塩を行っていたという伝説が残る。 |
 |
 |
| 大浦にある北淡海・丸子船の館では、琵琶湖の水運を支えた「丸子船」の実物のほか、ジオラマや資料が展示され琵琶湖水運の歴史を知ることができる。 |
 |
 |
| 庇瓦に見事な龍の飾りがあるニシン蔵。旧道沿いの歴史的な町並み。廻船問屋や旅籠などがかつての繁栄を偲ばせる。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
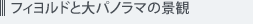 |
出船入り船で賑わった塩津浜には、ゆったりと時間が流れる。北琵琶湖周辺の景観は、細く深く入り組んだ急峻な入り江が特徴で、塩津港も風や波から守られた深い入り江の奥にある。

そんな景観を、北欧の「フィヨルドに来たみたいだ」と讚えたのは作家の遠藤周作氏だ。朝もやのなかに、鏡面のような湖上に横たわる岬の静謐な風景は、幻想的であり詩情的でもあり、凛としたフィヨルドの趣がある。水の透明度も高い。

塩津浜の南に険しく突きだした葛籠尾崎[つづらおざき]からは、神が棲むといわれる竹生島[ちくぶじま]が見え、その先に目をやると、長浜や米原、彦根などの湖北や湖東の町々を望むことができる。さらに、鈴鹿の山々やひときわ雄大な姿を見せる伊吹山、比良山系も遠望できる。北琵琶湖を代表する景観だ。

岬の反対側の入り江には、隠れ里といわれる菅浦の集落がある。他と孤絶した静かな集落は、奈良時代に帝位を追われた第47代淳仁天皇が隠れ住んだと伝わる地である。集落の歴史は平安時代以前に遡り、早くから自治が発達し独自の文化を守りつづけてきた。

湖北には豊かで美しい自然が今も昔のままにある。そして、目まぐるしい時間とは対極の人々の暮らしがそこにある。 |
 |
| 琵琶湖最北端の港町、塩津浜を望む。最盛期は琵琶湖に数ある港の中でも、南の大津と並ぶ飛び抜けて大きな港町だった。 |
 |
 |
| 葛籠尾崎の沖に浮かぶ竹生島。古来から信仰の対象として崇められ、多くの参拝者が訪れる。 |
 |
 |
| 町かどで出会った平塚喜代さん。塩津生まれ、塩津育ちの喜代さんは、祖父母から塩津の町の賑わいを聞いている。「旅館もたくさんあったし、人もたくさんいてました。今は若い人が少のうなりましたが、私には塩津が一番ええです」。昔は、冬になると屋根まで雪が積もって2階の窓から出入りしていたというが、今では積雪も少なくなったそうだ。「ずいぶん住みようなりました」と元気な声で話してくれた。 |
 |
 |
 |
 |
|
 |