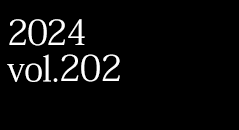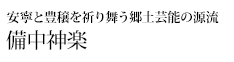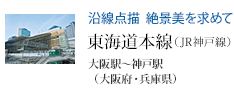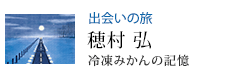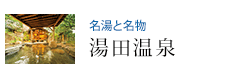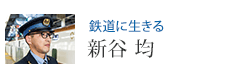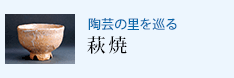萩焼の登り窯

平安古(ひやこ)の鍵曲(かいまがり)。萩城下町特有の街路の姿を残す。
山口県北部に位置する萩市は、萩焼の里で知られる。萩焼の歴史は400年以上前にまで遡り、茶人 千利休や古田織部[ふるたおりべ]と交流があった萩藩の開祖 毛利輝元[もうりてるもと]が、朝鮮から招致した陶工に命じ、萩の松本村に御用窯を設けたことに始まる。
萩焼は主に茶の湯で用いる陶器「茶陶[ちゃとう]」で知られ、土は粗く、浸透性や保水性、保温性に優れている。釉薬[ゆうやく]は枇杷[びわ]色や白色が主流で、土肌や見込み(器の内側)に走る貫入[かんにゅう](釉薬の表面に生じるヒビ)から水分が浸透し、長年使い込むことで色合いが変わる。それを「萩の七化[ななば]け」と呼び、趣のある景色は多くの茶人を魅了してきた。
「一楽[いちらく]、二萩[にはぎ]、三唐津[さんからつ]」。茶の湯の世界では古く、茶人好みの抹茶茶碗の格付けを表す言葉だ。萩焼の伝統技術は脈々と受け継がれ、日本を代表する陶芸文化として現在に至る。1970(昭和45)年に、旧萩藩御用窯三輪家の十代休雪[きゅうせつ](休和[きゅうわ])、1983(昭和58)年には十一代三輪休雪(壽雪[じゅせつ])が重要無形文化財「萩焼」保持者として認定された。

三輪休和(十代休雪)作 萩割高台[はぎわりこうだい]茶碗器の下に作られた高台の一部を切り込んだ割高台茶碗で、素朴さの中にも力強さを感じさせる姿。(撮影 下瀬 信雄)

ロクロ成形