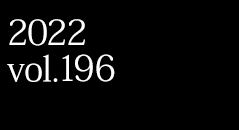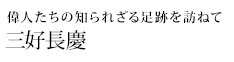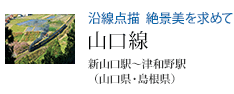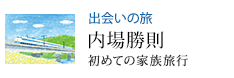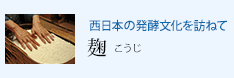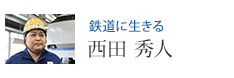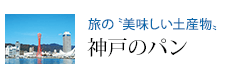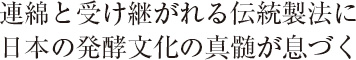

米どころ富山県は、日本でも有数の発酵食文化を持つ。
その要といえるのが、蒸した穀物に 菌を繁殖させてできる「麹」だ。味噌や醤油、味醂[みりん]、米酢、甘酒など、日本を代表する伝統食品の数々は、麹が原料となり醸されることによって生み出される。
菌を繁殖させてできる「麹」だ。味噌や醤油、味醂[みりん]、米酢、甘酒など、日本を代表する伝統食品の数々は、麹が原料となり醸されることによって生み出される。

「散居村(さんきょそん)」と呼ばれる美しい農村の姿が今なお残る砺波平野。福光を含むこの一帯は、古くは加賀藩の穀倉地帯として栄え、現在では全国に誇る富山米の生産地となっている。


「麹」の字を大きく染め抜いたのれんが目を引く石黒種麹店。建物は江戸時代中期のものと伝わる。

発酵の源となる種麹。石黒種麹店の所有する椿の山で採集した葉を燃やし、その灰を用いて 菌だけを純粋に培養する。
菌だけを純粋に培養する。

蒸した米を広げ、米同士を擦り合わせて表面に傷を付け、 菌が中まで入り込みやすいようにする。
菌が中まで入り込みやすいようにする。

「種切」と呼ばれる種麹を蒔く工程。米の一粒一粒にまで均等に胞子が行き渡るよう混ぜていく。

種切りした米を麹蓋に盛り、1枚1枚を「棚積み」する。この方法により酵素の多い麹ができる。

湿らせた菰(こも)を被せて湿度を保ちながら完成した麹。すべて手作業で48時間かけ、麹蓋400枚分の米麹ができ上がる。

完成した麹を拡大した写真。白い胞子に覆われた様子が花のようであることから、米麹のみを表す国字として「糀」が考え出された。
発酵には気候風土が大きく影響するといわれる。高温多湿の日本は、発酵を担う微生物が生育しやすい環境にあり、古くから 菌(コウジカビ)を中心としたカビ食文化が発達してきた。蒸した米に
菌(コウジカビ)を中心としたカビ食文化が発達してきた。蒸した米に 菌をまぶして繁殖させ、米の表面をふわふわとした綿毛のような菌糸で覆ったものが米麹。麦を使ったものは麦麹、大豆を使えば大豆麹となり、清酒をはじめ味噌や醤油などは、この菌がおこす発酵によって造られている。
菌をまぶして繁殖させ、米の表面をふわふわとした綿毛のような菌糸で覆ったものが米麹。麦を使ったものは麦麹、大豆を使えば大豆麹となり、清酒をはじめ味噌や醤油などは、この菌がおこす発酵によって造られている。
文献を紐解けば、奈良時代初めに編纂された『播磨国風土記[はりまのくにふどき]』には「神様に捧げた蒸し米にカビが生えたので、それで酒造りをした」という、日本初の米麹の記述が残されている。平安時代末期には、麹を独占的に製造販売する「麹座」が組織され、室町時代にはすでに「種麹[たねこうじ]屋」と呼ばれる商売が成立していた。種麹とは、麹を造るもと(種)となる 菌の胞子を集めたものをいう。先人たちは、胞子を培養する過程でアルカリ度の高い椿や樫などの木灰を使用し、雑菌を寄せ付けず
菌の胞子を集めたものをいう。先人たちは、胞子を培養する過程でアルカリ度の高い椿や樫などの木灰を使用し、雑菌を寄せ付けず 菌だけが純粋に育つ方法を考案。当時の種麹屋は、造り酒屋、味噌屋、甘酒屋などからの注文に応じて種麹を製造し、供給していたと伝えられる。和の食文化と密接に結びついた
菌だけが純粋に育つ方法を考案。当時の種麹屋は、造り酒屋、味噌屋、甘酒屋などからの注文に応じて種麹を製造し、供給していたと伝えられる。和の食文化と密接に結びついた 菌は、日本醸造学会によって日本の「国菌」に認定されている。
菌は、日本醸造学会によって日本の「国菌」に認定されている。

「先祖代々伝わってきたものを大切にしたい」と石黒八郎さん(左)。一子相伝の技は5代目和郎さん(右)に継承される。
郷土料理かぶら寿しを仕込むための甘酒。地元の人は漬物にも用いる。※「かぶら寿し用甘酒」は主に冬季に販売される。

富山県南西部に位置する南砺市福光。幕末までは加賀藩領であったこの地は、加賀や京へ絹、米などを運ぶ交通の要衝であった。その面影を残す町並みの中に、北陸で唯一、全国でも10軒足らずとなった種麹屋、石黒種麹店がある。江戸後期の文政年間より麹を作り続ける老舗だ。「夏は高温多湿、冬は冷涼多雪という気候風土が発酵に適しています」。そう話すのは、麹屋からは8代目、種麹店としては4代目当主の石黒八郎さん。1895(明治28)年から麹に加え、そのもととなる種麹も手がけてきた。種麹の製法は一子相伝。春と秋には一人室[むろ]にこもり、先代から受け継いだ技法で 菌を育てる。
菌を育てる。
その種麹を使った麹造りでは、代々伝わる「こうじ蓋製法」の教えを守る。蒸して冷ました米に種麹を振りかけ「麹蓋」と呼ばれる木の器の中にならし、それを1枚1枚木棚に並べて発酵させる製法だ。温度32度、湿度はほぼ100%という室の中で、麹は勢いよく破精[はぜ]ていく。「破精る」とは、 菌が繁殖していく様をいうそうだ。「うちの麹は、米の中にまで菌糸を伸ばした総破精の麹。酵素の量が多く力強いのが特長です」。この米麹で仕込んだ甘酒や味噌は、デンプン分解酵素やタンパク質分解酵素のはたらきによって、自然な甘さやコクのある旨みが引き出される。丁寧な手仕事から生まれる麹は、かぶら寿しやニシンの麹漬けなどの郷土料理に使われ、地域に根付く発酵文化を支え続ける。
菌が繁殖していく様をいうそうだ。「うちの麹は、米の中にまで菌糸を伸ばした総破精の麹。酵素の量が多く力強いのが特長です」。この米麹で仕込んだ甘酒や味噌は、デンプン分解酵素やタンパク質分解酵素のはたらきによって、自然な甘さやコクのある旨みが引き出される。丁寧な手仕事から生まれる麹は、かぶら寿しやニシンの麹漬けなどの郷土料理に使われ、地域に根付く発酵文化を支え続ける。