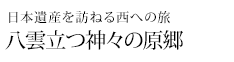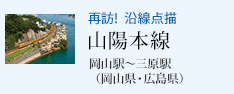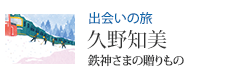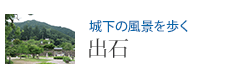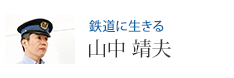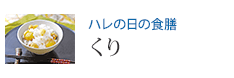山陽本線の岡山駅から広島県の三原駅まで89.9km。瀬戸内海の港湾都市を巡りながら
歴史と景勝美にふれ、三原駅をめざした。

岡山駅前の桃太郎像。
昔話「桃太郎伝説」でおなじみの岡山。岡山駅前の桃太郎像は待ち合わせ場所に利用され、カメラを向けた観光客が撮影に励んでいる。駅前から続く「桃太郎大通り」の先には漆黒の岡山城がある。別名「烏城」。外堀の役割を果たした旭川の対岸には藩主が憩いの場として愛でた後楽園が広がる。日本三名園の一つで知られる芝生の大庭園には能舞台や茶室があり、水路の巡る池には鯉が泳いでいる。回遊式の庭園を一周した後、旭川に架かる鶴見橋を渡ればレトロな建物が点在する出石[いずし]町だ。古民家を改装したカフェや雑貨屋などが並び、岡山の新しいスポットに寄り道するのもいい。
町散歩の後、新幹線や在来線7路線が交わるターミナルの岡山駅に向かった。駅のホームを離れた列車は西へと走る。伯備線が乗り入れる北長瀬駅を過ぎ、笹ヶ瀬川、足守川を渡ればやがて倉敷駅だ。日本有数の観光都市で知られる倉敷は綿花や米の集散地として隆盛を極めたかつての天領だ。繊維の町として潤い、近年は瀬戸内海沿いの工業都市として発展した。中でも「倉敷美観地区」には、倉敷の町づくりに努めた大原家の足跡が数多く残り、国内外からの観光客が絶えない。

宇喜多秀家により1597(慶長2)年に完成した岡山城。旭川を城の東背後を流れるように改修し、天然の外堀として活用している。天守閣の壁に黒漆塗りの下見板を取り付けていることから外観が黒く、「烏城」とも呼ばれる。

岡山城の城下町として栄えた出石町界隈には現在も古い建造物が残り、カフェやギャラリーなどに利用されている。

瀬戸内海に臨み、日本を代表する重化学コンビナートとして発展する水島コンビナート。工場群の美しい夜景は観光スポットになっている。

笠岡駅改札前に展示されているカブトガニの標本。

笠岡市立カブトガニ博物館でカブトガニの保護育成に取り組む館長の惣路さん。「最も絶滅の危機に瀕したのは1975(昭和50)年頃です。現在では活動の成果もあり、約1万匹の放流ができるまでになりました」と話す。
列車はさらに西へ。ここ一帯の沿岸部には、総面積2,500haの敷地に石油精製や鉄鋼生産など、200の事業所や工場が密集した水島コンビナートが24時間稼働している。夜景の美しさでも人気の一大コンビナート地帯だ。列車は岡山三大河川の高梁川を渡ると新倉敷駅で、さらに金光駅を過ぎると地図上では里見川と併走する。倉敷駅から約25分で笠岡駅だ。
何だこれ!? 駅の改札前にはインパクトのある標本が展示されていた。その繁殖地が国の天然記念物に指定されている「カブトガニ」だ。ここ笠岡ではカブトガニの繁殖地の保護や研究に努めている。その拠点が、「笠岡市立カブトガニ博物館」。かつての干拓による水質汚染で絶滅危機に瀕したカブトガニだが、継続的な保護活動が奏功し、現在は徐々に数も増えているという。カブトガニ博物館館長の惣路[そうじ]紀通さんは、「カブトガニの育成条件は内湾性で産卵のための浅瀬の砂浜や、子を育成する広い干潟が必要で、その条件を満たしているのが笠岡です」と話す。カブトガニの活動期は、4月末から9月までだ。

日本三名園の「後楽園」

日本三名園の後楽園から望む岡山城。

藩主の居間があった延養亭。1960(昭和35)年に復元された。
旭川沿いに聳[そび]える漆黒の岡山城と川を挟んで向き合うのが後楽園だ。金沢の兼六園、水戸の偕楽園と並び称せられる「日本三名園」で、一度はぜひ見ておきたい大名庭園だ。広さは東京ドームの約3倍。園内には歴代藩主の居間や能舞台のほか、300年前の築園時の景観をほぼとどめている。年間を通じてさまざまなイベントが催されている。また近年は「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」の三つ星に認定され、海外の観光客にも人気が高い。

世界で唯一のカブトガニ博物館

1990(平成2)年にオープンした笠岡市立カブトガニ博物館。

館内では、実際に活動するカブトガニを観察できる。
広島県との県境に位置する岡山県笠岡市は「カブトガニのまち」として知られる。カブトガニをテーマにした世界で唯一の「笠岡市立カブトガニ博物館」があり、館内ではカブトガニの研究に取り組み、繁殖地への放流も行っている。
約2億年前から姿を変えていない「生きている化石」のカブトガニは、カニではなくクモやサソリなどに近い節足動物で、全世界に4種類いる。また、カブトガニは医療現場でも注目され、青い血液は細菌を固める性質を持ち、注射剤や透析液などに菌の有無を確認する検査に利用されている。
1928(昭和3)年に、生江浜海岸の生息地が「天然記念物カブトガニ繁殖地」として、国の指定を受けた。

瀬戸内海の島々を車窓に走る列車。(尾道駅〜糸崎駅)
一つ隣の大門駅からは広島県だ。車窓から無数の線路や貨物のコンテナが見えると東福山駅で、間もなくすると備後地方の拠点、福山駅に着く。駅のすぐそばには、5層の福山城天守が勇壮に聳える。駅舎は山陽本線敷設の際に、線路を最短ルートで敷くためにやむなく城域内に設置された。駅から少し足を延ばすと、かつて北前船で隆盛を極めた鞆[とも]の浦がある。
瀬戸内海に突き出た沼隈[ぬまくま]半島の先端に広がる鞆の浦は、瀬戸内海のほぼ中央に位置する。“潮待ちの港”で知られた鞆は古く万葉歌人に詠われた景勝地で、とりわけ高台の福禅寺対潮楼[たいちょうろう]からの眺望は圧巻。目の前の仙酔島[せんすいじま]の由来は“仙人が酔う”ほどに美しいとされ、その佇まいが多くの人を魅了した。江戸時代に交易した朝鮮通信使はこの絶景に感激し、「日東第一形勝」の書を残した。それは対馬から江戸までの最高の景勝地を意味した。
弓なりの形の港には現在も数多くの船が停泊し、常夜灯や雁木などが往時を偲ばせている。街の中心部には格子の商家が並び、江戸から戦前までの趣のある建物が数多く残っている。船具店や名産の「保命酒[ほうめいしゅ]」の酒蔵など、総数で約300棟を数えるという。
列車は尾道をめざす。芦田川を渡った列車は備後赤坂駅、そして東尾道駅を過ぎると見上げるように大きな造船所のクレーン車が見えてくる。景色が開け、尾道大橋が迫るとまもなく尾道駅だ。

福山駅前に建つ福山城。1622(元和8)年に、徳川家康の従弟で初代藩主の水野勝成が3年の歳月をかけて完成させた。天守は空襲により焼失したが、1966(昭和41)年に市民の寄付などにより復元された。

福禅寺の本堂に隣接する客殿・対潮楼からの眺め。かつてここを訪れた朝鮮通信使が「日東第一形勝」と賞賛した美しい景色が望める。(写真提供:福山観光コンベンション協会)

名産の保命酒で財を築いた豪商の商家をはじめ、江戸時代以降の建築物が残る鞆の浦。

今年3月にリニューアルした尾道駅。駅には宿泊施設のほか、レンタサイクルや食堂、ブックラウンジなどが設置されている。
尾道は今年開港850年。江戸時代には北前船で大いに繁栄した美しい港町は「坂の町」、「寺の町」、「文学の町」、「映画の町」などさまざまに形容される人気の観光都市だ。そんな尾道が近年サイクリストの聖地として注目を集め、尾道駅もリニューアルされた。新駅舎内にはレンタサイクルを完備し、宿泊施設やカフェ、尾道水道を望む眺望デッキなどがあって駅舎自体が新たな観光スポットになっている。尾道の魅力がさらにアップして旅の楽しみが増えた。
いよいよ旅も終盤だ。尾道駅を出るとここから最大のビューポイントを迎え、沿岸部の際を走る列車からは、瀬戸内海に浮かぶ島々や船の往来が車窓を彩る。そして糸崎駅を過ぎると、終点の三原駅へ到着する。
瀬戸内海に沿って走る旅は、北前船交易で栄えた港町を辿る旅でもあった。

千光寺山からの眺望。尾道水道を挟んで、瀬戸内海の美しい島々を見渡せる。

サイクリストの聖地・尾道

倉庫を改装した「ONOMICHI U2」は、尾道の新たな観光拠点。

尾道を起点とする「瀬戸内海横断自転車道」は、日本で初めての海峡を横断する自転車道。
近年、尾道は「サイクリストの聖地」として脚光を浴びている。広島県尾道市と愛媛県今治市を結ぶ「瀬戸内しまなみ海道」に全長約70kmの自転車コースが設けられ、瀬戸内海に浮かぶ島々を巡るサイクリングの旅が人気だ。
尾道駅の西側、造船所の見える海沿いには倉庫を改装した「ONOMICHI U2」がある。自転車を持ち込んで宿泊できるホテルやレストラン、自転車ショップなどが入る複合施設で、そこではレンタサイクルの貸し出しも行っている。尾道の新たな観光スポットの一つとして、国内外のサイクリストに利用されている。