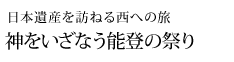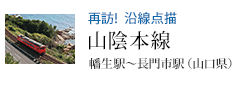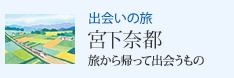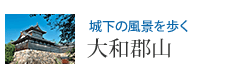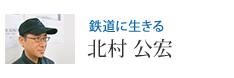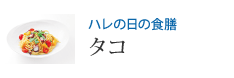1967(昭和42)年福井県生まれ。作家。2004(平成16)年「静かな雨」で文學界新人賞佳作を受賞してデビュー。2016(平成28)年『羊と鋼の森』(文藝春秋)で本屋大賞、キノベス!2016第1位、ブランチブックアワードを受賞。他の著書に『スコーレNo.4』(光文社)、『遠くの声に耳を澄ませて』(新潮社)、『太陽のパスタ、豆のスープ』(集英社)、『誰かが足りない』(双葉社)など。最新刊は食べることと生きることについてのエッセイ集『とりあえずウミガメのスープを仕込もう。』(扶桑社)。
大学で東京へ出て、初めて福井へ帰省したときに、とても驚いた。ーーいや、正直にいえば、初めての帰省の際は、久しぶりに実家に帰るのがうれしくて冷静にはなれなかったから、二度目か三度目だったかもしれない。三十年も前のことだ。これが私の生まれ育った街だったか、と驚いたのだ。
東京から東海道新幹線、米原で北陸線に乗り換える。その「しらさぎ」の中でのことだ。もうまもなく到着するはずなのに、と時計と窓の外を何度も見比べて、そわそわしてしまった。窓の外にはいつまでたっても田んぼが広がり、家はまばらで、とても県下最大の駅に着くとは思えない。到着予定時刻が迫るにつれ、時間を間違えたのかもしれないとさえ思ってしまった。曲がりなりにも県庁所在地の、市内ではたったひとつだけの特急の停まる駅なのだ。やがて、時間通りに福井駅に着いたとき、驚きと同時に笑いがこみあげてきた。そうか、こんなに小さな駅だったのか。ホームは全体が見渡せる大きさで、改札はひとつだった。小さいことを卑下するつもりはない。否定的な気持ちもない。ただ、小さいということを、初めて知った気がした。それは、新鮮な驚きだった。私はこの小さな街で生まれて育ってきたのだ、と発見したような気持ちだった。
当時の私は、福井が好きでも嫌いでもなかった。愛着はあるけれど、いつか出ていくものだと思っていた。なぜかはわからない。でも、若かった頃は、ここから新たな街へ出ていくことが出発だと思っていた。そこで新しい誰かと出会い、知らなかった何かと出会う。想像するだけで胸が躍った。
楽しかったなあ、と思う。18歳だった私は、東京で、福井では見たこともなかったような人たちと出会い、親しくなったり、また離れたりした。聴いたこともなかった音楽を聴くようになり、行ったことのなかったコンサートにも行くようになった。やったことのなかったスポーツを始め、4年間を体育会で過ごした。いいことにも、よくないことにも、うれしいことにも、つらいことにも、出会った。それらが今の私の一部になっていることは確かだ。
それでも今、福井で暮らしている。そうして、出会いについて考えるなら、外へ出ていって出会うものよりも、帰ってきて出会うものの大きさを思う。つまりは、旅から戻ったときのわが街、福井のよさを思うのだ。「サンダーバード」も好きだし、「しらさぎ」も好きだ。好きな席まで決まっている。でも、出かけるときのワクワクも、帰ってきて駅の改札を出るときの、ほっとする感じにはかなわない。何度旅に出て、そこで何かと出会ったとしても、ここへ帰ってきて私の中でじっくりと育つものがあって初めて、出会ったといえるのではないか。何を見て、何を聞いても、誰と話して、何を感じても、そのときだけのものならつまらない。福井へ帰り、日常に戻って、ひとつひとつの出会いをかみしめたときに、もう一度私の中で出会いなおしがある。それこそが、小説を書くときの核となるものであり、暮らしの核でもあると思っている。
福井という駅も、街も、もしかすると今、中途半端なところにいるのかもしれない。北陸新幹線は、まだ来ない。それがいいことなのかどうか、私にはよくわからない。早く来てほしいと願う人の気持ちはもちろんわかるし、これ以上便利にならなくていいという人の気持ちもわかってしまう。便利になるということは、その陰にひっそりと消えていってしまうものがあるはずだから。でも、いつか開通した新幹線で福井からどこかへ出かけるときに、とりわけ福井へ戻ってきて電車を降りるときに、必ず何かに出会うだろうと思う。今まで知らなかった福井、これまでは見えなかった福井と出会いなおす。私はそれをひそかに楽しみにしている。