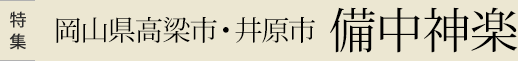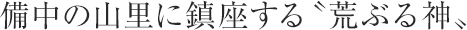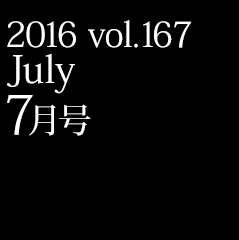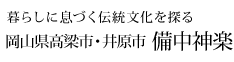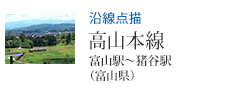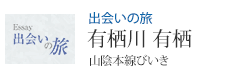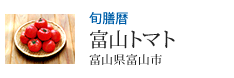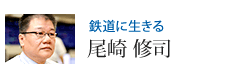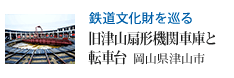成羽町は備中神楽発祥の里らしく、神楽による町づくりを進めている。町のあちらこちらで神楽人形を見かける。成羽川に架かる橋の袂には素戔嗚尊の神楽人形。
高梁川と成羽川[なりわがわ]、この二つの清流が交わる岡山県高梁市は山峡の美しい町だ。町の北側の臥牛山の頂には“天空の城”として知られる備中松山城があり、武家屋敷や古社寺に古い商家群を残す端正な町の佇まいは「備中の小京都」といわれる。なにより印象的だったのは、早朝、大人たちと一緒に街路を清掃する子供たちの姿だった。
高梁の市街地から少し外れた成羽川沿いの成羽町地区、ここが備中神楽発祥の里だ。橋の袂[たもと]には怖い形相で仁王立ちする大蛇[おろち]退治の素戔嗚尊[すさのおのみこと]。昔ながらの本丁商店街の神楽ロードには、猿田彦命[さるたひこのみこと]のほか神楽の物語順に手作りの神楽人形が置いてあって訪れる人の目を楽しませてくれる。
そもそも神楽の起源は、記紀神話の中の「天岩戸[あまのいわと]」の一節にある天鈿女命[あめのうずめのみこと]が岩屋の前で舞った即興の踊りともいわれ、神を招き祓い清め、神を楽しませおもてなしをする神事である。

成羽川に注ぐ小さな川が流れる谷筋に、備中神楽の最大の功労者、西林国橋の生家がある。ここの集落の景観は中世からの形態を今も保っている。
成羽町が備中神楽発祥の地とされる由縁は、江戸時代に西林国橋[にしばやしこっきょう]という神官が、備中神楽の一部に「神代神楽[じんだいかぐら]」と呼ばれる演目を創始したことによる。西林は当時興隆していた能や歌舞伎などの芸能に触発され、それまで神事色が濃かった備中神楽に、演劇としての要素を強調した芸能的な演出を加え、今日に伝わる備中神楽の基本を作った。成羽川の支流を遡[さかのぼ]った谷間の里、落合町福地が国橋の生誕地で、今も同じ場所に生家がある。
小さな谷を訪ねると、南側の山の斜面に家々が点在する。昔話に出てくるような集落の景観だ。山の斜面や尾根筋など高い場所に家屋敷が建ち、その周辺に畑、下方に田が広がっている。そして集落の一番高い場所には荒神が祀られている。備中神楽は大きく分けると、毎年行われる地域の氏神に奉納する「宮神楽」と、荒神に奉納する「荒神神楽」がある。

高梁市の最南部、川上町仁賀(にか)地区にある荒神社境内に祀られる地神。備中では土地を守る地神として五穀豊穣などを司る。
荒神信仰は主に西日本に広く分布しているが、備中地方は特に信仰が篤い。荒神とは一般的に火の神、竃[かまど]の神として知られているが、備中地方では祖霊と結び付いた土地を守る地神[じしん](産土神[うぶすながみ])として崇められている。一つの集落の地区単位で祀られ、土地との結び付きが極めて強い。荒ぶる神でもあり、時に凶作や疫病をもたらす。その神の御霊を鎮め、安寧と豊作を祈るのが「荒神神楽」である。

荒神を祀る祠は備中地方のいたるところで見かける。写真は井原市美星町の荒神神社。祠の前で神楽が奉納されるが、観客席となる広場は普段は子供たちの遊び場。
山中の曲がりくねった道を行くと、注連縄[しめなわ]を施した荒神を祀る祠をよく見かける。どの祠も掃き清められて清々しい。「荒神神楽」は十二支が一巡する13年目、または7年目の式年ごとで行われる。それは実に大掛かりで、神迎えの儀式から託宣の儀式まで夜を通して2日にも及び、厳粛かつ幻想的に繰り広げられる。古式ゆかしい神事と、国橋が創作した娯楽性に富んだ「神代神楽」が演じられる。その演目は、「宮神楽」とは比べものにならないくらい多いのだ。

高梁市成羽町の神楽ロードには、備中神楽の人形が並ぶ。写真は、神代神楽の「国譲り」で、高天原から天下った経津主命(ふつぬしのみこと)と武甕槌命(たけみかづちのみこと)が揃って舞う一場面。
「神代神楽」は通常、記紀神話に基づく「天岩戸」「国譲[くにゆず]り」「大蛇退治」の3篇が演じられるが、備中では桃太郎伝説にも関わる吉備津彦命[きびつひこのみこと]の鬼退治、「吉備津[きびつ]」が加わることもある。どの神代神楽も、軽快なテンポと躍動感のある動きと演技、台詞もあって観ていても実に面白いものだ。それは神と一緒に、大人も子供も楽しむ「神人和楽」の饗宴である。
「神楽が身体中にしみ込んでいる。面白うて飽きることがない」と、演じる者も見る者も誰もがそう話す。備中地方では毎年秋から春にかけて、山や谷間のどこかで神楽の太鼓がトントン、トンと響き渡る。それは、荒神を鎮め、家族の無事、暮らしの平穏、豊饒の実りを祈る調べでもある。