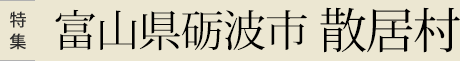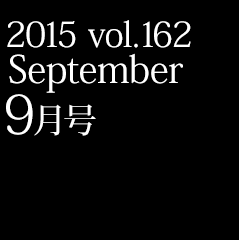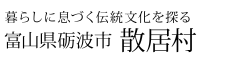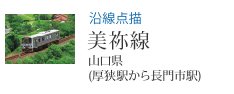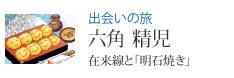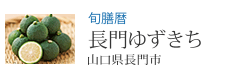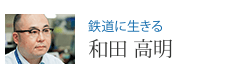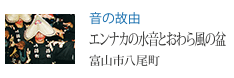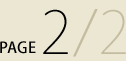
家屋敷はどこも立派な構えだ。大きな家の敷地は1,000坪。家の四方を囲むように広い田畑があり、隣家とは100m以上も離れている。敷地には母屋、土蔵、納屋、庭、囲炉裏の灰を保管する灰納屋が基本で、さらに洪水に備えた「ハトリ」という石垣も見られる。
なかでも代表的な母屋の形態は「アズマダチ」と呼ばれる。江戸時代の金沢の武家屋敷を倣った大きな切妻屋根を持つ家だ。それ以前は「クズヤ」という茅葺き屋根の寄棟造りが主流だったが、明治時代以降、切妻の瓦屋根に建て替えられた。その造形は大胆で、大屋根の黒い瓦に木組みと白壁の意匠は今日でもモダンだ。

稲穂がたわわに実り頭を垂れる。秋の散居村は一面金色に輝く。
見上げるほどの高木のカイニョに囲まれた、県の有形文化財に指定されている入道[にゅうどう]家を訪ねた。当主の入道忠靖さんは12代目で、江戸時代に入植し、かつて村長も務めた旧家だ。幕末にクズヤを建て、以後、歴代の当主が改修、改造を重ね、大正時代に現在のような大きな屋敷が完成。砺波では何代にもわたって家を大きくするのが習わしだ。間口九間、奥行九間、とにかく広い。一階だけで上中下の3つの玄関、天井まで吹き抜けの広間、座敷、茶の間など10部屋以上。広い屋根裏には薪などを保管した。「どの家も南西の風を避けて東(アズマ)向きに建てられています」。穏やかに話す入道さんの祖父も父も銀行家だったが、往時には何人もの使用人を抱えた農家で、広間の調度品や裏の庭園のしつらえにも歴代当主の洗練された贅[ぜい]が伺える。

砺波の伝統的民家の特徴的な構造、入道家のワクノウチ造り。

「祖父も父も銀行家で農業に従事したのは私だけです」と入道さんは話す。今も奥様と2人で砺波の伝統の家を守っている。
「ご先祖が代を重ねて守ってきた家です。この先も大切に守っていかないと、という強い思いがあります」と話す入道さんは、奥様と2人、昔のままの暮らしで自然を風雅に楽しんでいる。「手入れや維持も大変です。でも、楽しみだと思って毎日を過ごしております」。
入道さんのように、カイニョとともに昔のままの民家に暮らす人は少なくなっている。住む快適さと現代の生活スタイルでいえば、技術が進んだ現代の住宅の方が高機能で便利だ。だが、郷土の伝統的な景観とともに代々住み継がれてきた「砺波の民家」への愛着は捨て難い。
松嶋一郎さんは、定年を機に都会から故郷にUターンするにあたり、3代続いた伝統的な外観を残しつつ、現代の生活に合うようにリノベーションした。「新築するつもりでしたが、やはり壊すのが惜しくなりました。生まれ育った家への愛着、どうせなら砺波の伝統の家を残そうと思ったのです」と松嶋さん。

3代が暮らしたアズマダチを現代風に再生した松嶋家。伝統的なワクノウチ造りを残し、広間には囲炉裏を設けて、仲間が集まって楽しく語らう場所にした。
子どもの頃の家を囲むような立派なカイニョはなくなったが、家の外観は伝統的なアズマダチだ。古民家の再生を手がけたのは大工棟梁の北嶋寛光さんだ。松嶋家とは互いに代々の間柄で松嶋家をずっと守ってきた。設備は最新、間取りも便利に変更されているが、家の随所に伝統が残されている。
天井の高い広々した広間は、「ワクノウチ」造りと呼ばれる伝統的で特徴的な構造をそのまま生かしている。2本の大きな大黒柱の間に、ウシと呼ばれる太い横梁を渡し、その上にハリマモンという縦梁を直交させて組み上げられ、釘は1本も使われていない。建て替えに際しては古材を随所に用い、屋敷林の杉の高木も使っている。
「カイニョは将来に備えてうまく考えられた屋敷林です。でも、新しいタイプの家が増えています。この砺波地方独特の民家を残したいですね、でないと技術も廃れる。実際、技術のある大工さんも少なくなりました」と北嶋さんは呟いた。
砺波平野の景観も少しずつ変わりつつある。が、山の展望台の眼下に広がる散居村の絶景は、胸がすくような広がりと美しさだ。特に夕暮れの景観は幻想的であった。